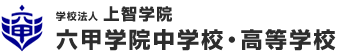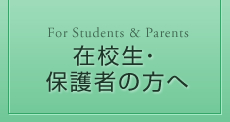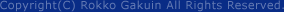《2025年4月7日 六甲学院中学校 88期生入学式式辞 校長講話》
真の正義と希望を生きる人へ-やなせたかしさんの人生観から
(1)88期の入学式-長い急坂を登って満開の桜の中で
新入生の皆さん、六甲学院中学校へのご入学、おめでとうございます。
保護者の皆様、ご子息の六甲学院へのご入学、本当におめでとうございます。
神戸の高台にある六甲学院では、ちょうど校内の桜が満開の美しい季節に、入学式が迎えられることを、たいへん嬉しく思います。新入生の皆さんは、六甲学院の88期生となります。
4月3日の入学オリエンテーションの初日に出会った一人の新入生は、六甲山の山裾にあるこの学校までの急な坂道を、重い荷物を背負いながら登り終えて、息を切らしつつ一階の西広場の階段前まで来て、教室に入るまでにもう一休み必要そうな様子でした。この新入生以外にも、おそらく「この長い急坂を、こんなに重い荷物を毎日背負いながら、通い続けられるだろうか?」という心配をするところから、六甲学院での学校生活が始まった新入生もいるのではないかと思います。それでも一ヶ月、二ヶ月と登り続けているうちに、途中で休まなくても登れるようになり、友人と通学路を上り下りする時間が楽しいものとなってゆくことでしょう。そしていつのまにか、この通学路を通っているだけでも、多少の事ではへこたれない体力と気力を獲得する日がきっと来ると思います。
⑵ 居場所や思い出の場所になる恵まれた六甲学院の教育環境
この学校には、広々とした土のグラウンドと人工芝のグラウンドがあり、体育でも部活動でも休み時間の遊び場としても使われています。蔵書が約7万冊あって、読書や探究学習や自学自習や映像鑑賞ができて、ながめも素晴らしい学習センターがあります。理科については、物理・化学・生物など教科ごとに実験室があります。遊び場とも憩いの場とも学習の場ともなる、庭園と呼ばれている一周500mほどの小山があります。本校舎南側の別館には美しい庭があり、カト研と呼ばれているグループのための部屋があります。講堂には演劇や音楽演奏ができる舞台があり、バレーボールやバスケットボールやバドミントンなどができる体育館があります。この学校での6年間の中でしっかりと学び知性を伸ばすとともに、自分が気に入る居場所や思い出に残るような場所を、ぜひ作ってほしいと思います。
⑶ 世界に視野を広げ、出会いと経験を通して将来の理想像を探す
健康で元気な体力・気力を身につけ、しっかりと学習に励みつつ、学校の中で自分の居場所を見つけて下さい。そうしたことと共に、新入生に願うのは、6年間のうちで自分がこんな人になりたいと憧れられるような理想像を見つけ、一生のうちでこんなことをしてみたいという何かを見つけることです。そのために自分から様々な出会いと学びの機会を生かして、視野を広げてほしいと思います。これまで小学校時代は新型コロナの世界的な流行の中で、一方的に日常生活が制約されるような影響を受ける経験はあったかと思います。これからの中学高校時代には、関西を離れ、日本を離れて、広い世界に目を向けて、被災地と防災、戦争と平和、貧困と正義等について、直接的な出会いや学びを通して、深く知る経験を積んでほしいと思います。中学での海山のキャンプ、フィールドワーク、東北研修、高校での海外研修・進路研修や6年間の社会奉仕活動の機会をぜひ生かしてくれたら、と思います。そして、この世界をよりよく変えてゆくために自分は将来何ができるのかについて、経験を通して深く考えられる人になることを願っています。
⑷ 理想像のひとつとしての「アンパンマン」と作者の人生観
4月に入るとNHKテレビ小説も新しくなり、先週から「あんぱん」という「アンパンマン」の生みの親である漫画家やなせたかしと奥様の物語が始まっています。子どもたちにとって、物心がつく頃から最初に好きになる絵本の主人公の一人は、このアンパンマンなのではないでしょうか? 実はアンパンマンは子どものための絵本やアニメの中のヒーローであるにとどまらず、青年や大人になっても自分が大切にしたい理想像のひとつとして、公言はしなくても心の内に持っている人は、少なくないのではないかと思います。
そして、アンパンマンの困っている人への優しさも、決して強くてカッコいいわけではないこのヒーローを作ったやなせたかしさんの人生観も、六甲が大切にしたい価値観と相通じるものがあるように思います。また、やなせたかしさんの戦争体験から発せられる言葉には、悲惨な戦争が止まない現代世界の中で、大事にすべき内容が含まれているようにも思います。六甲に入学した88期生にとって、世界に目を向けて平和や正義について考え始めるのに、よい入口になりますので、紹介したいと思います。
⑷ 正義が逆転する戦争と、逆転しない正義について
NHKのドラマでは、主人公「たかし」の次のような言葉で、第1話が始まりました。
「正義は逆転する。信じられないことだけど正義は簡単にひっくり返ってしまうことがある。じゃあ、決してひっくり返らない正義って何だろう。お腹をすかせて困っている人がいたら一切れのパンを届けてあげることだ。」
ドラマの始まりの最初の主人公のこの言葉は、やなせたかしさんの人生観の中心の一つであろうと思います。「正義は逆転する」という言葉は難しく思われるかもしれませんが、やなせさんは日中戦争時に召集されて中国へ派兵されます。その戦争の体験がこのセリフの中にも込められていて、アンパンマンが生まれる原点にもなっています。
『何のために生まれてきたの?』(やなせたかし PHP文庫)という本の中で、やなせさんは戦争と正義について次のように述べています。「(戦争に行ったら)とにかく殺人をしなくちゃいけない。殺す相手というのは、憎くも何ともないんですよ。家へ帰ればよいお父さんであったり、よい息子であったりするわけでしょう。でも、その人を殺さなくちゃいけない。相手も同じですよね。しかも、自分も殺されるかもしれない。」 「そこにはどんな目的があるのか。正義のためと言っても、爆弾が落ちれば、罪のない子どもも死んでしまう。戦争というのは、絶対にやっちゃいけないということを、骨身にしみて感じましたね。どんな理由があっても、戦争はやってはいけない。」 「戦争というのはいつも、いろいろな理屈をつけるわけです。向こうが非常に悪いから、正義のためにやるんだっていうけれど、正義の戦争なんてものはない。間違いなんです。……それぞれの立場の正義を、言い合う。言っている限りは、戦争は終わらないし、なくならないんです。」「正義っていうのは、立場が逆転するんですよ。僕らが兵隊になって向こうへ送られた時、これは正義の戦いで、中国の民衆を救わなくちゃいけないと言われたんです。ところが戦争が終わってみれば、こっちが非常に悪い奴で、侵略をしていったということになるわけでしょう。それで向こうは全部いいかというと、そんなことはない。……ようするに、戦争には真の正義というものはないんです。しかも逆転する。それならば、逆転しない正義っていうのは、いったい何か?」「困っている人、飢えている人に食べ物を差し出す行為は、立場や国に関係なく、『正しいこと』。これは絶対的な“正義”なんです。」「その飢えを助けるのがヒーローだと思って、それがアンパンマンのもとになったんですね。」
(5) アンパンマンと卒業生の正義と“For Others, With Others”
以上の引用にあるように、「“正義”の戦争というようなものはなく、人が人を殺す戦争はどんな理由があろうと、絶対にしてはいけない。戦争に真の正義はなく、絶対的な正義があるとしたら、それは飢えて困っている人に食べ物を差し出すことだ。」そう考えるやなせさんは、正義の行いについて次のように述べています。
「アンパンマンは、自分の顔をちぎって人に食べさせる。本人も傷つくんだけれど、それによって人を助ける。そういう捨て身、献身の心なくしては正義は行えない。」(『わたしが正義について語るなら』ポプラ新書)
六甲学院は“For Others, With Others”「他者のために、他者と共に」という教育目標を大切にしています。そのOthers-他者-とは、飢えて困っている人・弱い立場で他の人からの支えがなければ生きるすべのない人たちです。そうした人たちの存在を知り出会うために、インド募金や施設訪問、被災地訪問、海外研修などをして、自分たちに何ができるかを考える機会を作っています。やなせさんが述べようとすることと共鳴する方向性を、六甲学院は持っているように思います。
六甲学院で教育を受けた卒業生の中には、やなせたかしさんが言う「正義」を行おうと奮闘努力している人たちが、日本国内にも海外にも多くいて、そうした卒業生と出会い、話を伺う機会を持つプログラムが数多くあります。そうした機会を持つ中で、自分はこういうことをしたい、こういう人になりたいという憧れられる人や理想像を見出すこともあると思います。そして、絶望しかねないような暗い方向に向かっている世界の中で、諦めずに具体的に正義の実現のための活動をしている人たちと出会うことが、私たちの希望にもつながると考えています。
(6)一滴から世の中を変える「希望」―正義の同調者の波及へ
「 これからの時代に希望はあるんでしょうか?」という問いに、93歳の時のやなせさんは次のように答えています。
「もちろん、あると思っています。汚れた水の中に、一滴のきれいな水を入れても、なんの効果もないと思うんだけど、……一人じゃなく、10人、100人という具合に増えていけば、なんとかなっていくんです。……楽してお金をたくさん儲けようとばかり考えるんじゃなくて、自分のやっていることが世間にどういう影響を与えるか、ということを考えれば、やるべきことは自ずときまっていくと思う。そういう人が少しずつでも増えていけば、いまの世の中を変えていくことは不可能ではないと思います。」「『これはもう、ダメだ』と絶望しないで、一滴の水でも注ぐというか、そういう仕事を自分でもやっていく。そうすれば、それに同調してくれる人間が必ず出てくると思います。」(『なんのために生まれてきたの?』PHP文庫)
やなせたかしさんが言う通り、真の正義を実現する生き方を、すでに選んでしている卒業生が多くいますし、また、そうした生き方を選びめざそうとする先輩たちも多くいます。それが、六甲学院の誇りでもあります。そして”For Others, With Others”(「他者のために、他者と共に生きる人」)と共に“Multiplying Agents”(「正義の波及的連鎖をもたらす人」)を育てることが、イエズス会学校の目標であり使命でもあります。
六甲学院の一員になった新中一のみんなも、ぜひ周りの人たちの希望になるような生き方を、この6年間で身につけてもらえたらと思います。
(7)「何のために生まれて 何をして生きるのか」を探究すること
アンパンマンのマーチに「なんのために生まれて なにをして生きるのか 答えられない なんて そんなの いやだ!」というセリフがあるのを知っていると思います。3~4歳の幼児でも大きな声で歌っている歌でありながら、やなせさん自身が「人生のテーマソング」「永遠の命題」と言っているように、一生をかけて答えを探すような問いです。
答えは一人ずつ違うかもしれませんが、自分なりに「ひっくりかえらない正義」「逆転しない正義」を探すことは、答えを見つけ出すヒントになるかもしれません。また、やなせたかしさんの次のような言葉もヒントになるかもしれません。
「人間が一番うれしいことはなんだろう?長い間、ぼくは考えてきた。そして結局、人が一番うれしいのは、人をよろこばせることだということがわかりました。実に単純なことです。人は、人がよろこんで笑う声を聞くのが一番うれしい。」
自分ができることで、人を喜ばせたり平和な気持ちにさせる何かを見つけられたら、それが自分の幸せや生きがいにもつながるのだろうと思います。
日々の学びや行事や活動を通して、また六甲であれば特に先輩や卒業生との出会いとかかわりの中で、同じ方向性を持つ仲間を作りながら、「何のために生まれて 何をして生きるのか」について、自分なりに希望や生きがいにつながる答えが出せるように、これからの6年間を充実した、実りあるものにしてくれれば…と願っています。
改めて、六甲学院へのご入学、おめでとうございます。
《2025年4月7日 一学期始業式 校長式辞》
世界危機の中の希望の拠り処-ウクライナ侵攻と風の谷のナウシカ
(1)2025年度新学期を迎えて―春期定期演奏会の曲「ルパン三世」
2025年度の新学期が始まりました。春休みはどのように過ごしたでしょうか? 何か心に残る出来事はあったでしょうか? また、この新学期を、どんな気持ちで迎えているでしょうか? こんなことに挑戦してみたいとか、こういう人をめざしたい、こういう域まで到達したいなど、前向きに明確な目標を持って迎えられたらよいと思います。
私は春休み中の3月31日に、音楽部の定期演奏会を聴きに行きました。コロナ禍の影響で部員に高2最上級生はいないとのことでしたが、中1から高1まで30人弱が、どの曲も迫力のある見事な演奏をしていて、十分楽しむことができました。卒業生との息の合った演奏もあり、世代を超えた音楽部の結束の堅さを実感しました。
私にとって特に印象に残った演奏の一つは、アニメ映画「ルパン三世カリオストロの城」のテーマ曲でした。映画自体は1979年公開のずいぶん古い作品ですが、ほとんど誰もが聞いたことのある時代を超えた“現代的”な曲です。軽快で歯切れよく楽しい演奏でした。
⑵ 宮崎駿さんのアニメ映画製作に込められた願い
この曲が使われている「ルパン三世」の映画は、演奏会のパンフレットの説明にあった通り、のちにスタジオジブリを設立する宮崎駿(はやお)さんの劇場映画監督作品1作目です。ちなみに宮崎駿さんが劇場映画監督をした2作目は「風の谷のナウシカ」、3作目は「天空の城 ラピュタ」です。テレビでも放映されることがあるので、こうした作品を見たことがある人はいるかと思います。昨年2学期の生徒会朝礼スピーチの中でも、テレビで放映された「天空の城 ラピュタ」の感想を話してくれた生徒がいました。スピーチでは映画監督宮崎駿さんの自作映画についての、次のような印象的なコメントを紹介していました。
「古典的骨格を持つ冒険物語を、今日(こんにち)の言葉で語れないだろうか。正義は方便になり、愛は遊びになり、夢が大量生産品になったこの時代だからこそ、無人島が消され、宇宙が食いつくされ、宝物が通貨に換算されてしまう時代だからこそ、少年が熱い想いで出発する物語を、発見や素晴らしい出会いを、希望を語る物語を子供達は待ちのぞんでいる。自己犠牲や献身によってのみ獲得される絆について、何故、語ることをためらうのだろう。子供達のてらいや、皮肉や諦めの皮膚の下にかくされている心へ、直に語りかける物語を心底つくりたい。」(「子どもたちの心に語り掛けたい」映画パンフレットより) その時の生徒が話していたようにやや難解ではありますが、宮崎駿さんは次のようなことを伝えたかったのではないか、と思います。
(3)宮崎駿さんの言葉の趣旨を私なりに敷衍(おし広げて説明)すると……
「現代社会に生きる子どもたちに勇気や希望を与えロマンを感じさせるような、昔ながらの純粋な冒険物語を作りたい。今の時代は、物であふれた消費社会の中で、正義や愛や夢が、求めるに値しない安っぽい偽物(にせもの)かなぐさみもののように扱われている。また、私たちが暮らす地球や取り巻く宇宙は、自然破壊によって危機的な状況に陥っている。それにもかかわらず、人々はお金を稼ぎ増やすことにしか関心を持てなくなってしまっているのではないだろうか? そういう現代だからこそ、少年が新たな発見をしたり、素晴らしい出会いを求めて旅立ったり、希望に胸を膨らませられるような物語を作りたい。命をかけて実現したい正義や愛や夢は、現代でもありうるし、子どもたちも心の奥底ではそれを真剣に追い求めたいと願っている。そういう志ある人の望みを、あざけったりひやかしたりする風潮や人の目を気にして心がひるんだり諦めたりする風潮を跳ねのけて、体を張ってでも大切なものを守りたい、困難な状況にいる人を助けたいと、真摯に行動することを通して得られる人間の絆がある。そのことを、物語を通じて子どもたちに伝えたい。」そんな思いを宮崎駿監督は語っているように思います。それは「ラピュタ」だけでなく、他の作品の制作動機にも共通して根底にある宮崎駿さんの願いであり、少年たちに限らず現代の人たちに向けてのメッセージなのではないかと思います。
⑷ ロシアのウクライナ侵攻と「風の谷のナウシカ」
昨年の3月にアメリカのアカデミー長編アニメ賞を受賞した「君たちはどう生きるか」は長編映画として12作目です。私は彼の作品のすべてを見ているわけではなく、娘たちが小中学生の頃に一緒に見ることが多かったので、作品として知っているのは10代の少女が主人公のものが中心です。
様々な作品がある中で、特にロシアのウクライナへの侵攻があってから、時々2作目の「風の谷のナウシカ」を思い浮かべることがあります。1984年公開作品で40年以上も前に作られたのですが、今の時代を予見ていたかのような作品だと思います。物語では、文明が高度に進んだ先に、人間を自滅に向かわせるような世界を巻き込む戦争が起こり、それによる人類と自然の荒廃の中で、人間は何を大切にしたらよいか、どういう道を選び、どういう生き方をめざすべきか、を考えさせる作品として、今も観る価値があると思っています。
⑸ ウクライナに実在する「腐海」近隣の惨状と「ナウシカ」の物語
私と同世代ですと、深刻な現実を前に、アニメを思い起こして引き合いに出すことなど、不謹慎だと思われかねないのですが、2023年の初夏、ウクライナ南部の水力発電所のダムが破壊され大規模な洪水が発生した頃、ウクライナの悲惨さを見ながらナウシカの物語がふっと思い浮かぶことがある、と高校時代の友人に話をしたことがありました。するとその友人は、実は「風の谷のナウシカ」に出てくる「腐海(腐った海)」は、ウクライナの南部のクリミア半島との境目の海から着想を得ているのだと教えてくれました。映画の中で「腐海」は、有毒ガスを放ち人類の存続を脅かす菌類の森として描かれています。
その友人は国と国、大陸と大陸をつなげる海底通信ケーブルを作るための商談をする商社に勤めていたことがあって、文字通り世界をまたにかけて大きな仕事をしていました。ウクライナにもロシアにも仕事で行った事があり、ウクライナ南部の「腐海」と呼ばれる辺りは本当に海が腐ったようなにおいがするんだ、と話してくれました。聞いた時には半信半疑だったのですが、ブリタニカ百科事典のオンライン版によると、「『腐海』はウクライナ本土とつながるクリミア半島の付け根の部分にある約2,560平方キロにもなる広大な入り江の名称で、非常に強い塩分を含んでおり、塩を採掘する塩田として有名である」、とのことです。その干潟は悪臭を放ち内海はピンク色になることがあって、宮崎駿さんはその「腐海」という言葉に衝撃を受けて、映画の中に用いたそうです。ウクライナと「風の谷のナウシカ」とは、実際につながりがあることを知って、(1986年に起きたウクライナ北方の20世紀最大最悪のチェルノブイリ原発事故も併せて思い出しつつ、)ウクライナでの現実の出来事とアニメの内容とを関連づけて考えることの中で、何かしら現代への警鐘につながるような意味やメッセージが見出せるかもしれないと思うようになりました。
⑹ 宮崎駿監督「マグサイサイ賞」受賞の意義-過去の受賞者と照らして
スタジオジブリの宮崎駿監督は、昨年の秋、アジアのノーベル賞とも言われる「マグサイサイ賞」を受賞しています。「君たちはどう生きるか」が春にアカデミー長編アニメ賞を受賞した時には、様々なメディアで報道され大きな話題になりましたが、監督が秋にマグサイサイ賞を受賞したことについては、一部の新聞以外はほとんど報道されず、それほど話題にもなりませんでした。しかし、この受賞はもっと着目してよい出来事ではないかと思います。
マグサイサイ賞は、アジア地域で社会の進歩ために尽くしたり平和に貢献したりした個人や団体に贈られる賞です。選考委員会はフィリピンのマニラにあって、授賞式もそこで行われます。これまでに平和・国際理解の分野では、1962年にインドを始め世界各地の貧しく顧みられることのない孤独な人々を救済したマザー・テレサが受賞しています。ノーベル平和賞を受賞する17年も前のことです。日本人としては国連難民高等弁務官を務め、戦地を含めて厳しい状況にある難民を救済するために献身した緒方貞子(おがたさだこ)さんが1997年に受賞しています。また、極度に貧しく紛争が続き治安面で不安定なアフガニスタンで、命を懸けて医療活動と用水路建設に尽力した中村哲(なかむらてつ)さんが2003年に受賞しています。文化芸術面では、映画監督で「羅城門」「七人の侍」「生きる」などの作品で知られる黒澤明(くろさわあきら)さんが1965年に、作家として環境汚染に苦しむ人々の姿を描き、自然や人間の命の尊さを伝える「苦海浄土-わが水俣病」などを著した石牟礼道子(いしむれみちこ)さんが1973年年に受賞してきました。社会的・文化的に優れた貢献をしていると十分納得できる方々、特にその時代の世界の課題について真摯に取り組み、宮崎駿さんの言葉を借りれば「自己犠牲や献身によってのみ獲得される絆」を苦境にある弱い立場の人たちと結んできた人たちが、これまでに多く選ばれてきた、たいへん権威のある賞です。
宮崎駿監督の授賞式では授賞理由として、監督がアニメ作品を通じて人間性を照らし出し想像力をかき立てるとともに、平和や環境保全など多くの社会課題を題材とし、社会課題への理解に貢献した人物であることが挙げられていました。
芸術作品として優れた制作活動をしたことだけでなく、作品を通して平和や環境保全など多くの社会課題への理解に貢献している、という内容は、宮崎駿さんの作品への深い理解に基づく正当な評価だと思います。また、彼の「社会課題の理解への貢献」は、もっと広く知られてよい観点ではないかと考えます。
⑺ 「風の谷のナウシカ」-世界情勢の切迫した危機への警鐘として
受賞理由となった「平和や環境保全、自然との共生」をテーマとした宮崎駿の作品として、多くの人々に最初に注目されたのは、おそらく先ほどから取り上げている「風の谷のナウシカ」ではないかと思います。この点を理解してもらうためには、もう少し物語の背景を補足して説明する必要があるかもしれません。
「風の谷のナウシカ」の物語の舞台設定は、人類が近代文明によって自然を征服し繁栄を極めた後に、核兵器を思わせる壊滅的な破壊力を持った武器を使って、全面戦争を起こした1000年後の世界です。巨大産業文明が崩壊した後には、“荒れた大地に腐った海-腐海-と呼ばれる有毒の瘴気(しょうき・ガス)を発する森が広がり、衰退した人間の生存を脅かしていた”と映画のオープニングでは説明されています。
地球全土の自然は核兵器の放射能などで汚染されて荒廃し、高度に発達した産業文明の残骸は遺物と化し、いくつかの民族は生き残って町を形成し生活していたものの、地球絶滅の危機が迫っています。それにもかかわらず、人間は醜く民族間の紛争や戦争をし続けています。
宮崎駿さんと組んでこの映画のプロデューサーをしていたのは、高畑勲(たかはたいさお)さんです。後に「火垂るの墓」という、戦争の最中に神戸・西宮の地で生きた兄と幼い妹を描いた名作映画の監督を務めた人です。「風の谷のナウシカ」について、原作マンガをアニメーション化するにあたっての願いとして高畑さんは、「巨大産業文明崩壊後千年という極限の世界の彼方から、核戦争の危機をはらみ、快適さのみを追い求めて資源浪費と自然破壊にあけくれる現代社会を鋭く照らし返してもらいたい。」(映画パンフレットより)と述べています。
この作品に込められているのは、プロデューサーの要望にある通り、人類を短い時間で滅ぼしかねない核兵器使用への警告と、核戦争によって自然を壊滅的に長期間汚染し、人間を含めた生物全体の存続の危機につながることへの警告です。ロシアがウクライナへ侵攻して以降に生まれた今の世界情勢の危機感は、作品が発表された40年前よりも、より切迫したものとなり、この警告もより現実味を帯びたものとなっているように思います。
⑻ 主人公の人間性について-自然界の命と関わる姿と「希望」の拠り処
宮崎駿さん自身は、「風の谷のナウシカ」の原作の作品紹介では「人類の黄昏(たそがれ)期の地球を舞台に、人間同士の争いに巻き込まれながら、より遠くを見るようになっていく少女を主人公にした作品」と述べています。それとともに「戦いそのものを描く」のではなく「人間を取りかこみ、人間が依存する自然そのものとのかかわりが、作品の重要な主題」であるとも述べています。さらに「黄昏のときにおいても希望は見いだせるのだろうか。もしそれを求めるとしたら、どういう視点が必要なのか。」という問題を徐々に明らかにしたいと願っていたようです。すべてが八方ふさがりで滅亡にむかうしか道がないような「希望」の見出しにくい時代に、どのように「希望」を見出すことができるか、が作品の主要テーマのひとつとなっています。
実際にこの作品を見てもらった上でないと、中々伝わりにくいかと思いますので、機会があればぜひ作品を観てほしいのですが、この作品の中で世界に希望を見出す拠り処になるのは、ストーリーの展開や登場人物の言葉だけではなく、むしろそれ以上に、「ナウシカ」という16歳の少女の人間性のほうであるように、私には思えます。快活で優しく探究心旺盛な性格や、困難な出来事に前向きに取り組む姿勢や、生きとし生きるものすべてに共感し対話する主人公の姿に、作品を見ている側は、希望を感じるのではないかと思います。
もしも、小説や映画やアニメ・マンガなどの主人公の中で、“For Others, With Others(他者のために、他者と共に)”の生き方をしている人の例を挙げるのであれば、入学式で話題にしたアンパンマンはそのモデルの一人だと思うのですが、ナウシカも“For Others, With Others”の生き方を体現している人間像(モデル)の一人として取り上げてよいのではないかと考えます。
⑼ “For Others, With Others”の生き方の実践のために身につける“4C‘s”
六甲学院を含むイエズス会学校では、“For Others, With Others”をめざすべき人間像としていて、そのために教育活動の中で育成すべき人間の能力として、先ほどの入学式でサリ理事長も述べられていた通り、“4C‘s”を挙げています。4C’sとは、弱い立場の人たちへの共感(compassion)、課題を解明する知性面での有能さ(competence)、平和や正義に適う行動を選択し決断する良心(conscience)、課題ある現実の課題解決・変革のために実際にかかわり行動する実行力(commitment)を指します。
こうした能力・人間性を伸ばすことは、イエズス会教育に限られたものでなく、「他者に仕えるリーダー」として社会に貢献する生き方を目指すうえで、誰にとっても必須のものなのではないかと、最近は考えています。この時代の指針となりうる人物、例えば先ほど挙げた緒方貞子さんや中村哲さんなどは、確かにこの4C’sが優れたレベルでバランスよく備わっていた方々です。また私たちの卒業生で海外・国内で、世界をより良い方向に変えてゆくための働きをしている人たち(カンボジア研修、ニューヨーク・ワシントンDC研修、東京研修、シンガポール・マレーシア研修などで出会ったり、講演会や進路の日に講話をしてくださったりする先輩たち)を思い起こすと、やはりこの4C‘sがバランスよく備わっていることに気づきます。
⑽ ナウシカ―4C‘sをバランスよく身につけている主人公として
そして、今回話題にしているアニメ映画の主人公ナウシカもそうした4つの能力をバランスよく身につけている人物です。弱い立場の老人や子どもや自然界に生きる虫や動物・植物への共感(compassion)、腐海に生息する植物の胞子を採取し、きれいな水と土とで育成して、腐海が存在する意味を探究する優れた知性と知的好奇心(competence)、自分を含めて憎しみにかられる人間の弱さ・危険さを内省しつつ、自然界と人間、人間と人間との和解や平和のために進む道を選ぶ良心(conscience)、そしてその実現のために自分の命を懸けて行動する実行力(commitment)など、4C‘sに挙げられている能力をフルに発揮して、“For Others, With Others” の生き方を体現しています。現代の若い人たちにとっても、性別を超えて、めざすべき人間像の一人になりうる主人公なのではないかと思います。
⑾ 宮崎駿監督のマグサイサイ賞受賞スピーチと正義と平和の希求
さて、昨年の11月16日のフィリピンの首都マニラで開かれたマグサイサイ賞の授賞式に、スピーチの中で宮崎駿監督はアニメの制作者としては、意外と思われることに言及しています。第二次世界大戦中にマニラの市街戦で、約10万人ともいわれる非常に多くのマニラ在住の民間人が、アメリカ軍との市街戦の巻き添えで犠牲になったり、ゲリラの可能性を疑われて旧日本兵によって虐殺されたりしています。宮崎駿さんは受賞の喜びに代わるメッセージとして、そうした戦時中の過去を日本人は「忘れてはいけない」と述べています。
こうした出来事は、日本の中では、「忘れられている」というよりも、教育の中でもほとんと伝えられておらず「何も知らなかった」という日本人が多いのではないかと思います。しかし、アジアの国々の人たちと信頼し合える人間関係を作ろうとする時に、そうした話題を表に出さないとしても、知っていることが大事である場合があります。
世界に向けて日本に投下された核の悲惨さを知らせ伝えることが非常に大事であると同様に、もう一方で宮崎駿監督が話すように、戦争の中で日本が悲惨な状況を生み出す側でもあったことも知り、相互理解の関係を築くために忘れないでいることの大切さを、自覚する必要があるのだと思います。
日本が誇るアニメ映画監督の第一人者の中に、そうした人間として・日本人としての良心と正義と平和への希求があること、だからこそ、彼が創る作品は子どもだけでなく大人の心を動かすものになり、主人公が、これからの時代に人としての生き方を示す指針にもなり得ているのではないかと思います。
始業式にあたって、現代世界の危機的状況の中に希望を見いだす拠り所として、作品制作の奥にある宮崎駿監督の思いや願い・高い志について、私なりに紹介しました。また、今の時代に希望を保ち続け、この危機の迫る世界をよりよい方向に向かわせる指針となるモデルとして、彼の物語「風の谷のナウシカ」の主人公を取り上げました。皆さんも身近に見聞きしたり読んだり視聴したり、実際に出会う人たちの中で、希望や指針につながる何か・誰かを探し出し、自分なりにめざすべき目標としてくれたら、と願っています。
2025年度が、皆にとって大きな成長を遂げる一年となり、充実した、実り多い一年となることを、祈ります。