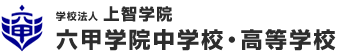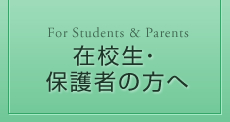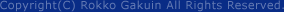校長先生のお話
《2026年1月7日 始業式 式辞》
この世界と日常の奥に在る「永遠なるもの」を見出す
(1)OB講演会の振り返り-「仕えるリーダー」と「永遠なるもの」の探究
(2)六甲生活で培われる信頼の基となる人間性
(3)目に見えない「大切なこと」を心で見ること
(4)すべてのことの内に「真善美聖」を見出すこと
(5)「瞑目」を通して日常の中に大切なこと・永遠なるものを見出す
《2025年 12月23日 終業式 校長講話》
救い主イエスの誕生と“For Others, With Others” - 人に寄り添い「祝福」を送り続ける生き方
(1)クリスマス-イエス・キリスト誕生の祝い
(2)”祝福”-「あなたの存在は喜び」という全肯定のメッセージ
(3)支えの必要な人々に”寄り添う”こと
(4)「恵まれている」ことの気づきから世界に繋がる生き方へ
(5)「祝福・受容」と「呪い・排除」-イエス誕生の物語と私たち
(6)「泊まる場所がなかった」-排除される側のイエスの父母
(7)排除されがちな立場の「羊飼い」に向けた喜びの知らせ
(8)共に喜び祝う相手として社会の隅にいる人々を選ばれる神
(9)弱く貧しい人々を心にかけ大切に思われる神-フィリピンのスラムでの経験
(10)社会の隅にいる人々と共にいて寄り添うイエス
(11)“For Others, With Others”-人に寄り添い“祝福”を送り続ける生き方
(12)クリスマスを本当の意味で祝うために
《2学期 始業式 校長講話 2025年8月29日》
台湾訪問-自由と平和を隣国と共に守ること
1.夏休みの出来事を振り返る機会を作ること
2.夏休みに訪れた二か国の共通点
3.台湾の姉妹校聖イグナチオ学院と教会活動施設の訪問
4.本格的な昆虫博物館のある成功高校訪問
5.台湾のシリコンバレー「新竹」のTSMCミュージアム等の見学
6.台湾留学の朝日新聞記事
7.自由と平和を隣国同士が共同で守ること
※ こうしたイノベーションによる優れた技術革新と製品生産をし続けることが、一企業にとどまらず国家の安全保障にもつながるという見解があります。台湾であれば、30年以上にわたり磨き上げた高い生産技術によって、世界のあらゆる分野で必要とされる優れた半導体を作り、世界に供給することが、他国からの攻撃や侵略から自国を守ることに繋がるという「シリコンの盾」と呼ばれる考え方です。こうしたイノベーション・ミュージアムの展示意図の中にも、一国を超えて共同で発明・開発・発展に向かう仕事の魅力・やりがい・面白味を伝えつつ、世界の優秀な開発者・技術者等とのネットワークを広げ、協力して優れたものの開発・生産・供給をし続ける「拠点」となることを通して、他国からの侵略を防ぎ平和の均衡を保っていこうとする姿勢も見られるように思います。武力競争ではかなわない小国が、平和を保つために選択できる道の一つなのではないかとも思います。
《2025年7月19日 一学期終業式 校長講話 》誰に寄り添い何のために学ぶのか―世界の変革をめざす「真のエリート」へ― (1)世界に広がるイエズス会学校で学ぶ私たちは共通して何をめざすか?
(2)東ティモール-他国に統治され苦難と紛争が長く続いた最貧国
(3)東ティモールの教育課題-教師の養成と使用言語の混乱
(4)教育設備面への支援―六甲学院から寄贈されたメルシュ机
(5)新しい平和な国を築く人間育成のための学校づくり
(6)経済的社会的エリートでなく社会に仕えるリーダー育成を
(7)“For Others, With Others”-「弱者(Others)」に寄り添う真のエリート
(8)各個人が幸福になるために社会構造の変革をめざす教育
(9)若者の未来とめざしたい生き方を奪う戦争
(10)生命と未来を奪う戦争への警告と「何のために生き学ぶのか」の探究
※「加害の歴史と向き合わずして『平和』を語れるのか」2024.8.10 “Dialogue for People” https//d4p world 参照
《2025年4月7日 六甲学院中学校 88期生入学式式辞 校長講話》
真の正義と希望を生きる人へ-やなせたかしさんの人生観から
( 1 ) 88 期の入学式-長い急坂を登って満開の桜の中で
新入生の皆さん、六甲学院中学校へのご入学、おめでとうございます。
保護者の皆様、ご子息の六甲学院へのご入学、本当におめでとうございます。
神戸の高台にある六甲学院では、ちょうど校内の桜が満開の美しい季節に、入学式が迎えられることを、たいへん嬉しく思います。新入生の皆さんは、六甲学院の88期生となります。
4月3日の入学オリエンテーションの初日に出会った一人の新入生は、六甲山の山裾にあるこの学校までの急な坂道を、重い荷物を背負いながら登り終えて、息を切らしつつ一階の西広場の階段前まで来て、教室に入るまでにもう一休み必要そうな様子でした。この新入生以外にも、おそらく「この長い急坂を、こんなに重い荷物を毎日背負いながら、通い続けられるだろうか?」という心配をするところから、六甲学院での学校生活が始まった新入生もいるのではないかと思います。それでも一ヶ月、二ヶ月と登り続けているうちに、途中で休まなくても登れるようになり、友人と通学路を上り下りする時間が楽しいものとなってゆくことでしょう。そしていつのまにか、この通学路を通っているだけでも、多少の事ではへこたれない体力と気力を獲得する日がきっと来ると思います。
⑵ 居場所や思い出の場所になる恵まれた六甲学院の教育環境
この学校には、広々とした土のグラウンドと人工芝のグラウンドがあり、体育でも部活動でも休み時間の遊び場としても使われています。蔵書が約7万冊あって、読書や探究学習や自学自習や映像鑑賞ができて、ながめも素晴らしい学習センターがあります。理科については、物理・化学・生物など教科ごとに実験室があります。遊び場とも憩いの場とも学習の場ともなる、庭園と呼ばれている一周500mほどの小山があります。本校舎南側の別館には美しい庭があり、カト研と呼ばれているグループのための部屋があります。講堂には演劇や音楽演奏ができる舞台があり、バレーボールやバスケットボールやバドミントンなどができる体育館があります。この学校での6年間の中でしっかりと学び知性を伸ばすとともに、自分が気に入る居場所や思い出に残るような場所を、ぜひ作ってほしいと思います。
⑶ 世界に視野を広げ、出会いと経験を通して将来の理想像を探す
健康で元気な体力・気力を身につけ、しっかりと学習に励みつつ、学校の中で自分の居場所を見つけて下さい。そうしたことと共に、新入生に願うのは、6年間のうちで自分がこんな人になりたいと憧れられるような理想像を見つけ、一生のうちでこんなことをしてみたいという何かを見つけることです。そのために自分から様々な出会いと学びの機会を生かして、視野を広げてほしいと思います。これまで小学校時代は新型コロナの世界的な流行の中で、一方的に日常生活が制約されるような影響を受ける経験はあったかと思います。これからの中学高校時代には、関西を離れ、日本を離れて、広い世界に目を向けて、被災地と防災、戦争と平和、貧困と正義等について、直接的な出会いや学びを通して、深く知る経験を積んでほしいと思います。中学での海山のキャンプ、フィールドワーク、東北研修、高校での海外研修・進路研修や6年間の社会奉仕活動の機会をぜひ生かしてくれたら、と思います。そして、この世界をよりよく変えてゆくために自分は将来何ができるのかについて、経験を通して深く考えられる人になることを願っています。
⑷ 理想像のひとつとしての「アンパンマン」と作者の人生観
4月に入るとNHKテレビ小説も新しくなり、先週から「あんぱん」という「アンパンマン」の生みの親である漫画家やなせたかしと奥様の物語が始まっています。子どもたちにとって、物心がつく頃から最初に好きになる絵本の主人公の一人は、このアンパンマンなのではないでしょうか? 実はアンパンマンは子どものための絵本やアニメの中のヒーローであるにとどまらず、青年や大人になっても自分が大切にしたい理想像のひとつとして、公言はしなくても心の内に持っている人は、少なくないのではないかと思います。
そして、アンパンマンの困っている人への優しさも、決して強くてカッコいいわけではないこのヒーローを作ったやなせたかしさんの人生観も、六甲が大切にしたい価値観と相通じるものがあるように思います。また、やなせたかしさんの戦争体験から発せられる言葉には、悲惨な戦争が止まない現代世界の中で、大事にすべき内容が含まれているようにも思います。六甲に入学した88期生にとって、世界に目を向けて平和や正義について考え始めるのに、よい入口になりますので、紹介したいと思います。
⑷ 正義が逆転する戦争と、逆転しない正義について
NHKのドラマでは、主人公「たかし」の次のような言葉で、第1話が始まりました。
「正義は逆転する。信じられないことだけど正義は簡単にひっくり返ってしまうことがある。じゃあ、決してひっくり返らない正義って何だろう。お腹をすかせて困っている人がいたら一切れのパンを届けてあげることだ。」
ドラマの始まりの最初の主人公のこの言葉は、やなせたかしさんの人生観の中心の一つであろうと思います。「正義は逆転する」という言葉は難しく思われるかもしれませんが、やなせさんは日中戦争時に召集されて中国へ派兵されます。その戦争の体験がこのセリフの中にも込められていて、アンパンマンが生まれる原点にもなっています。
『何のために生まれてきたの?』(やなせたかし PHP文庫)という本の中で、やなせさんは戦争と正義について次のように述べています。「(戦争に行ったら)とにかく殺人をしなくちゃいけない。殺す相手というのは、憎くも何ともないんですよ。家へ帰ればよいお父さんであったり、よい息子であったりするわけでしょう。でも、その人を殺さなくちゃいけない。相手も同じですよね。しかも、自分も殺されるかもしれない。」 「そこにはどんな目的があるのか。正義のためと言っても、爆弾が落ちれば、罪のない子どもも死んでしまう。戦争というのは、絶対にやっちゃいけないということを、骨身にしみて感じましたね。どんな理由があっても、戦争はやってはいけない。」 「戦争というのはいつも、いろいろな理屈をつけるわけです。向こうが非常に悪いから、正義のためにやるんだっていうけれど、正義の戦争なんてものはない。間違いなんです。……それぞれの立場の正義を、言い合う。言っている限りは、戦争は終わらないし、なくならないんです。」「正義っていうのは、立場が逆転するんですよ。僕らが兵隊になって向こうへ送られた時、これは正義の戦いで、中国の民衆を救わなくちゃいけないと言われたんです。ところが戦争が終わってみれば、こっちが非常に悪い奴で、侵略をしていったということになるわけでしょう。それで向こうは全部いいかというと、そんなことはない。……ようするに、戦争には真の正義というものはないんです。しかも逆転する。それならば、逆転しない正義っていうのは、いったい何か?」「困っている人、飢えている人に食べ物を差し出す行為は、立場や国に関係なく、『正しいこと』。これは絶対的な“正義”なんです。」「その飢えを助けるのがヒーローだと思って、それがアンパンマンのもとになったんですね。」
( 5 ) アンパンマンと卒業生の正義と“ For Others, With Others ”
以上の引用にあるように、「“正義”の戦争というようなものはなく、人が人を殺す戦争はどんな理由があろうと、絶対にしてはいけない。戦争に真の正義はなく、絶対的な正義があるとしたら、それは飢えて困っている人に食べ物を差し出すことだ。」そう考えるやなせさんは、正義の行いについて次のように述べています。
「アンパンマンは、自分の顔をちぎって人に食べさせる。本人も傷つくんだけれど、それによって人を助ける。そういう捨て身、献身の心なくしては正義は行えない。」(『わたしが正義について語るなら』ポプラ新書)
六甲学院は“For Others, With Others”「他者のために、他者と共に」という教育目標を大切にしています。そのOthers-他者-とは、飢えて困っている人・弱い立場で他の人からの支えがなければ生きるすべのない人たちです。そうした人たちの存在を知り出会うために、インド募金や施設訪問、被災地訪問、海外研修などをして、自分たちに何ができるかを考える機会を作っています。やなせさんが述べようとすることと共鳴する方向性を、六甲学院は持っているように思います。
六甲学院で教育を受けた卒業生の中には、やなせたかしさんが言う「正義」を行おうと奮闘努力している人たちが、日本国内にも海外にも多くいて、そうした卒業生と出会い、話を伺う機会を持つプログラムが数多くあります。そうした機会を持つ中で、自分はこういうことをしたい、こういう人になりたいという憧れられる人や理想像を見出すこともあると思います。そして、絶望しかねないような暗い方向に向かっている世界の中で、諦めずに具体的に正義の実現のための活動をしている人たちと出会うことが、私たちの希望にもつながると考えています。
(6)一滴から世の中を変える「希望」―正義の同調者の波及へ
「 これからの時代に希望はあるんでしょうか?」という問いに、93歳の時のやなせさんは次のように答えています。
「もちろん、あると思っています。汚れた水の中に、一滴のきれいな水を入れても、なんの効果もないと思うんだけど、……一人じゃなく、10人、100人という具合に増えていけば、なんとかなっていくんです。……楽してお金をたくさん儲けようとばかり考えるんじゃなくて、自分のやっていることが世間にどういう影響を与えるか、ということを考えれば、やるべきことは自ずときまっていくと思う。そういう人が少しずつでも増えていけば、いまの世の中を変えていくことは不可能ではないと思います。」「『これはもう、ダメだ』と絶望しないで、一滴の水でも注ぐというか、そういう仕事を自分でもやっていく。そうすれば、それに同調してくれる人間が必ず出てくると思います。」(『なんのために生まれてきたの?』PHP文庫)
やなせたかしさんが言う通り、真の正義を実現する生き方を、すでに選んでしている卒業生が多くいますし、また、そうした生き方を選びめざそうとする先輩たちも多くいます。それが、六甲学院の誇りでもあります。そして”For Others, With Others”(「他者のために、他者と共に生きる人」)と共に“Multiplying Agents”(「正義の波及的連鎖をもたらす人」)を育てることが、イエズス会学校の目標であり使命でもあります。
六甲学院の一員になった新中一のみんなも、ぜひ周りの人たちの希望になるような生き方を、この6年間で身につけてもらえたらと思います。
(7)「何のために生まれて 何をして生きるのか」を探究すること
アンパンマンのマーチに「なんのために生まれて なにをして生きるのか 答えられない なんて そんなの いやだ!」というセリフがあるのを知っていると思います。3~4歳の幼児でも大きな声で歌っている歌でありながら、やなせさん自身が「人生のテーマソング」「永遠の命題」と言っているように、一生をかけて答えを探すような問いです。
答えは一人ずつ違うかもしれませんが、自分なりに「ひっくりかえらない正義」「逆転しない正義」を探すことは、答えを見つけ出すヒントになるかもしれません。また、やなせたかしさんの次のような言葉もヒントになるかもしれません。
「人間が一番うれしいことはなんだろう?長い間、ぼくは考えてきた。そして結局、人が一番うれしいのは、人をよろこばせることだということがわかりました。実に単純なことです。人は、人がよろこんで笑う声を聞くのが一番うれしい。」
自分ができることで、人を喜ばせたり平和な気持ちにさせる何かを見つけられたら、それが自分の幸せや生きがいにもつながるのだろうと思います。
日々の学びや行事や活動を通して、また六甲であれば特に先輩や卒業生との出会いとかかわりの中で、同じ方向性を持つ仲間を作りながら、「何のために生まれて 何をして生きるのか」について、自分なりに希望や生きがいにつながる答えが出せるように、これからの6年間を充実した、実りあるものにしてくれれば…と願っています。
改めて、六甲学院へのご入学、おめでとうございます。
《2025年4月7日 一学期始業式 校長式辞》
世界危機の中の希望の拠り処-ウクライナ侵攻と風の谷のナウシカ
(1)2025年度新学期を迎えて―春期定期演奏会の曲「ルパン三世」
⑵ 宮崎駿さんのアニメ映画製作に込められた願い
(3)宮崎駿さんの言葉の趣旨を私なりに敷衍(おし広げて説明)すると……
⑷ ロシアのウクライナ侵攻と「風の谷のナウシカ」
⑸ ウクライナに実在する「腐海」近隣の惨状と「ナウシカ」の物語
⑹ 宮崎駿監督「マグサイサイ賞」受賞の意義-過去の受賞者と照らして
⑺ 「風の谷のナウシカ」-世界情勢の切迫した危機への警鐘として
⑻ 主人公の人間性について-自然界の命と関わる姿と「希望」の拠り処
⑼ “For Others, With Others”の生き方の実践のために身につける“4C‘s”
⑽ ナウシカ―4C‘sをバランスよく身につけている主人公として
⑾ 宮崎駿監督のマグサイサイ賞受賞スピーチと正義と平和の希求
《2025年3月1日 六甲学院高等学校 82期生卒業式 上智大学 曄道学長 祝辞》
皆さん、ご卒業誠におめでとうございます。また、ご父母、ご関係の皆さまにも心よりお祝い申し上げます。節目の時を迎えられ、ご本人もご家族も、そして皆さんを見守り続けるご関係の方々も、それぞれの感慨をお持ちのことと思います。
さて、社会は黎明期にあります。技術革新、国際関係の複雑化、新たな価値の出現など、私たちが直面している社会変革の進行は、これまでの延長ではない人間社会の在りようを描こうとしています。私たちの社会は重要な岐路にあると言えるでしょう。「岐路にある」と表現した理由は、おそらく人間社会は、今、いくつかの選択肢を持っているであろうからです。今日の革新的なデジタル技術の出現を、産業革命時の蒸気機関の出現のインパクトに準える見方がありますが、技術革新が次から次へと社会の変革を促した当時も、そして今までも、おそらく人間社会は多くの選択肢を持っていたでしょう。様々な無数の選択肢を前にして、私たちは利便性、高効率、大量生産を過度に追い求め、地球環境に対する犠牲を見過ごしました。自らが選択し、何かを追い求め、何かを享受した事実があるのですから、それは私たちの選択の結果であったと言わざるを得ません。
このことは個人についても当てはまります。今みなさんは卒業を経て新たな道を進むその入り口に立っていると言えます。その道は皆さんによって選択されたものです。今後、皆さんの人生は、多層的にいくつものステージによって構成されていきます。これまでの中学、高校への進学によって到達したステージでは、主にある枠組みの中にある体系化された学びの機会が提供されてきました。これからのステージでは、多くの人には大学を指すでしょうが、学びは皆さん自身によって、自由に様々に選択することによって彩られていきます。そしてその彩こそが皆さんの個性になるのです。その選択は、大きさ、重要性、選択肢の数から、いつその選択を行う機会が訪れるかというタイミングに至るまで、今予測できるものではありません。その折々において、「選択の自由度をいかに多く持ち得るか」が、人生をデザインするための支配的な要因、要素となるでしょう。例えば大学での学び、研究は、この選択の自由度を拡げるための大きな力になると言えます。皆さんの人生における数々の選択は、その対となる選択との比較はできません。皆さんが通る道は、実に多くの選択によって形作られますが、無数の選択肢の中から皆さん自身によって選ばれ形成された道筋、すなわち人生は一通りだけです。これが人生の醍醐味であろうと思います。この道筋に納得がいく、誇りを持てるということを、充実した人生と呼ぶのだと思います。
上智大学は六甲学院と同じ学校法人に属しています。その教育精神は、「他者のために、他者とともに」として共有されています。この教育精神は、支えの必要な人たちに、弱い立場にある人たちに向けた私たちのあるべき姿勢を示しています。皆さんがこれから向き合うマルチステージへの選択はハードルの低いものではないでしょう。むしろ果敢にチャレンジするハードルの高さが皆さんを奮い立たせることでしょう。しかし、どのような状況にあろうとも、皆さんの耳を、目を、心を、立場の弱い人にも向けてください。先頭に立つ者こそ、すべての人の後になり、すべての人に仕える者になるべきと聖書は説いています。様々な選択によって自分自身の目標に近づいていくということが、他者に仕える自分の在りようを高めていくことでもあって欲しいと思います。真のリーダーとは、自分の目標がアップデートされていく中でこの心得を実践しようとする人であろうと思います。真のリーダーとは、まさに自分が困難な時にあってもこの心得を実践しようとする人であろうと思います。
本日祝辞としてお話させて頂いた「選択」の意味は、この社会においてますます重要性を帯びるものと認識しています。無数にある個人の選択、組織の選択、そして社会の選択が、知らぬ間に人間社会の、そして地球の将来を描き出していきます。そしてその社会像と私たち一人ひとりの人生は密接に関係し、どちらかだけが満足のいく結果を得るという結末が訪れることはありません。自分の成功の陰で弱者が放置されることがあってはなりません。地球環境の悪化の中で、一時の利便や利益が尊重されてもなりません。これからの個人の、組織の、社会の日々の「選択」は、責任のある拠り所によってなされていくべきものと思います。そのような自覚の下で、皆さんが人生を大いに謳歌してくださることを祈念致します。高度な専門性を、世界に通じる広い教養を、他者との合意形成を得るコミュニケーション力を、そして私たちの教育精神である「他者のために、他者とともに」に基づく深い人間性を身に付けた皆さんにとって、「責任ある選択」の追求もまた、人生の彩なのであろうと確信し、私からの祝辞とさせて頂きます。
2025年3月1日
《2025 年 3 月 1 日 六甲学院高等学校 82期生卒業式 校長式辞》
「感謝」と「共通善」の追求
―「命」と「人の支え」に感謝し、壁を越えて共に平和を築く仲間づくりへ
(1) 中高6年間の成長
82期の皆さんのご卒業、おめでとうございます。保護者の皆様、ご子息のご卒業、本当におめでとうございます。82期の皆は、この6年間をどういう思いで振り返っているでしょうか。少年期から青年期に向かうこの6年間の心身の成長には、著しいものがあります。例えば、入学して程なく行われる体育祭総行進では、先輩の指導についてゆくのに必死で、目の前の生徒の後を追って歩くのに精一杯だった中学1年生が、高校3年生になると立派に全校生を指揮して総行進を創り上げ、後輩の手本として堂々と歩くまでに成長します。
(2) 高3生の朝礼スピーチー「支えられて生きている『命』への感謝」
昨年6月初めの、体育祭を週末に控えた月曜日に、高校3年生のある生徒が、生徒会朝礼で、「感謝」をテーマに4~5分ほどの短い時間、話をしてくれました。命の大切さや生まれて今ここに生きていることへのありがたさについて、語ってくれました。
「自分は700グラムという超未熟児で生まれた。生まれ落ちてそのままの状態だったら生きてはいられなかった。それが、設備の整った病院で手厚く医療スタッフからの手当・看護のもとに命を保つことができた。そして、今、こうして好きなスポーツが思い切りできるくらい元気に生きている。自分をあきらめずに生んでくれた親への感謝とともに、超未熟児で生まれながらも多くの人たちに支えられて、今生きていることへの感謝の気持ちを忘れずに、恩返しをしてゆきたい」と話してくれました。体育祭をするにあたって、「後輩は先輩へ、先輩は後輩への感謝を忘れないでほしい」とも加えて話をしてくれていました。
(3) 体育祭-受け継がれたテーマ「覇」と先輩(78期生)への感謝
82期は、中2から高1までの3年間、思いがけなくコロナ禍の中で生活することになり、学校生活にも様々な制約がありました。皆にとって中1指導員のいる学年であった78期生は、2020年、3ヶ月にも及ぶ新型コロナ学校閉鎖の影響を受けて、無念な思いの中で体育祭が中止となり、高校生活最後で最大の行事を後輩たちと創り上げることができませんでした。皆にとっては中学2年生の時の出来事でしたが、その時高3であった78期の先輩たちの気持ちを察し、お世話になった先輩たちに向けてできることはないかという思いを、その後も保ち続けていたのだろうと思います。78期が決めていた「覇(はたがしら)」というテーマを82期はそのまま受け継いで、総行進を含めて見事な体育祭を仕上げてくれました。それは82期が6年間のうちで示した行為の中で、最も印象に残ることの一つでした。中1から自分たちの成長を願って日々世話をしてくれた先輩たちに向けて、感謝の気持ちを表し、立派に体育祭を創り上げることで自分たちの成長も表現し、恩返しをしたいという思いの表れだったのだと思います。こうした先輩・後輩の関係は、六甲学院ならではの出来事であるともいえるでしょう。
(4) 後輩を励まし褒めねぎらい感謝しつつ、「高み」を目指す姿勢
総行進をするにあたって、歩きながら図柄を作る上で目印になる、グラウンドに打つ杭(くい)の数は、昨年度は1800個であったと聴いています。それだけのポイント数の多さからして、例年以上に複雑で難度の高い絵模様に、生徒たちは挑戦したのだと思います。六甲で伝統として受け継がれてきた六列交差、六角形の幾何学模様、一昨年野球界の覇者となった阪神タイガースの黄色と黒色を基調にした虎のマーク、古代から昨年のパリオリンピックまで受け継がれてきた聖火、漫画界の覇(はだがしら)であるドラゴンボール、昨年の干支(えと)の空を勢いよく昇る龍、全校生1000人で作るテーマ「覇(はたがしら)」の絵文字など、一つひとつがすばらしく見ごたえのあるものでした。
仕上がるまでの過程は、必ずしも順調であったというわけではなかったと思います。前々日、前日の練習風景を見ていると、本番に間に合うだろうかとやや不安に思うようなことも、高校3年生の中にはあったのではないでしょうか。より理想に近い形を追究する中で修正・微調整を繰り返しつつ、なかなか思い通りには行かないあせりやいらだちを感じていた上級生もいたかも知れません。練習光景を見ながら私が感心したのは、上級生の下級生たちへの声掛けの中に、感謝や励まし・ねぎらいの言葉が終始中心であったことです。あせりやいらだちは、容易に怒りの感情へと移ってしまい兼ねないと思うのですが、「ありがとう」「よくなった」「おつかれ」「よく頑張っている」と、下級生を終始、よく励まし褒(ほ)めていました。褒めつつ励ましつつ、的確に注意やアドバイスをその中に込めていました。そうして、励ましねぎらい、感謝の言葉を伝え続けていたことが、しんどい中でもう一歩下級生を頑張らせる力になっていたように思います。高校3年生たちの、難易度が高いからと諦めたり妥協したりせずに、粘り強く、その高度で困難なものを、より完成度の高いパフォーマンスへと創り上げていこうとする姿勢にも感心しました。
上級生たちのそうした姿勢のうちに、6年間の身体面だけでなく精神的な面での著しい成長を感じますし、そうした経験を通して、六甲学院の卒業生として、また「社会に仕えるリーダー」としての在り方を身につけてきたのではないかと思います。
(5) 海外研修-現在の国際情勢の中で多様性を体験する意義
もうひとつ、私が82期の学年行事として印象深かったのは、一昨年の6月に行われたシンガポール・マレーシアへの研修旅行でした。82期は、コロナ禍からなんとか抜け出して、最初にシンガポール・マレーシア研修旅行に皆で行くことのできた学年でした。卒業してこれからより広い世界に向かう中で、この研修旅行の体験が、何らかの形で活かされればと願っています。
このシンガポール・マレーシアへの研修は、今、世界の中で国家間や民族間の対立・分裂・分断による紛争が起こり、環境問題がより深刻化し経済格差が広がってゆく中で、特別に意味のある体験ができる旅行ではではないかと思います。シンガポールは民族・宗教・文化などの違いを乗り越えて共存の道を探る上で、一つのモデルとなりうる国だと考えています。街歩きをしたりバスで街中を巡ったりする中でも実感することですが、この国には世界の縮図でもあるかのように、中華系・マレー系・アラブ系・インド系等の多民族・多文化が存在し、イスラム教・キリスト教・仏教等の多宗教が国内で共存しています。そして、水や資源の不足が致命的な弱点・課題としてありながらも、経済と外交努力を通して周囲の国々とも共存して発展してきた国です。
背景が多様な人々の集まりである故に国際語でもある英語を共通言語として使い、国が将来を見据えた明確な目標やヴィジョンを持って、街作りや教育や環境問題などに取り組んできました。シンガポール国立大学の学生たちとの世界課題についてのセッションや、現地で活躍する六甲の卒業生との交流会の中でも、日本とは対照的に、多様性を特長として受け入れて、むしろ積極的に活かそうとする前向きさを、この国に感じた生徒もいたのではないかと思います。
(6) 学校交流-垣根を超えて協調・和解する原体験として
82期の皆が、研修旅行の中で最も表情が明るく楽しんでいたのは、マレーシアのアヤヒタム村での高校生たちとの学校交流だったのではないかと思います。マレーシアはイスラム教文化の影響が強く、交流校もその文化を大切にしている公立学校だったのですが、同世代として国や民族・宗教・文化の垣根を越えて交流ができた、貴重な体験だったのではないでしょうか。若い同世代同士ならば2~3時間の交流の中で、こんなにも親しくなれるのかと思うくらい、和気藹々(わきあいあい)とした雰囲気でした。
そうした一つ一つの体験が、今後、さらに分裂や分断へと向かいかねない世界の中で、融和や協調や和解へとつながる方向へ物事を進めてゆくための原点のひとつになれば、と願います。そして、何らかの形でそうした働きを担う「社会に仕えるリーダー」として、将来活躍してくれることを期待しています。
(7) 「共通善を追求する社会的交友」を築く
教皇フランシスコは、現在全世界のカトリック教会のリーダーであり、六甲の創立修道会と同じイエズス会の司祭であった方ですが、青年に向けて次のようなメッセージを述べています。「若者の皆さんには、内輪のグループを超え出て、『「共通善を追求する社会的交友」を築いていただきたいと思います』」(『キリストは生きている』169)。さらに教皇は、反目や敵意によって家庭が崩壊し、国が滅び世界が戦争によって壊されつつある危機を指摘しつつ、次のように語ります。「すべての人の幸福を思って『共通善を追求する社会的交友』を築くならば、共通の目的に向けてともに闘うために、互いの相違を問題にしないというすばらしい体験を手にすることができるでしょう」。
ここで言う共通善とは、英語でいえば“common good”で「個人の価値観や思想の違い、国家や民族間の対立を超えて、皆が人として幸福に暮らすことができる「だれにとっても(common)よいもの(good)」=「普遍的な善」を指します。「皆が幸福に暮らせる誰にとってもよいもの」ですから、「共通善」を「平和」と置き換えるとわかりやすいかもしれません。「共通善を追求する社会的交友を築く」とは「違いの壁を越えて共に社会の平和を追求する仲間を作る」ことと言ってもよいように思います。
実は「共通善を追求する社会的交友」は、六甲生が六甲学院の在学6年間で、委員会活動・社会奉仕活動やクラブ活動をする中でも、クラス・学年の運営や、体育祭・文化祭・研修旅行などの学校行事・学年行事を担う中でも、築いてきた経験のあるものだと思います。少しでも皆に喜んでもらおう、その場をより良くしてゆこうと、意見や価値観の違いがあっても話し合って仲間同士が協力してきた経験は、それに当たります。また、82期生は身近な学校の仲間を超えて、シンガポール・マレーシアやカンボジア、ニューヨークやガーナに行って、「互いの相違を超えて共通の目的に向けてともに闘う友人」となりうる人たちと、すでに海外でも出会っているかもしれません。今後も、国内・海外を問わず友人を作り、それがこれから多くの人々の幸福をめざす社会的交友になることはありうると思いますし、違いの壁を越えて平和を築く仲間作りをめざしてほしいと思います。
この世界に命を与えられて今生きていること、多くの人たちに支えられて今があることに感謝しつつ、困難な状況にあったり失望したりしている人たちに、生きる勇気や希望を与える人となりますように、そして様々な違いや壁を超えて多くの人々が幸せに暮らすために、仲間と共にこの世界をより良くし平和をもたら
《2025年1月8日 始業式 校長講話》
For Others, With Others ―「共感」から「希望」をもたらす人へ
(1)「希望」を取り戻す一年に―カトリック教会の「聖年」にあたって
年が明けて2025年が始まりました。カトリック教会は25年に一度「聖年(聖なる年)」を迎えます。2025年は、この聖年に当たります。聖年の中心テーマは『希望』です。教皇フランシスコは次のように述べています。
「すべての人は希望を抱きます。明日は何が起こるか分からないとはいえ、希望はよいものへの願望と期待として、一人ひとりの心の中に宿っています。けれども将来が予測できないことから、相反する思いを抱くこともあります。信頼から恐れへ、平穏から落胆へ、確信から疑いへ―。わたしたちはしばしば、失望した人と出会います。自分に幸福をもたらしうるものなど何もないかのように、懐疑的に、悲観的に将来を見る人たちです。聖年が、全ての人にとって、希望を取り戻す機会となりますように。」
この教皇フランシスコの言葉にある通り、より良い方向へむかう願望や期待を込めて希望を抱くのが、私たちの自然な姿なのだと思います。しかし、将来への不安や恐れから悲観的・懐疑的になり、希望を失い落胆している人と出会うことがあります。また、将来が幸福になることを信じて、希望を抱き続けることが難しい時代でもあるのかもしれません。教皇フランシスコが祈るように、すべての人にとって希望を取り戻す機会が与えられる1年になれば、と願います。
(2)日本と世界の「現実」-大災害と戦争に苦しみ犠牲になる人々
具体的に、日本の現実を見てみると、昨年の元旦に起きた能登半島沖の地震から1年が経ち、阪神淡路大震災から30年を向かえようとしています。能登半島に暮らす住民の中には、大きな地震とその後の土砂崩れや津波によって大切な人を失い、被災者の多くは生活再建のめどが立たず、さらに9月下旬には追い打ちをかけるような豪雨災害によって、立ち直る気力すら失われている人々がいます。
世界の現実を見てみると、ロシア軍のウクライナ侵攻による戦争も、イスラエル軍のパレスチナ地域のガザで暮らしている住民を攻撃する紛争も、停戦・終戦の糸口が見いだせないまま、現在も続いています。ウクライナにもパレスチナにも大切な人を失い、子どもや女性を含めてこれまで普通に日常を暮らしていた人々が武力による攻撃に常時怯(おび)えて生活しています。食料や安全な水や医療が足りない中で、怪我や感染症に苦しみ、戦争の終結を望みつつ実現しない状況の中で、生きる気力さえ失われている人々がいます。
(3) “Others”に希望をもたらすために―他人事を自分事とすること-
そうした日本の災害地域や世界の紛争地域だけでなく、私たちが暮らす地域の中にも、もしかしたらクラスの中にも、周囲から気づかれなかったり理解されない中で、様々な悩みや苦しみを抱えたまま、希望が見出せない人がいるかもしれません。
イエズス会学校として六甲教育が “Men for Others, With Others” を目指しており、その「Others」 とは、特に顧みられることの少ない、困難な状況の中で苦しむ人たちであるとすれば、こうした人たちのことをより深く知り、その人たちのために何ができるか、どうしたらこうした人々に生きる希望をもたらすことができるのか、と考え行動に移すことは、私たちの課題だと思います。その一方で、日本のことも世界のことも、周囲にいる人たちのことでさえ、今の自分の日常生活からは遠い出来事のように思えて、自然には関心を向けることのできない、という場合も私たちには多いのではないかと思います。他人事を自分事として捉え返すこと、少なくともより身近な出来事として感じ取れるようにすることは、私たちにとって大切なチャレンジではないかと思います。
(4)大災害や戦禍に苦しむ人々をより身近に感じること
阪神間で比較的平穏な生活を送っているように思われる私たちですが、30年前に大震災を経験しました。堅固に見えるマンションも含めて家々が倒壊し、あちらこちらで火災が発生し、6400人を超える人たちが亡くなりました。
被災地であるこの地域で暮らしていれば、犠牲者の中には、大抵は何人かの知り合いがいます。私の家族にとって最も悲しかった出来事は、当時4歳だった長女の親しい友だちが、倒壊した家の下敷きになって亡くなったことでした。そのご家族は、お父さんお母さんと、小学生の長男と、4月から小学校1年生になるはずだった長女と、私の子の友人だった4歳の次女の、子ども3人が、川の字になって寝ていて、その5人家族のうちお母さんと長男だけが助かり、お父さんと女の子2人は崩れた天井の梁(はり)に胸を圧迫されて命を落としました。
4月から1年生になるはずだった長女さんは、すでにランドセルを買ってもらっていて、小学生になるのをとても楽しみにしていました。そのお母さんの申し出で、私の長女が2年後に小学生になるときに、そのランドセルを譲り受けて、6年間使わせていただきました。
当時、神戸、西宮、芦屋など、地震の揺れが激しく倒壊家屋が多い所で暮らしていた地元の人たちにとっては、思い出しては心が揺り動かされたり涙を流したりするような出来事が、何かしらあったのではないかと思います。そうした悲しい現実を共有しながら、水道や電気やガスが止まり、衣食住に事欠く生活の中で、近所同士が自然に助け合って生き延びていたような日々を、多くの人たちが経験していました。大切な人を失った時に、何が残された人たちにとって生きるための励まし・勇気・慰めになるかはわからないのですが、大切な人が生きていた証を何らかの形で共に生きてきた人たちが受け継いでゆくこと、分かち合い共有してゆくことが、悲しみつつも生きようとする望みにつながることはあるかもしれません。
現在はもちろん阪神淡路大震災の被災地は、日常的には衣食住に心配することのない生活をしています。街に大震災があったような痕跡もほとんどありません。10代の生徒の皆にとっては30年前に今暮らしている地域で起こった大震災の出来事は、その当時の大変さを含めて、遠い昔の別の場所の出来事であるかのように、想像も理解もしにくいでしょう。
しかし、大切な人を失った人にとっては、悲しみが癒えるまでには長い時間を要しますし、30年経ち一見日常の生活を取り戻したように見える今でも、傷の痛みを抱えながら生きている人は少なくないのではないかと思います。
また、世界では今も続いている戦争や飢餓にしても、日本で暮らしていれば、80年間戦争のない平穏な状況が続いており、(それは有り難く幸せなことでもあるのですが)実体験として経験することはありません。そういう今を生きる六甲生たちにとって、大災害や戦禍の中で苦しむ人たちのことを、どれだけ身近に感じられるかは、先ほども述べたように一つのチャレンジであると思います。
(5) “涙で洗われた瞳でなければ見えない現実”-過酷な境遇への共感
話の冒頭で「希望の聖年」についての言葉を紹介した教皇フランシスコは、2015年にフィリピンを訪れた折に、『マニラにおける若者への講話』の中で次のようなことを話されました。
「ある程度困らない生活を送る人たちは、涙を流すとはどんなことかが分かりません。人生には、涙で洗われた瞳でなければ見えない現実があります。一人ひとりが振り返ってみてください。涙が流せていただろうか。空腹の子、路上で麻薬を打つ子、家のない子、捨てられた子、虐待された子、社会から奴隷のように酷使される子、彼らを見て泣いただろうか。それともわたしの頬を伝うのは、さらにほしがって泣く者の身勝手な涙だろうか」。
この言葉と関連して、教皇は「キリストは生きている」(使徒的勧告・カトリック中央協議会)という文書の中で、さらに次のように述べています。
「あなたよりもひどい境遇にある若者のために、涙を流すことを覚えて下さい。思いやりや優しさは、涙によっても表現されるのです。……涙が流れるならば、あなたは相手のために、心から、何かをすることができるはずです。」
この言葉の最後の部分にある通り、他者のために心から何かをする、つまりFor Others, with Others の生き方を私たちが身につけるためには、相手の過酷な境遇を見て涙を流すほどに心を揺り動かされ共感することが、ひとつの出発点になります。日々の生活の中で、周囲の人々に気遣う「思いやりや優しさ」を身につけることも、For Others, With Othersの生き方に向かう大切な道だろうと思います。
(6)インド募金-ハンセン病施設の前向きで健気な子どもたちへの共感
さて、六甲学院の私たちが、実際にFor Others, With Othersの生き方に向かうために、共通して毎月取り組んでいるのは、インド募金です。本日はHRで、インド募金をテーマに話し合いをする予定になっています。インド募金の送金先は、インド東北部ダンバードという町のダミアン社会福祉センターです。ここは、ハンセン病を治療し療養するための総合施設で、特に寮で暮らす子どもたちの教育と生活のために、私たちの募金は使われています。養育施設を伴う学校で生活している子どもたちとの交流の様子は、11月のインド訪問報告会で見た通りです。報告会で見聞きしたことや、今日のHRでの社会奉仕委員の説明や話し合いを通して、インド募金についてより深く理解し、自然に協力したいと思えるような機会になってくれることを期待しています。インド募金も、遠く離れた所で困難を抱えつつ前向きに生きている健気な子どもたちのことを、他人事でなく、どれだけ身近に感じられるか、が私たちの取り組むインド募金の課題の一つになるのだろうと思います。
(7)インド募金の意義-現在と将来を「希望」を持って生きるために
募金を、その果たす役割も意味も感じられないままするのと、実際に誰かの役に立っていると感じながらするのとでは、私たちにとっての行為の意味合いは大きく変わってくると思います。インド募金は、親がハンセン病という感染症を患っているため親元を離れて暮らしている子どもたちが、学校と寮で友人と過ごす生活を支えるためにしています。また、そうした子どもたちがしっかりとした教育を受けることで将来にむけての準備をし、自分と家族の生活を支える仕事に就くことを支援するためでもあります。それとともに、自分がハンセン病の親を持つために偏見を受けてきたその苦しみを、次の世代の子どもたちが味わうことのないよう、差別されることのない社会づくりに貢献するためでもあります。そして、そうしたよりよい将来に向けて、今を「希望」を持って生きるために、私たちはインド募金をしていると、言ってよいのではないかと思います。
(8)お年玉募金-東チモールの貧困村落の子どもたちへの教育支援
1月のインド募金は来週から始まりますが、「お年玉募金」とも呼ばれていて、いつもよりも多くお小遣いをいただいている分、普段の月よりも多めの募金協力を呼びかけています。多く集まる募金の一部は東チモールに送られています。この、1月のお年玉募金のもう一つの送金先である東チモールという国については、多くの生徒たちは、インドと比べるとよりなじみが薄いかと思います。アジアの最貧国と言われていて、21世紀に入って2002年にインドネシアから独立した新しい国です。21世紀の初頭まで続いた独立戦争で荒廃した国の教育を立て直し、将来を担う人間を育成することが急務になっています。
六甲学院で教鞭を取られていた浦善孝神父が2012年から東チモールに移り住み、「学びたいすべての子どもたちが、貧富の隔たりなく学べるきちんとした学校」作りを目標に、2013年1月に貧しい村にイエズス会学校「聖イグナチオ学院」を設立しました。今も中心スタッフとして働いています。この1月に13期目の入学生を迎える学校です。コロナ禍の中で3年前には豪雨による洪水の大災害にも見舞われ、がけ崩れで教職員にも犠牲者が出たりしましたが、なんとか危機を乗り越えてきました。洪水は4月初めのことでしたが、当時の社会奉仕員は首都も村落も広範囲で大きな被害となっていることを聞いて、自主的に募金活動をしてくれました。
聖イグナチオ学院は、まだまだ国全体の教育制度の整わない東チモールで、学校教育のモデルケースになることを目指している学校です。首都のディリからも通える距離にあるので、都市部の、東チモールの中では比較的恵まれた家庭の子どもたちと、学校近隣の貧しい村落の家庭の子どもたちが、一緒に机を並べて学んでいます。使われている机は創立当初から、六甲学院で2012年まで使われてきた木製の手作りのものです。イエズス会の修道士でドイツ人マイスターのブラザー・メルシュという方が六甲学院の創立当初から、六甲生のために作られた机が、厳しい熱帯地域の気候にも耐えて今も役に立っています。1月の募金の一部は、この学校のある貧しい家庭の子どもたちの奨学金-この学校で学び続けるための教育支援金―として主に使われています。
(9)将来への「希望」につながる教育
これまで述べてきたように、インド募金は、インドのハンセン病の家庭の子どもたちの教育費として、また1月のお年玉募金の一部はアジアの最貧国東チモールの子どもたちの教育費として、使われているのですが、それはこうした子どもたちにとって、教育を受けることが将来への「希望」につながるからでもあります。
インドではハンセン病への差別が厳しいだけでなく、インド政府はすでに国としてハンセン病は克服した病気として支援を打ち切っています。そういう状況の中で、もしも六甲学院まで援助を途絶えさせてしまえば、支援している子どもたちの未来は希望を持てる道が閉ざされると言っていいと思います。十分な教育を受けられないままでは、インド社会で差別の対象となるハンセン病者の子どもたちは、生活を支えるだけの収入を得られる仕事にはつけずに、一生街に出て人から金品を請い求めて暮らす物乞いとならざるを得なくなります。
東チモールの貧しい村で暮らす子どもたちは、恵まれない食生活の中で十分な栄養も取れずに、ちょっとした疫病で亡くなることも珍しくありません。聖イグナチオ学院では給食で栄養のある食事を提供しつつ、将来家族を養えるような仕事に着けるように、しっかりとした学力が身に着く教育しています。
教育を受け続ける環境を子どもたちに提供するということが、どれだけインドや東チモールや、今年2回目の訪問旅行を企画しているカンボジアの子どもたちにとって、将来の夢や希望を抱くための支えになっているか、こうした地域とかかわりをもつ六甲学院にいる間に、知ってほしいと思います。そして「教育は希望である」という観点をぜひ理解し意識してもらえれば、と願っています。
(10)「現実」を見て共感することを通して「希望」をもたらす人へ
まずは、教皇フランシスコが「人生には、涙で洗われた瞳でなければ見えない現実があります」と述べるような「現実」を見ることのできる目を持つ人間、そうした「現実」を生きる人々に共感できる人をめざせたら、と思います。そのためには、日々の授業や学校活動が、日本や世界で起こる様々な事象や出来事に共感する機会、時に涙を流すほどに心が揺り動かされる機会になれば、と思います。早速本日行われるインド募金ホームルームも、中学2年生が1月末に被災地を訪れる東北研修も、また3学期に参加希望者を募る予定のカンボジア研修なども、そうした成長の機会になることを願っています。
遠い国々に限らず私たちの周囲にも、差別、偏見、虐待、貧困に苦しんでいる人はいるかもしれません。また日本では大災害によって、世界では戦争・紛争によって、希望を失いかけ、将来に対して懐疑的に、悲観的にならざるおおえなくなった人々がいます。そうした人たちにとって、希望を取り戻すために、支えや助けができる人になることを、めざすべき人間像の一つにしてくれたら、と願っています。過酷な「現実」を生きる人々に共感し、「希望」をもたらす人へと成長することを、六甲学院で学ぶ私たちの今年の目標のひとつにしたいと思います。
《2024年12月23日 終業式 校長講話》
「理性と良心のもとに命を尊び、世界に平和をもたらす人間へ」
(1)クリスマス直前の教会の祈りから
カトリックの教会では、昨日(12月22日)、クリスマスを迎える直前の日曜日のミサの中で、共同祈願として、次のような祈りを会衆の皆が一緒に唱えました。
「人を傷つけ、命の尊厳と自由を踏みにじる悪の力を退けて下さい。弱者を思いやり、支える人々の輪が力強く広がっていきますように。」
「混迷する世界の中で人が歩むべき道を示して下さい。一人ひとりが神の導きに心を開き、よりよい社会にするために連帯していけますように。」
六甲学院に通う私たちにも、登下校時や学校内の日常生活の中で、弱者を思いやることができなかったり、人を傷つけてしまったりすることはあると思います。そうした自分に気づき、弱い立場の人たちを傷つける側ではなく、そうした人たちを「支える人々の輪」を力強く広げる人になることをめざしたいと思います。また「混迷する世界」の中で、人として「歩むべき道」を見出し、国や民族や宗教や立場を超えて、「命の尊厳と自由」を大切にする「よりよい社会」を創るために、 「連帯」できる人になることをめざしたいと思います。今日の講話では、この2つの祈りとも繋がる、六甲学院の卒業生の集まりの話から、始めたいと思います。
(2)初代校長に叱られた卒業生の体験-理性と良心を持った人間になる
六甲学院の卒業生から生徒時代の体験談を伺うことは、行事や同窓会や講演会などで度々あります。それが、私にとって楽しみでもあり貴重な機会だとも思っています。これまでも、その中で印象に残る話は、朝礼などで紹介したり学院通信に書いたりもしてきました。しかし、年配の方々にお会いしても、初代武宮校長から直接教えを受けた経験を聴く機会は、不思議と殆どありませんでした。それが、11月半ばに名古屋で、卒業生の組織である伯友会の中部地区の集まりがあった時に、武宮校長から直接個人的に叱られた経験を、話して下さった方がおられました。27期の卒業生で現在70歳代の方です。皆にとってはおじいさんの世代かと思います。
その卒業生の話は、今から60年前の出来事になります。その方は子ども時代にはかなりやんちゃだったそうで、中学1年生の時に、クラスメイトに対して、相手の気持ちを察せずに行き過ぎた悪戯(いたずら)をして傷つけてしまったことがあったそうです。それが見つかって、武宮先生から真剣に厳しく叱られたとのことです。自分の心ない行動を諭(さと)す中で、校長は自分に「人間と猿との違いは何だと思うか?」と問いかけられたそうです。皆なら、そう問われてどう応えるでしょうか?
その方は、人間と猿との違いを考えるにはまだ幼くて、何も思いつかず応えられなかったとのことですが、まだ中1のその人に武宮校長は次のように話されました。
「人間には理性と良心がある。人間は、理性と良心をもとに行動するということだ。それができないのなら、猿と同じだ。お前は決して猿になってはいけない。」
60年前にそう諭された70歳代の大先輩は、次のように話しました。「武宮校長から叱られたときのその言葉が、その後の自分の一生の行動基準なっています。『自分は今人間として生きているか、理性と良心のもとに行動しているか、猿になっていないか?』と、常に自分に問いかけ心がけながら、行動してきました。粗暴でわきまえのないところのあった自分が、何とか人としての道を踏み外さずに、これまでまっとうに生きて来られたのは、武宮校長から叱られたこの経験があったからです」。
(3)人として大切にすべき価値観の核(中心軸)をつくる体験
六甲という学校は、その人にとっての一生の拠り処となる中心軸を、在校中の経験の中で与えられる機会のある学校だと思います。27期のこの方の話も、そのことを表す、一つの逸話です。よりよい人になりたいという願いや、自分の弱さを見つめる正直さや、相手から真剣に発せられたメッセージを受け入れる素直さがあれば、今の六甲でも同様の経験をすることは、あるはずです。
今の時代の生徒たちの多くは、ご家族からも小学校の先生からも大事に守られながら育てられてきていると思います。この卒業生が初代校長から受けたような、厳しく叱られる経験は、殆どの人にはなかったのではないでしょうか。生徒によっては、真剣に諭される中で相手の伝えたいメッセージを受け取ることには、慣れていない面もあるかもしれません。また現代は、良いところを褒めて一人ひとりの個性を育てる中で、自己肯定感を育む教育が大切な時代であることも、確かだと思います。ただ、人として大切にすべきことに気づかなかったり、相手の気持ちを察せられずに傷つけたりしてしまう自分に対して、教師や親の言葉の中に、真剣に自分の至らなさを気づかせ、よりよい人間になるためのメッセージが込められているとするならば、それを素直に受け止め、自分の内面にある弱さ・足りなさを見つめ、自分をより良い方向に変えられる人間にはなってほしいと思います。
27期のこの大先輩のように、そうしたことの積み重ねが、人として大切にすべき価値観の核を作る体験につながることは、六甲生にはあるのだと思います。
(4)理性と良心に拠って命・人権・平和を大切にする世界へ
さて、中部地区の同窓会では、そこから話題は自分の恩師との思い出話に移るのかと思ったのですが、同窓会の人たちの話題は思わぬ方向にむかいました。
「理性と良心のもとに行動するのが人間で、そうでなければ、猿であるとすると、今の世界は『猿の惑星』になりつつあるのではないか」というご年配の方の発言から、現在とこれからの世界の在り方についての話題にむかいました。何人かの先輩たちの話の流れは、概ね次のようなものでした。
“コロナ禍前までは少なくとも、世界の人々が平和を願い、戦争のない世界にしてゆこうとしてきたし、環境の課題に国を超えて協力して取り組もうとしていた。人間の命の尊厳や人権や民主主義を大切な価値観として守っていこうという機運は高まりつつあったように思うし、少なくともよりよい方向にむっているように思っていた。それなのに、そうした動きがここ数年ですっかり後退してしまっている。特にロシアのウクライナ侵攻やイスラエルによるガザの民間人への殺戮などにみられるように、命や人権や平和を大切なものとして守るよりも、世界の政治リーダーたちは、理性や良心を失って自国の利益や繁栄をより優先する価値観へと傾いている。それに伴ってヨーロッパや中東の不安定な情勢に、核戦争への危機さえも感じられる。こうした世界になりつつある中で、これからを生きる若い世代のために、自分たちに残された時間はそう多くはないかもしれないが、何かできることはないだろうか?” そうしたことが卒業生たちの話題になってゆきました。
中部地区の同窓会に集まったのは19期から66期までの20名ほどで、私よりも年上の20期代から30期代前半の方々が多く集まられていたのですが、それぞれの方々がグローバルな視野の中で世界を眺める見識を持っておられることに、また真剣に今の世界を憂い、これからのためにできることを模索する姿勢に、六甲学院の世代を超えた卒業生たちの共通の特徴を感じましたし、自然に尊敬の念を抱くことのできた同窓会でした。
(5)核爆弾の悲惨さを語り継ぎ人類の危機を救う方向へ
卒業生方々が指摘されるように、今の地球が人間としての理性と良心を失って「猿の惑星」になりつつあるというのは、本当のことのように思います。そのことに地球の危機を感じて、理性と良心のもとに行動を起こしメッセージを発している人たちに目を向け、その人たちのメッセージに耳を傾けることが、今後の世界を考えるうえで極めて大切なことのように思います。平和を願い、戦争のない世界にして行こうとすること、生命や人権や平和を大切な価値観として守っていこうとすること、そうした方向性を持つ動きに共感し協力してゆくことが、大切なのだと思います。
そうした、これからの世界の方向性を指し示す取り組みの一つとして、今年ノーベル平和賞に選ばれた団体が、日本原水爆被害者団体協議会なのではないかと思います。核兵器がどれだけ悲惨な殺戮をもたらすか、その非人道性を語り継ぎ、核廃絶の必要性を唱えてきた団体です。日本は原子爆弾によって広島で約14万人、長崎で約7万4千人の尊い命が奪われています。68年前に結成された日本被団協の結成宣言には「自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」と、その基本精神が記されています。
12月10日のノルウエー・オスロ市庁舎で行われたノーベル平和賞授賞式では、代表の田中煕巳(てるみ)さんは「核のタブーが壊(こわ)されようとしていることに、限りないくやしさと憤りを覚える」「人類が核兵器で自滅することのないように」「核兵器をなくしていくためにどうしたらいいか、世界中のみなさんと共に話し合い、核廃絶を求めていただきたい」と訴えていました。
受賞の背景には、国連のグテーレス事務総長が「核戦争のリスクは過去数十年で最高レベル」と語り、核軍縮を専門とする黒澤満大阪大名誉教授が「ここ数年で核兵器が本当に使われ人類が全滅するかもしれないという危機感が生まれた」と指摘している現実があるのだと思います。今回の受賞理由の中では、核兵器について「何百万人もの人々を殺し、気候に壊滅的な影響を及ぼし得る。核戦争は、我々の文明を破壊するかもしれない」と述べられています。ノーベル委員会の委員長は授賞式で日本被団協が「核兵器が2度と使われてはならない理由を身をもって立証してきた」とその功績を紹介しつつ、「記憶が新たな人生への契機をもたらすこともある」として、核兵器が人類にもたらした悲惨さを新たに記憶にとどめ、次世代へとつないでゆくことの大切さを強調しています。
講話の最初に紹介した祈りにあるように、「人を傷つけ、命の尊厳と自由を踏みにじる」出来事が日常レベルだけでなく国家レベルでも広まりつつある「混迷する世界」の中で、「人が歩むべき道」の一つは、まずは「体験」の記憶を受け継いでゆくことだと思います。様々な立場の違いはあるかもしれませんが、日本被団協の結成宣言に「私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」とあるように、唯一の被爆国としての体験を私たちも知ることを通して、核爆弾の悲惨さ・理不尽さと「人類と核兵器とは共存できない」こと、核兵器の使用は人類の自滅に繋がりかねないことを訴え続けることは、これからの世界がより平和的に存続し続けるため、人類の危機を救うために大切で必要なことではないかと思います。
(6)苦しみ傷む世界の人々と共に住み、平和と救いをもたらす生き方
クリスマスの中で祝われる救い主イエスの誕生は、神がこの世界全体をご覧になって、このままではこの世界は救うことができなくなると思われ、具体的な生き方と言葉を通して救いの道を人々に示す人間として、神がご自分の愛する子をこの世界に遣わされたという出来事です。
イエズス会の創立者、イグナチオ・デ・ロヨラは、同様に神がこの世界をご覧になるようにこの世界を見渡して、アジアの貧困の悲惨さとと魂の救いのない状況に目を向け、そこに生きる人々を救うために、自分の最も信頼するフランシスコ・ザビエルをアジアに遣わし、ザビエルは命がけでアジアの様々な地域を巡り、私たちは神にとって大切な存在であることを伝えるために、日本にまでも宣教に来ました。
アルペ神父はそのフランシスコ・ザビエルに憧れて、宣教の地として日本に来ることを望み、広島で原爆を体験して、世界に核兵器が人間にもたらす悲惨さと非人間性を伝えた人物です。そのアルペ神父は、被災地で負傷する人の命を救うために尽くし、後にイエズス会教育のモットーである“Men for Others” を提唱した人物でもあります。
イエス・キリストからイグナチオ、ザビエル、アルペ神父へと受け継がれてきた、この世界をグローバルな視点で見て、この世界をなんとか救えないか、良い方向に変えられないかという思いは、六甲学院の創立にも受け継がれ、卒業生の内にも生きています。先ほども述べたように、この秋に出会った中部地区の同窓会での、卒業生たちの世界への見方や姿勢にも、それは一貫して受け継がれているように思います。
世界の中の傷み苦しむ姿を見て、そこへと向かいその内に共に宿り住み、その中で、悲惨さの最中に苦しむ人を助け救い、人々のうちに平和をもたらす、この“For Others, With Others”の生き方が、私たちに示された「混迷する世界の中で人が歩むべき道」だと思います。始まりは、この世界に暮らす人々の苦しみ傷みを見て、この世界を救いたいと願い、イエス・キリストをこの世界に生まれさせた、神の思いであり、クリスマスの出来事でした。その“For Others, With Others”の道を、その生き方と言葉を通して生涯をかけて示されたのがイエスです。イエスの誕生から、六甲学院創立後の卒業生へと綿々と引き継がれてきたその願いと行動を、私たちも受け継いでゆければと思います。そして、人として理性と良心のもとに生き、危機的な状況に向かいつつあるこの世界に、平和をもたらすために生き働く人になれますように、祈り願いたいと思います。