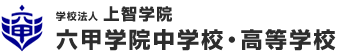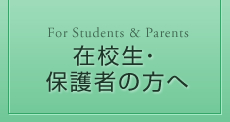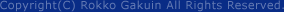《2025年7月19日 一学期終業式 校長講話 》
誰に寄り添い何のために学ぶのか―世界の変革をめざす「真のエリート」へ―
(1)世界に広がるイエズス会学校で学ぶ私たちは共通して何をめざすか?
1学期には、東ティモールの姉妹校で働かれている浦神父様から、朝礼の短い時間でしたが、お話を伺うことができました。この終業式の講話では、東ティモールの独立までの歩みと独立後の課題、そして六甲学院との関りについて紹介したいと思います。また、東ティモールの姉妹校「聖イグナチオ学院」創立の目的と六甲学院の2代目シュバイツェル校長の言葉「エリートでありなさい」を例に挙げながら、現代世界の中でイエズス会学校とそこに身を置く私達は何をめざすのかについて、考えてみたいと思います。
(2)東ティモール-他国に統治され苦難と紛争が長く続いた最貧国
東ティモールは、2002年にインドネシアから独立して20年少々の若い国です。現在の人口は約130万人、淡路島を除いた兵庫県と岡山県を合わせたほどの広さで、アジアで最も貧しいと言われている国です。16世紀からポルトガルの植民地の時代が長く続き、第二次世界大戦中は日本軍が占領していた時期が3年半ほどありました。※1
ポルトガルの統治から1975年に独立を宣言した直後に、隣国インドネシアが軍事侵攻し、20年以上にわたって統治されました。独立運動に対するインドネシアからの弾圧が繰り返され、独立賛成派・反対派の対立が紛争に発展し、時に家族・親戚同士の中でも争い合い、当時の国民約100万人のうち20万人、つまり5人に1人が弾圧と紛争とで死亡したり行方不明になったりしました。独立にあたって、それまで行政も教育も医療も要所を締めていたインドネシア統治者は、建造物や道路などを含むインフラを徹底的に破壊しながら本国に引き上げていきましたので、殆ど何もない焦土と化したところからの独立・建国になりました。極貧の中で他国からの統治に苦しめられ続け、長く過酷な時期を経ての独立でした。国連の全面的な支援のもとで、治安維持や人道支援が行われ、政府機構や公共サービスが設立され、敵対し傷つけあってきた国民同士が和解するための平和構築の試みも、民間NGOの協力を受けながら続けられてきました。
(3)東ティモールの教育課題-教師の養成と使用言語の混乱
教育については、教師になるべき世代が青少年時代を混乱期の中で過ごし、十分教育の機会が与えられないまま教壇に立つことになりました。授業の使用言語として、公用語がポルトガル語と現地のテトゥン語、実用語としてインドネシア語と英語、さらに30を超える現地語が存在する中で、どの言語を使用するかの方針が定まらず、学校教育の混乱の一因となっています。東ティモールにおける学校教育の使用言語の課題を中心に、研究を続けている先輩に71期卒業生の須藤玲さんがいます。長い間、過酷な統治と戦乱と貧困とに苦しんできた東ティモールが、将来にわたって平和な国を築き、人々が幸福に暮らす社会をつくるためには、未来を生きる青少年の教育が極めて大切であるからこそ、教育言語の課題を克服するための助けになりたいと願い、研究を続けています。上智大学卒業後東大の修士・博士課程に進み、現地を行き来しつつ研究し、今年から東大の助教となっています。いつか須藤先輩からも話を伺う機会があれば、と思います。
(4)教育設備面への支援―六甲学院から寄贈されたメルシュ机
教員や教育言語だけでなく教育設備面にも課題がありました。十分な校舎や机椅子が揃わず教材もないまま、それぞれの学校での授業が始まりました。浦神父が今も働いているイエズス会学校、聖イグナチオ学院は、国中にまともに教育が成り立つ環境がない中で、独立から約10年が経った2013年に創立されました。私はその1年後に最初のティモール訪問に行ったのですが、まだ、首都ディリの町中には壊されたビルがあちらこちらに痛々しく残り、道路も至る所で陥没しているような状況でした。
浦神父は、創立の前年に東ティモールに入り、開校準備から姉妹校設立に関わられました。この学校の生徒たちは、六甲生が創立期から80年近く使ってきたメルシュ机と呼ばれる木製の机を使っています。机の呼び名になっているメルシュというのはドイツ人の修道士のお名前で、メルシュ机は木工の職人としてマイスターの称号を持つ方が、創立期から六甲の生徒たちのために作り続けて来られた重厚な机です。六甲創立75周年に当たって、9割近くの机椅子を入れ替えることになって、その方が作って教室や図書館で使われていた机椅子や書棚を、創立される姉妹校に寄贈することになりました。
今年の4月から上智大学の学長になられた杉村美紀先生は、教育学科の開発教育の専門家で、1ヶ月ほど前にご本人から次のような話を伺いました。ちょうど研究のために東ティモールを訪れた2013年に、六甲学院の机が港からコンテナで学校に届いたところに出くわしたそうです。日本の神戸から東ティモールへ船に乗せて送られてきたその頑丈そうな机に、とても感激されたとのことです。今も地域懇談会や高校生と保護者に向けた説明会で、イエズス会学校の世界的なつながりとイエズス会教育について紹介する時には、神戸の六甲学院から教育支援として送られた机のことを話されるそうです。
熱帯地方の過酷な気候の中で、他国から送られた家具類は壊れてしまうことが多いのに、メルシュ机は、創立期から今も使われ感謝されています。生徒が日常使う机や図書館の本棚など、メルシュさんが創られたものは、どんな環境にも耐えるものとして、喜ばれています。浦先生の願いとしては、オーストラリアからは開校当初から毎年数校の姉妹校の生徒が合同で、校舎にも寝泊まりしながらボランティアをしに来るので、ぜひたくましい六甲生たちが東ティモールに来て、地元の村を訪問し、生徒たちと交流し、ボランティアもして、またメルシュ机が活躍している教室の授業風景も見に来てほしいと、お会いするたびに話されます。本当に、いつか実現できればよいと思います。
(5)新しい平和な国を築く人間育成のための学校づくり
-農村の子どもたちが学ぶための経済支援と学力支援-
これまで述べてきた通り、東ティモールは独立後も、学校で教えるのに相応しい教師が足りず、使用言語も定まらず学校設備も教育環境も整わない状況でした。そうした中で、これから新しい平和な国を築く人間を育てるために、どのようなイエズス会学校を作ってゆくか、アジアの各地域からイエズス会士が集まって話し合いながら、スタートしたのが聖イグナチオ学院でした。戦後復興期に、多国籍の司祭が集まって学校作りをした六甲学院にも似ているかもしれません。この学校の第一の創立理念は「貧富の隔たり無く、学びたいすべての子どもたちによい教育を提供できる学校」です。東ティモールでは、それまで自分たちの手で学校を運営する経験が、ほとんどありませんでしたので、学校というのはこんな風に教育を行う場所であるということを内外に模範として示すパイロット校になることが、まずはめざされました。
イグナチオ学院は、首都ディリから自動車で40分~50分の海辺の農村ウルスラ村に設立されたのですが、開校して3年後には、実際にそれまでにないしっかりとした教育をしていることが評判になり、都市部から能力面でも経済面でも恵まれたご家庭の子弟が集まるようになりました。学力も経済も不足しがちな地元のウルスラ村の家庭からは、定員75名中入学者が3名だけという事態になりました。つまり、都市部の社会的経済的エリートたちの子弟が集まり、再び社会的経済的に恵まれたエリートとして、都市部で暮らす人間を生み出すだけの学校になりかねない状況になりました。もちろんそうした社会的な影響力を将来持ち得る生徒たちに、良質な人間教育をすることにも充分意味があります。ただ、生活が貧しく困窮している農村部に学校を建てたのは、農村部の子どもたちに、しっかりとした教育を受ける機会を設けたい、そして、その中から最貧国東ティモールが貧しさから脱して平和な国を築くために貢献する人たちを育てたいという強い希望がまずあったからでした。そのままでは最も大切にしたい学校の目的が達せられませんので、地元の児童の中で学ぶ意欲のある子どもたちを集めて学校が補習塾を開き、ある程度学力を身につけさせた上で受け入れるという方法が取られました。
農村では家族が生活するだけで経済的に手一杯の貧困家庭がほとんどですので、社会的に弱い立場の貧しい子どもたちに、奨学金を与えて、都市部の恵まれた子どもたちと共に学ぶ学校になるようにしました。六甲学院からの寄付は、そうした社会的に弱い立場の、貧しい生活をしている家庭の子どもたちが、勉学を続けられるように、そのための費用として伯友会からの寄付と合わせて、毎年50万円が送金されています。
(6)経済的社会的エリートでなく社会に仕えるリーダー育成を
東ティモールの聖イグナチオ学院の創立期の例に限らず、イエズス会学校は世界的に、各地域の中で質の高い教育を提供するので、社会的にも経済的にも能力的にも恵まれた生徒が集まる傾向があります。ただ、社会に出てから自分たちだけが上位層を占めて、豊かで安定した生活を保障される、特権階級的な社会的経済的エリートを育てる学校ではありません。弱い立場の人たちを含めて皆が、人として大切にされ幸せな生活が送れるような社会にするために、貢献する人間を育てる学校です。その目標は、日本でももちろん同じです。しかし、六甲学院の歴史の中でも「エリートを育てる学校」という言葉が、やや誤解を生む可能性を秘めつつ、広まった時代はありました。
1965年28期入学時から約10年間、初代武宮校長を引き継いで2代目の校長となったドイツ人のシュワイツェル先生は、よく生徒たちに「エリートでありなさい」とおっしゃっていたそうです。同時に「よきリーダーになりなさい」とも話されていたようです。それを聞いて、日本社会のトップに座を占めて、人々を引っ張ってゆくエリート養成をめざしている学校と考え、誇りをもって勉学に励む生徒がいた半面、そうしたエリート指向に反発を感じた生徒や教職員もいたようです。
もちろん学問的な卓越性はイエズス会教育の中で伝統的に重要視されていて、それは今でもゆるぎない目標ではあるのですが、イエズス会教育の中で目指されているのは、人格面も知性面も含めて個人に与えられた優れた才能を最大限に伸ばし、人のためにその能力を活かすことのできる人です。そして、周りの人たちもその人の人柄や生き方に自然に影響されて、他者が幸福になるために何ができるかを共に考え、共に働きたくなるような人なのだろうと思います。
イエズス会学校は長い歴史の中では、先ほども述べたように、世界の数多くの地域で“世間的”には「社会的地位や経済的安定を将来にわたって約束されたエリート」を育てる学校として評価を得て、それがイエズス会教育の目的であるかのように思われていた時代もありました。そのため広島に原爆が投下されたときに救援活動のために奔走し、後にイエズス会総長になったアルペ神父は、50年前にその誤解の修正を促し、イエズス会学校が育成するのは「社会的経済的エリート」ではなく「社会に仕えるリーダー」であり、世界が必要としているのは愛と正義を実践する“Man For Others”であると訴えました。特に弱い立場の貧しい人々に深い関心をもって「他者のために、他者と共に生きる人」を育てることが目標となるようにと、世界中のイエズス会学校は学校改革を進めてきました。
(7)“For Others, With Others”-「弱者(Others)」に寄り添う真のエリート
シュワイツェル校長の「エリートでありなさい」という言葉を、誤解なく正しく理解する上で参考になる、当時の校長が伝えたかったことを代弁しているかのようなドラマを、たまたま見る機会がありました。1月から3月まで放映されていた「御上(ごじょう)先生」という松坂桃李主演のドラマで、これまでの学園ドラマとは幾らか視点の異なるドラマとして、見ていた生徒も多いのではないかと思います。
ストーリーは、文部科学省の若手官僚御上が、教師として、県で東京大学合格者数トップの進学校の教育現場に派遣されるその初日から始まります。着任してすぐに担任になった御上先生は、生徒たちに教壇から次のような話をします。
「君たちは、自分のことをエリートだと思っているか? 県でトップの学校にいて、自分がエリートだと思うのは当然だけれど、エリートの本当の意味を、理解しているだろうか? エリートはラテン語で神に選ばれた人という意味だ。なのでこの国の人は、高い学歴を持ち、それにふさわしい社会的地位や収入のある人間のことだと思っている。でもそんなのは、エリートなんかじゃない。ただの上級国民予備軍だ。」
初回のドラマの終わりにはその話の続きとして、次のようなセリフがあります。
「今どんな思いで受験勉強をしているか。過酷な、過酷すぎる競争を勝ち抜いてようやくつかみとった人生が“上級国民”でほんとうにいいのか? 言ったよね。エリートは神に選ばれた人だと。なぜ選ばれるか? それは普通の人ならば負けてしまうような欲やエゴに打ち勝てる人だから。自分の利益のためでなく他者や物事のために尽くせる人だからだ。ぼくは、そこに付け加えたい。『真のエリート』が寄り添うべき他者とは、つまり『弱者』のことだ。」
日本の教育がめざすべきリーダーの人間像が、この言葉の通りに「自分を律して自分の利益のためでなく他者に尽くせる人」になるならば、そのままイエズス会教育の目標とほとんど同じとも言えそうです。少なくとも、最後に「『真のエリート』が寄り添うべき他者とは、つまり『弱者』のことだ」が、付け加えられていることで、イエズス会教育で育てたい“For Others, With Others”の人間像と繋がり、共通の方向性を持った言葉になっているように思えます。恐らく2代目校長が生徒に伝えたかったメッセージも、ここで言う「真のエリートになりなさい」ということだったのだろうと思います。
(8)各個人が幸福になるために社会構造の変革をめざす教育
「御上先生」のドラマには「Personal is political(パーソナル・イズ・ポリティカル)」という言葉もよく出てきて、主要テーマの一つになっています。この言葉には、社会の構造的な問題-歪み―が、個人の境遇や幸・不幸とそのまま繋がっているという視点があります。だからこそ個人が本当に幸せになる社会を築くためには、目の前の困窮している人を助けるだけでなく、社会構造の変革をめざす人間を育てる必要があります。このヴィジョンは、イエズス会教育の中では「若者の教育は、世界の変革である」と述べた16世紀のイエズス会の教育者Juan de Bonifacio(ボニファシオ)から受け継がれて、現代のイエズス会教育にも共通しているものです。
社会のありようがそのまま個人の生き方や幸せ・不幸せと繋がっていることを、端的に示す最近のドラマをもう一つ紹介するならば、日本の第二次世界大戦中を描いた朝の連続ドラマの「あんぱん」が挙げられます。「アンパンマン」の作者「やなせたかし」をストーリーのモデルにしているドラマなのですが、4月の入学式でも述べた通り「何のために生きるのか」と「逆転しない正義」という主要テーマが、戦争を始めとした人々を巻き込み束縛(そくばく)する社会の出来事の中で、繰り返し現れています。
(9)若者の未来とめざしたい生き方を奪う戦争
ドラマでは第二次世界大戦中、たかしが軍隊に入隊して2年後、ひさしぶりに会った弟の千尋(ちひろ)は、海軍の士官になっていました。京都帝大、今の京都大学に入学して勉強に励んでいると思い込んでいた兄は、なぜ海軍の兵士になったのかと問います。弟の千尋は、海軍予備学生に志願することにした理由を兄に説明します。卒業が間近になり、日本を守るために自ら志願して兵隊になり戦争に行くことを決意する友人たちの前で、その思いをそぐわけにいかず、自分も志願したことを話します。「駆逐艦に乗り、敵の潜水艦のスクリューを探知して爆雷を投下する」のが弟の命がけの任務です。それを聞いて、もともと優しい心根の弟が、弱い立場の人たちに寄り添いその力になるために法律学を志したことを知っている兄のたかしは、次のように言います。「お前が耳を澄まして聞きたかったのは敵のスクリューの音じゃないだろう。弱い者の声を聞いて救うために法科に行ったんだろう。」「おじさんが、よく言っていたじゃないか。何のために生まれて何をして生きるのか?敵の潜水艦をやっつけるためじゃないだろう。」この兄の言葉を聞いて弟の千尋は次のように言います。「わしもよくおじさんの言っていた言葉を思い出す。何のために生まれて、何をして生きるのか。わからんまま終わるなんて、そんなのは厭じゃ。この戦争がなかったら、わしはもっと法学の道を究めて、腹をすかせた子どもらや、虐げられた女性らを救いたかった。この戦争がなかったら、一遍も優しい言葉をかけてあげられなかった母さんに親孝行したかった。この戦争がなかったら、兄貴と何べんも酒を飲んで語り合いたかった。この戦争さえなかったら、愛する国のために死ぬより、わしは愛する人のために生きたい。」そう切実に訴える弟に兄は「千尋、生きて帰ってこい。必ず、生きて帰れ。生きて帰ってきたら、こんどこそ、自分の人生を生きろ。」と語ります。他者の幸せにつながるような学問を追及したいと願って法科の学生になった千尋は「真のエリート・弱者のために尽くす人」になり得たはずです。その可能性が戦争のために閉ざされ、「自分の人生」を生きられないまま、弟の千尋は戦死したことを、あとのストーリーの中で知らされます。
少年の視点で戦争を描いた『少年H』には、空襲時の恐ろしさだけでなく、国が着々・黙々と準備する戦争に市民が知らぬ間に巻き込まれてゆく恐ろしさも併せて描かれています。作者妹尾河童は「戦争では一人一人の心など、全く無視され、個人の意志など、国家という強大な権力に押さえこまれ、口をふさがれてしまう」と述べているのですが、それはこの「やなせたかし」をモデルにしたドラマにも同様に当てはまります。)
(10)生命と未来を奪う戦争への警告と「何のために生き学ぶのか」の探究
おそらく、こうした場面を描く背景には、ただ80年前の戦争の実相を描く意図だけでなく、現代も戦争によって“祖国のため”の名のもとに、未来を生きることのできた若者の多くが命を落としているウクライナやロシア、ガザやイスラエルなどの現実への問いかけがあるように思います。また80年前と同じように政府が戦争への準備をしつつ、市民の私たちが知らぬ間に戦争へと向かい兼ねない日本への懸念や、未来のある若者をそうしたことに巻き込ませてはいけないという警告も含まれていると思います。※2
他国による過酷な支配と様々な戦乱や紛争を経験してきた東ティモールは、国自体が貧しく近隣諸国の中で弱い立場に置かれているのですが、そこで生きる人々がより幸せになることをめざす学校を作るために、六甲学院で教えていた浦神父が今も働いており、六甲学院で学んだことの延長として、この国の教育の課題を自分事のように研究している須藤先輩がおり、六甲学院の先輩たちが使い続けてきた机椅子が今も使われ、私たちの募金が貧しい家庭の子どもの奨学金として使われていることは、六甲学院にとっても、この学校の教育がめざしてきた方向性の目に見える証として、意味のあることなのではないかと思います。
そして、第二次世界大戦から80年が経ち、日本では戦争がそこに生きる人間に何をもたらすかが忘れ去られようとしている今だからこそ、新聞テレビの報道や戦争体験者の証言・書籍・ドラマ・アニメなどを含め、様々な機会を通して戦争の実相や政府の軍事化への動きや戦争によって個人個人が失うものの大きさを知ろうとする努力は、大切なことなのだと思います。
六甲教育、イエズス会教育は何をめざしており、そこに身を置く自分は何のために生き、何のために学ぶのかを、真剣に考え続けてくれたらよいと思います。
※「加害の歴史と向き合わずして『平和』を語れるのか」2024.8.10 “Dialogue for People” https//d4p world 参照
※「ルポ軍事優先社会-暮らしの中の『戦争準備』」(吉田敏浩著 岩波新書 2025.2 参照)