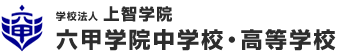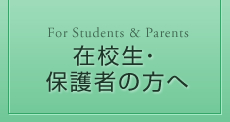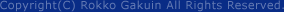《2学期 始業式 校長講話 2025年8月29日》
台湾訪問-自由と平和を隣国と共に守ること
1.夏休みの出来事を振り返る機会を作ること
40日ほどの夏休みが終わり、今日から2学期が始まります。この夏休みを、皆さんはどう過ごしたでしょうか。部活動を頑張った人もいれば勉強を中心に励んだ人もいるでしょうし、文化祭準備を熱心にした人もいるかと思います。最も長い休暇ですので、学校行事としても泊りがけのものが多くありました。海山のキャンプ、クラブ合宿、東京研修、ガーナ高校生との交流、能登の震災被災地へのボランティア、カンボジア研修旅行などに取り組む中で、皆にとって貴重な出会いがあり、充実した交流をし、成長の機会にもなったことと思います。自分にとって心を動かし印象に残る出来事として、どのようなことがあり、そこにどのような意味があっただろうか、と各々が振り返る機会を、ぜひ作ってもらえたらと思います。
2.夏休みに訪れた二か国の共通点
私自身は、この夏期休暇には、それぞれ短い日数ではありましたが、個人的な旅行として2か国を訪れました。一か国は台湾、もう一か国はエストニアです。この二か国は共通点があります。一つ目は小さな国で中国やロシアなどの大国の軍事的・経済的な脅威にさらされていること、二つ目は伝統を保ちながらデジタル技術面で先進的な国家となっていることです。
台湾については知っている生徒が殆どだと思います。中華人民共和国から台湾海峡を隔てて南東の島国であり、日本からは南西に位置していて、九州とほぼ同じ広さでありながら人口は約2340万人の国です。風光明媚な景勝地に富み、おおらかな国民性で豊かな食文化を持った親日の国でもあり、同時に半導体・電子機器などの最先端の技術で世界をリードしていることでも知られています。エストニアについては、なじみのない生徒も多いかもしれません。北欧のフィンランドからバルト海を隔てて南側にある国で、国境の東側はウクライナと同じくロシアと接しています。面積は日本の約9分の1、人口は約134万人で、世界最先端のデジタル国家として知られています。
台湾にもエストニアにも、大変美しい歴史的な街並みや伝統文化があって、それを大切にしつつ、現在の自由と平和を保つために、そして巨大な近隣の国に軍事的にも経済的にも飲み込まれないために、あらゆる分野で社会の変革や改革を推し進め産業を育て、新しい技術革新を取り入れた国造りをしています。小さいながらも世界に存在感を示し、周囲の国々と連帯して日々の生活を守りより豊かにしてゆこうとする、そうした創造的で前向きな真剣さが、様々な場面で感じられる二国です。日本にも、かつてあったそういう活力や先進性・創造性を大切にする気質を取り戻すために、こうした小さな国の営みから学ぶべきものがあるようにも思いながら、帰国しました。
3.台湾の姉妹校聖イグナチオ学院と教会活動施設の訪問
今日の始業式では、その2国のうちの主に台湾の訪問について話したいと思います。
台湾の首都台北(タイペイ)では、St.イグナチオ中学校・高校(天主教徐匯中学校・徐匯高校SISH)というイエズス会学校への訪問をしました。六甲と同じ男子校ですが、校長先生は陳海珊(Susan Chen)さんというお名前の快活な女性の方で、元気な中学生の授業を参観させて頂いた後に、学校の寮を見学しました。4人1部屋で、現在85人ほどが利用しているそうです。毎日が合宿のように、一緒に寝起きをし、食事をし、勉学も助け合いながらしています。部屋内も見せていただきましたが、所持品も極めて簡素です。スマホも使えるのですが、使える時間帯には約束事がありました。
私は寮というのは学校に通えない遠方の生徒が利用するものと思っていましたが、そうではなく、ごく近所のご家庭でも保護者の要望で子どもの自立と規律ある団体生活を学ばせるために寮生活をさせているとのことです。校長先生のお話によると(冗談半分だったのかもしれませんが)、むしろ親が反抗期の自分の子どもとぶつかり過ぎないよう、適度の距離を取るために寮に入れているのだろう、とのお話でした。その話を聴いてもしも六甲学院に寮を作ったら、同じ80人くらいの生徒はこうした毎日が合宿のような共同生活を望むのではないか、とも思いましたが、どうでしょうか?
六甲学院の多目的室1ほどの大きさの一部屋に、イエズス会の創立者イグナチオやアジアに宣教に来たザビエルや、学校の創立期からの歴史が、絵画・写真・年表・図表などを使いながら大変わかりやすく展示されており、感銘を受けました。校長先生とは、お互いの学校の特徴も紹介し合ったのですが、聖イグナチオ学院の校長先生の目が輝いたのは、今年の体育祭の総行進の動画映像を見ていただいた時でした。校長先生からは、時期にもよるが、30~40人ぐらいならば、寮にとめさせてあげられると思うから、六甲の生徒たちに来てもらって交流ができるとよいですね、という思いを伝えて下さいました。
その後に、イエズス会が司牧する教会を訪問しました。カトリック六甲教会よりも二回りくらいは大きいと思われる教会堂です。敷地内の別棟の社会活動センターでどんな活動をされているかを紹介していただきました。六甲学院が社会奉仕活動に参加しているカトリック社会活動神戸センターと、その役割は近いように思います。野宿者や先住民族やアジア各地から集まって来る労働者などが、様々な要因で生活が行き詰ってしまったときのケアや炊き出し活動をしています。日本と異なると思ったのは、教会施設には若い人たち(MAGISと呼ばれるグループ)が、いつでも集まれる広い多機能スペースがあって、社会活動はそうした若者と密接に連携しながら行われていることです。それは若い人たちが社会活動に、自ら積極的に関わっているということでもあります。そうしたお話を伺うと、こうした所に六甲の生徒たちも来て、海外の若い人たちと交流しつつボランティア体験をすることも可能なのではないか、と思ったりもしました。
4.本格的な昆虫博物館のある成功高校訪問
カトリックの学校や関連施設については、以上のような場所に行ったのですが、台北の伝統的な公立の進学校も訪問しました。もともとは日本が台湾を統治していた1895年から1945年の約50年間の中で、当時の政府が20世紀の初めごろにエリート校として設立した学校で、その名前も、「成功」が校名になっています。この成功高校のモットーは、「世界を視野に入れて、成功の道を歩むこと」(「全球視野、成功領航」)で、80%が理科系の生徒であり、生徒の内の16%は日本の東京大学にあたる国立の台湾大学に進学するという学校です。台北の中で公立校ではトップ、私立を含めると3本の指に入るとのことです。この学校のもう一つの特徴は、学校内に六甲で言えば合併教室くらいの広さ昆虫博物館があるということです。学校としても、進学成績だけでなく、むしろそれよりもこの昆虫博物館を誇りにしているように思えました。
私が訪問した時には、コレクションについてのプレゼンテーションや標本についての説明をこの学校の生物部の生徒や卒業生が英語でしてくれました。日本人もこの学校内の博物館を見学に来ることがよくあるのか、中国語と併記して日本語のカラーパンフレットまで作ってあって、英語の説明が十分には理解できなくても楽しむことができます。たとえば、私が実際に見て感動した蝶については、「大自然の奇跡-雌雄(しゆう)モザイク蝶」と日本語タイトルがあり、次のような説明があります。
「一匹のナガサキアゲハが雄と雌の特徴を同時に持っているなんて、想像できますか? この珍しい自然の奇跡は「雌雄モザイク」と呼ばれ、遺伝子の突然変異によって生まれる神秘的な存在です。片方の翅(はね)には雄蝶の鮮やかな色彩と模様が、もう片方には雌の美しい姿が広がり、まるで自然が描いた幻想的なアート作品のようです! このような標本は非常に珍しく、生物多様性の無限の可能性を証明するものです。」
大変珍しい蝶の標本の実物を見て、こうした解説を読むと、六甲の生物部の部員や生物の好きな生徒たちに見せてあげられたら、とも思いました。
5.台湾のシリコンバレー「新竹」のTSMCミュージアム等の見学
今回の旅行では九份という伝統的な古い街並みを散策したり、大きな風船に筆で願いを描いて蠟燭の火を灯し空に揚げたり、龍山寺という街中のお寺で市民が大勢朝から集まって真剣にお祈りをしているところを訪れたり、夜の市のさまざまな料理が並ぶ屋台で食事をしたりといった、いわゆる観光もしたのですが、印象に残ったのは台北からバスで1時間ほどの、新竹(シンチク)という台湾のシリコンバレーとも呼ばれる、IT関連企業の集まる地域を訪れたことでした。
TSMCという世界の半導体の60%のシェアーを占めていると言われる会社の、イノベーション・ミュージアムと、その企業とも連携している明新科学大学を見学しました。イノベーションとは、新しい発想や方法で技術・製品・ビジネスの仕組み・組織・制度などを変革し、新しい価値観を生み出し、社会に大きな変化をもたらすことを言います。特にTSMCのミュージアムは「イノベーション(革新)が私たちの生活を豊かにする」ことをテーマにした展示施設です。かつては日本が世界をけん引してきた集積回路(IC)技術を用いた製品から、コンピューターやスマホに用いられている現代の半導体への発達の歴史や、これから予測される技術革新と未来の生活の姿を体験できるゾーンがあります。また、TSMCが優れた半導体を開発し生産し続けるために、どのような方法で他社企業や研究機関と協力的なネットワークを作っていったか、一技術者であった創立者モリス・チャンが、どういう発想や思想のもとにTSMCを世界企業に導いたのか、台湾にとっていかにこうした技術革新・イノベーションの営みが大切か(※)等、理系・文系を超えて、これからの時代を生きる人々にとって学ぶ観点の多いミュージアムです。
ミュージアムの展示の最後にはこの創立者の次のような言葉も紹介されていました。「厳しい困難の中で希望が見えにくい状況にあっても、あきらめずに続けていけば、一筋の光が見えてきて、明るい未来に続くことがあります。」展示では創立者と企業の成功のストーリーの方に目が向きがちですが、こうした言葉を読むと、希望を見失いそうになる多くの困難を努力で乗り越えた上での「今」があるのだろうと思います。
日本語の音声ガイドもあり、科学技術やITに興味がある人だけでなく、新しい発想で物事を変革するというイノベーションと、それが社会にもたらす変化・意義・役割などについて知りたい人は、訪れるとよいと思います。
6.台湾留学の朝日新聞記事
以上のように、主に2校の学校見学や、社会活動の施設訪問、TSMCの施設見学などをして、帰って来たのですが、ちょうど今週の月曜日(8月25日)の朝日新聞の夕刊一面に、「安くて教育充実 台湾留学 人気」という見出しの記事が載っていました。昨年度の留学者は8700人を超えていて、年間学費が50万~75万円、台湾は以前から英語教育には力を入れており、留学先の大学での講義は主に英語で行われるとのことです。安い学費に比べて語学教育が充実しており、奨学金や生活費まで受けられるコースもあるとのことで、静岡県内の高校3年生の母親は「娘の留学希望に反対していたが、台湾の教育水準の高さや学費の安さ、治安の良さと、調べれば調べるほど『いいじゃない!』と背中を押したくなった」という声も、その記事には載せています。先ほど紹介した企業TSMCも、この日本からの台湾留学を全面的にサポートしていて、台湾留学人気には半導体関連企業への就職への期待や、奨学金を得ながら英語や中国語で学べることの魅力が背景にあることを、その記事では述べていました。
新聞記事としては、やや台湾留学への宣伝広告とも読まれかねない内容ではあるのですが、ここ20年ほどの高校生たちはどちらかというと、海外留学を敬遠し国内に引きこもりがちの傾向があり、国際的な視野が育ちにくいという指摘もされてきましたので、積極的に海外に目を向けるきっかけにはなるのではないかと思います。また、六甲生にとっても現実的に手の届きそうな海外への留学先の選択肢として、台湾は今後の進路を考えるにあたって、頭の片隅に置いておいてもよいのではないかとも思います。
7.自由と平和を隣国同士が共同で守ること
最後に、台湾の方々から「私たちは政府に不満があるとよく訴え、こうしてくれと要求するのですが、そうした声を挙げられること、反対を唱えられること、なんでも発言できる自由があることは、とても有難いことだと思っています」という話題を、旅行中時々聴くことがありました。確かに、街を歩いていても、そうした活気のある屈託のない自由さを、この国には感じます。おそらく、その言葉の裏には、そうした自由のない中国に突然飲み込まれ支配されたくはない、という強い願いがあるのだろうと思います。また、そうした今謳歌(おうか)している自由さが、おそらく企業だけでなく社会全体で柔軟な発想ができ、社会の改革-イノベーションーを進めてゆく環境にも繋がっているのではないかと思います。
台湾がそうした国であるからこそ、隣国として、また同じ中国という大国の隣にある国に住む人間として、平和的な国同士の関係を作ってゆくことに、私たちも何らかの貢献ができればよいと思います。同じ自由と平和を共同で守ってゆければとも思います。関空から飛行機で2時間半ほどの、比較的行きやすい国ではありますので、もしも興味の持てる何かが見出されれば、(大学生になってからにはなるかもしれませんが、)行ってみることを勧めたいと思います。
それでは、まじかにある課題考査を乗り越えて、その後に控える文化祭も、ぜひ楽しみながら、成功に向けて頑張って下さい。
※ こうしたイノベーションによる優れた技術革新と製品生産をし続けることが、一企業にとどまらず国家の安全保障にもつながるという見解があります。台湾であれば、30年以上にわたり磨き上げた高い生産技術によって、世界のあらゆる分野で必要とされる優れた半導体を作り、世界に供給することが、他国からの攻撃や侵略から自国を守ることに繋がるという「シリコンの盾」と呼ばれる考え方です。こうしたイノベーション・ミュージアムの展示意図の中にも、一国を超えて共同で発明・開発・発展に向かう仕事の魅力・やりがい・面白味を伝えつつ、世界の優秀な開発者・技術者等とのネットワークを広げ、協力して優れたものの開発・生産・供給をし続ける「拠点」となることを通して、他国からの侵略を防ぎ平和の均衡を保っていこうとする姿勢も見られるように思います。武力競争ではかなわない小国が、平和を保つために選択できる道の一つなのではないかとも思います。