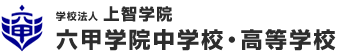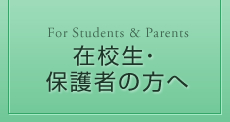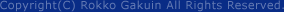校長先生のお話
《2022年7月20日 一学期終業式 校長講話》
自分が「めざす姿」を探すことと
イエズス会教育がめざす「決然と弱者を擁護する者」
1 行事の中で「なりたい自分」を探すこと
一学期を振り返って、六甲生全員が体験した中で最も大きかった出来事は、やはり体育祭だったと思います。競技の観戦をみなで楽しめていたことも、総行進の完成度も、総行進のあとの競技が最後まで引き締まって行われていたことも、様々な点でよくできた体育祭でした。練習の中でも、高3、高2の役員たちの真剣に取り組みながら、どこか共に作り上げてゆくことを楽しんでいた姿が、そのまま下級生たちにも伝わって、下級生にはただしんどくて苦しいだけになりがちな練習が、本番が近くなるにしたがって少しずつやりがいや意味のある練習と感じられるようになっていったプロセスがあったようにも思います。先輩からの「ナイス行進‼」という声かけも後輩たちには励みや喜びとなっていたようでした。
中学1年生の作文を読んでいると、中一指導員や部活動の先輩だけでなく、体育祭の役員の中にも、数年後は自分もこんな風に後輩に接することのできる人になりたい、というめざす姿となった人もいたようです。入学して最初の時期に、そうした自分がなりたい姿が見いだせるのは、六甲学院の六年間の生活の中でとても大切なことだと思います。また高校生にとっては、進路の日などに講話に来てくれる社会人や大学生の先輩や、社会奉仕活動やOBの仕事場で出会う人たちが、自分の将来めざす姿になればよいと願っています。
将来自分のなりたい姿、めざす姿、生き方のモデルを探すことをテーマの中心に据えて、話をしたいと思います。
2 「決然と弱者を擁護する者」という生き方のモデル
今年の2月にインド募金を始めとした社会奉仕活動が、上智学院から「教皇フランシスコ来学記念表彰」を受けたことは、すでに伝えました。この表彰は教皇フランシスコが2019年訪日時の上智大学への来校を記念し、学生・教職員に向けて講話したメッセージに適った活動をしている個人・団体に送られるものです。その教皇フランシスコのメッセージの中心は「決然と弱者を擁護する者」になってください、ということです。さらに「己の行動において、何が正義であり、人間性にかない、まっとうであり、責任あるものかに関心を持つ者」となるように、というメッセージを送られています。6月に宗教部講演会でお話を伺った、外国人労働者のために活動している鳥井一平さんは、そうした生き方のモデルになる人の一人だと思います。また、この「決然と弱者を擁護する者」を育てることは、そのまま“Man for Others, with Others.”にも通じる、基本的なイエズス会学校の教育方針であるといってよいものです。そして、六甲の卒業生にも、それぞれの期に「決然と弱者を擁護する者」として”For Others, With Others.”の生き方をしている人がいることが、六甲学院の教育の実りだと思います。
3 「決然と弱者を擁護する」六甲の卒業生
六甲学院のOB会である伯友会の総会・懇親会は、卒業して25年経った期が幹事をします。今年は54期が幹事の年なのですが、54期に在間という弁護士がいます。もとから弁護士などの法律専門家のいない司法過疎地である陸前高田に、東日本大震災が起こった1年後に移り住んで、被災者のために法律相談をしてきました。在間さんが移り住んでから1年後位に、大船渡と陸前高田に生徒と災害ボランティアに行ったときに、彼の法律事務所を訪れています。生徒と共に話を伺う場を持ったのですが、生徒時代はラグビー部に所属しクラブ活動に熱心で、それほど社会奉仕活動に特別な関心を持った記憶はないとのことでした。「父親が弁護士ではあったものの思春期の反発心もあってそれほど弁護士になりたい思いも湧かなかったのだけれど、父親が人から感謝されている様子を見て少しずつ弁護士をめざす気持ちになった」という話をしてくださっていました。その在間さんが7月2日に東京の伯友会で講演者として来られ、久しぶりにお会いしました。
在間さんは高校1年生の時に阪神淡路大震災を経験しています。今年の4月下旬のある新聞の夕刊に、彼のことが掲載されていました。被災地の陸前高田に移り住む決断をしたきっかけの一つは、東北の被災者が家屋から家財道具を運ぶ姿を見たとき、高校1年で被災した阪神淡路大震災で、近所の小学校に避難していた被災者の引っ越しを手伝ったときのことを思い出したことだ、と記事で語られていました。自分の震災体験と岩手の被災地の現実とが重なったことが赴任の決意につながったのだそうです。こうした中学高校時代の体験が、ふと現在の出来事と重なって思い出されて、人生の方向性を決めるきっかけになることはあるのだろうと思います。この夏休みを中心に六甲生が参加するキャンプや社会奉仕活動、フィールドワークや東京・大阪・神戸の研修旅行、海外姉妹校とのオンライン交流なども、そうした将来の自分の姿や生き方を考えるきっかけとなれば、と願っています。
4 法律とSDGs・卒業生が目を向ける生き方
在間さんは、現在でも東日本大震災の被災者の家族が災害関連死に認定されるために、弁護士として裁判にかかわっており、認定に当たっては阪神大震災の時の判例を援用することもあるそうです。そうした形で弁護士として災害の弱者である被災者を擁護する働きをし続けておられます。さらに、東京での伯友会の集まりでお話を直接お聞きした折りには、現在は被災地などで法律相談をする人が不足している司法過疎地に、継続的に弁護士を派遣する仕組みを作る活動に取り組んでいると話されていました。
法律とSDGsとは一見関係がなさそうに思われるかもしれませんが、SDGsの目標16の「平和と公正をすべての人に」の項目は、平和で公正な社会を実現するためにすべての人が法律によって守られ、法律を利用できる社会にしてゆくことが含まれています。在間さんが司法過疎地で自分のしてきたことを次世代へと受け継いで、弱い立場の人々を支援し続けるための組織づくりに取りかかっていることは、そのまま大事なSDGsの活動と言えます。こういう生き方をしている卒業生が各期にそれぞれいることが六甲学院としての誇りだと思いますし、六甲の卒業生の良いところは、そうした人たちを各期が支援しているということです。
六甲学院の卒業生は優れた能力を持った方々は多いので、社会的に成功している人、「社長」「CEO」といわれる人たちも多く輩出しています。(同窓会の幹事会などに行くと半分くらいはそういう方々です)。もちろんそういう人たちも人々から評価され一目置かれるのですが、卒業生が目を向けるのは、在間さんのような生き方、教皇フランシスコの言い方でいえば「決然と弱者を擁護する者」、イエズス会教育のモットーで置き換えれば「他者のために、他者とともに」生きている人の方だと思います。生活のすべてをかけてそういう生き方をすることまでは、中々できないとしても、そういう人たちに関心を持ち、支援する側の人になることも大切なことだと思います。
5 姉妹校交流―共通点と相違点から見直す視点
イエズス会学校が恵まれているのは日本でも世界でも同じ方向性を持つ姉妹校が数多くあることです。インド訪問、NY研修、カト研巡礼やアジアのイエズス会学校との研修企画だけでなく、昨年からコロナ禍をきっかけに始まっているオンラインでの交流など、国内・海外を問わずそうした学校の生徒たちとの交流は今後も大切にしたいと考えています。高2の研修旅行では上智福岡の生徒たちと、学年規模の交流を企画していたのですが、コロナ禍で2月から6月に延期したために日程的に実現できなくなってしまったことは残念なことでした。これまでの経験から姉妹校交流の機会を持つ中で、同じ教育方針を共有す
る姉妹校であるが故に相通じる何かがあると共に、それぞれに独自な特徴があって、その違いを元に自分の学校生活について見直す視点が得られるという点でも、有意義なことだと考えています。これからも機会は創っていければと思います。
6 姉妹校栄光学園の生き方の基準“Noblesse Oblige”
私自身はこの1学期中に栄光の卒業生と話す機会がありました。4年ほど前にアジアのイエズス会学校の生徒たちが集まって、“イグナチオ的なリーダーシップ”をテーマにした合同研修会「ISLF」を日本でしたときに、ヘルパーとして手伝ってくれた学生の一人です。現在は神戸
大学の大学院で学んでいて、研究しているのは都市社会学という分野です。
その栄光の卒業生が、どんなことを研究しているかというと、“都市計画によって新しい商業
施設や宿泊施設が建設されて便利になり地域が繁栄する一方で、そのために住んでいた地域か
ら立ち退いたり周辺の住民の生活が変化したりする。場合によっては昔ながらの商店街が廃(す
た)れて、地域コミュニティがなくなってゆく。繫栄する側でなく、生活の変化を余儀なくされ
る人たちの方、社会的弱者の側を研究したいんです”、とのことでした。直接きっかけになった
のは、高校生の頃、冬休みに栄光の社会奉仕活動で釜ヶ崎に来て、炊き出しや夜回りをしつつ、
ある方から聴いた話だったそうです。新今宮の駅の北側に大規模な一流ホテルが作られる。その
一流ホテルができることで立ち退く住民の人たちのこと、街の変化を心配する話を聴いたことが、今の研究の動機になっているとのことです。
どうしてそういう繁栄する側よりも社会的弱者の側に関心を持つようになったのかを聴いてみると、栄光時代に教えられたものごとの考え方や生き方の基準として、そのOBから発せられた言葉は“Men For Others, With Others”とともに“Noblesse Oblige(ノブレス・オブリージュ)”という言葉でした。この“Noblesse Oblige(ノブレス・オブリージュ)”は栄光の教育の特徴を示すキーワードで、「地位や権力や財産を持つ社会的に恵まれた者には社会的義務が伴う」という意味です。西洋の貴族の騎士道に通じる言葉らしく、社会のリーダーは社会のために尽くす(身を投げ出す)覚悟が求められるという含みを持つ言葉です。「他者のために、他者とともに」という言葉と合わせて、社会的に恵まれている人間として社会の中で弱い立場の者に対して、尽くす精神が必要だという風に教えられるようです。
7 他者を“理解する”ために低身に立つ(”understand”)
同じイエズス会の姉妹校として共通点がありつつ、ノブレス・オブリージュというイエズス会の伝統やキリスト教用語とはまた異なる系統の言葉を使って、わかりやすく生き方の指針を示しているところに、栄光学園の独特さがあるように思います。六甲の場合も「“真のエリート”になる教育」として特に30期代の卒業生はこのノブレス・オブリージュと近い精神は教え込まれていたようです。その後六甲の40期代頃から「Man for Others, with Others」が教育モットーの主流になってゆきます。六甲では、ノブレス・オブリージュと通じる「社会の中で恵まれている自分たちの他者への役割」を伝える場合でも、時には社会的特権・優位性を捨てて低身に立って奉仕しなければならない場合があることを、加えて強調してきたように思います。六甲伝統のトイレ掃除の意味合いも、そうしたつながりの中で説明されることがあります。社会的に底辺にいて困窮している立場の人たちのことを「理解」するためには、英語のunderstandという単語の成り立ちにも示されるように、自分自身が低身に立つ体験が必要だということです。
8 フランシスコ・ザビエル-六甲教育がめざす生き方のモデルとして
本日配布される『よき家庭』という冊子の2~3ページ目に書いたことでもあるのですが、六甲学院の創立の原点となる人物はフランシスコ・ザビエルです。彼はポルトガルのリスボンからインドのゴアに向かう、一年にわたる船旅をするにあたって、ポルトガル王からの特別室や特別な食事や身の回りの世話をするボーイをつけるという特権待遇の申し出を断って、一番底辺の人たちと一緒に寝泊まりして、自分も船酔いに苦しめられながらも病気に倒れた人たちを必死に看病したと言われています。貴族出身であり、高学歴であり、司祭でもあるという当時にしたら非常に恵まれた特権を一旦置いて、目の前の助けの必要な人と同じ地平に立って生活するところから、本当に助けたい人たちのニーズも分かり、役に立つ奉仕もできる。そうした在り方、生き方を躊躇なく選ぶことができるために心身を鍛えることに、六甲学院の教育の主眼が置かれてきているように思います。
9 六甲独自の教育モットー(教育の特徴を表すキーワード)は?
以上、様々な出会いの中で、将来めざす人物やめざす生き方のモデルを探すことをテーマの軸にして話をしてきました。
それでは、六甲学院のみんなへの問いなのですが、六甲の場合、“Man For Others, With Others” の言葉と合わせて六甲独自の教育の特徴を表すキーワード、栄光の“Noblesse Oblige(ノブレス・オブリージュ)”に替わる教育モットーを端的な言葉で表現するとしたら、それは何でしょうか? 私も六甲として大切にしている独自の教育を一言で表すような言葉は何なのか、答えを探している問いです。みんなも、夏休みの様々な活動をしつつ、考えてくれれば良いと思います。
《2022年4月7日 一学期始業式 校長式辞》
◇『新しい人』になることをめざす
新学期が始まりました。
ノーベル文学賞を受賞した作家大江健三郎が次のようなことを言っています。「『新しい人』になることをめざしてもらいたい。自分のなかに『新しい人』のイメージを作って、実際にその方へ近づこうとねがう。…そうしてみるのと、そんなことはしないというのとでは、私たちの生き方はまるっきりちがってきます。」
新学期にあたって、大江健三郎の勧めに従って、まず自分の中に『新しい人』のイメージを思い描いてくれたらよいと思います。『新しい人』になることをめざしてください。今この時代に求められている『新しい人』とはどのような人でしょうか? または、今の自分にとって、なりたいと思う自分はどのような人でしょうか? まずは、何にもとらわれずに『新しい人』の自分なりのイメージを思い浮かべてくれたらよいと思います。
私がこの言葉に目が留まったのは、19世紀・20世紀の価値観をそのまま受け継いでしまっているような『古い人たち』が、世界のリーダー、社会のリーダーで居続けたら、世界は変わらない、それどころか破壊的な結果に導かれかねないのではないかという危機感を抱いているからです。これまでとは違う『新しい人』が、これからの時代には必要なのではないかと、痛切に思います。
◇世代を超えて世界に和解をもたらす『新しい人たち』
大江健三郎が「新しい人」という言葉に出会ったのは、「新約聖書」のパウロの書簡「エフェソの信徒への手紙」だそうです。大江健三郎はキリスト教の信徒ではないのですが、聖書を愛読している作家です。彼は次のように述べています。「『新しい人』という言葉は、次のような意味で使われていました。『キリストは平和をあらわす。それは、対立してきた二つのものを、十字架にかけられた御自身の肉体を通じて、ひとつの『新しい人』に作りあげられたからだ。そしてキリストは敵意を滅ぼし、和解を達成された……。 私は、なにより難しい対立のなかにある二つの間に、本当の和解をもたらす人として、『新しい人』を思い描いているのです。それも、いま私らの生きている世界に和解を作り出す『新しい人(たち)』となることをめざして生き続けて行く人、さらに自分の子供やその次の世代にまで、『新しい人(たち)』のイメージを手渡し続けて、その実現の望みを失わない人のことを、私は思い描いています。」(『「新しい人」の方へ』)
対立している二つのものが和解して、平和をもたらすための要(かなめ)になる人物が「新しい人」です。それも何世代にもわたって、その実現の望みを失わずに受け継いでゆける人たちです。
◇アジアのイエズス会学校の生徒たちのISLF体験
2018年の夏期休暇にISLF(Ignatian Student Leadership Forum)と呼ぶ、アジアのイエズス会学校の高校生が日本に集まる企画がありました。生徒がイグナチオ的リーダーシップを身につけるために80人ほど集い、プレゼンテーション・フィールドワーク・ワークショップ・分かち合い等をします。フィリピン、インドネシア、台湾、香港、マカオ、東ティモール、ミクロネシアの国、地域からイエズス会学校の生徒たちが集まりました。日本の神奈川県の秦野が会場でしたので、日本の姉妹校4校からも5人くらいずつ集まりました。“Beyond the Border”「境界を超える」ことを統一テーマに、戦争と紛争・被災地と環境・移民(在日外国人)という3つの課題に分かれて話し合いの場を持ちました。各国の社会問題も発表してもらい、貧困や環境破壊など各国に共通する課題を共有しました。そして、フィールドワークとして、戦争テーマのグループは第二次世界大戦当時の展示や戦没者を慰霊する場所を見学しに行きました。被災地と環境のグループは同世代の東日本大震災体験を聞きつつ原発事故のあった福島から首都圏に避難し、幼い子を育てている家族の話を聞きに行きました。移民(在日外国人)のグループはベトナムやカンボジアをルーツに持つ人々が多く住む神奈川県大和市のいちょう団地に行ったり、地元秦野のフィリピンをルーツに持つ若い人たちの話を聞いたりしました。
◇参加者の和解プロセスの助けになった日本の難民次世代の協力関係
プログラムを進めてゆく中で気づいたのは、「戦争」をテーマにして話し合うにしても、日本にとって80年前の出来事でも、例えば東ティモールの独立は2002年で、独立するまでの内戦や実質的に統治していた隣国インドネシアからの攻撃・破壊行為は、自分たちが生まれる少し前の、まだ生々しい出来事だということです。2月に一時帰国された浦神父様からのお話にもあったように、当時東ティモールの人口100万人ほどのうち独立の過程で20万人が亡くなったり行方不明になったりしました。つまり5人に1人ですので、家族や親せき、知り合いの誰かは命を落としている戦争状態であったと言っていいと思います。東ティモールの生徒たちは紛争とその後の混乱の中で、自分の兄姉や親戚が命を落としたり悲惨な目にあったりしていることを聞いて育っています。心情的に統治国であったインドネシア人の生徒たちと一緒に話し合うには、互いにその場で心のわだかまりを解き和解する過程が必要でした。東ティモールとインドネシアの生徒たちの心の葛藤に寄り添おうとする他国の姉妹校の生徒たちの姿もあって、そうしたことがこの集いの意義を深め、参加者たちの貴重な体験にもなりました。
今回心のわだかまりを解くための助けになったのは、フィールドワークでした。例えば訪問先の大和市の団地でカンボジアとベトナムにそれぞれルーツのある若者たちが、自分の親の世代では国としては過去に敵対関係にあったとしても、日本では難民の次世代として協力し合って、子どもたちのための学習支援のNGOを立ち上げていることを聞きます。そして国際的な集いのテーマBeyond the Border の通り、心に壁を作ってしまっているその境界線を越えて、将来に向けて若い世代が和解し協力することの大切さにも気づき始めます。
対立している二つのものが和解して平和をもたらすための「新しい人」になるということは、日本にいると実感を伴う言葉になりにくいのですが、こうして姉妹校交流を通じて世界とのつながりを持つことで、世界にとっていま必要な「新しい人」のイメージがより明確になるということは、あるのではないかと思います。そして、実は日本にとって80年近く前に終わった戦争であっても、アジアには世代を超えて、わだかまりがとけずに和解の必要な国々や人々がいることも忘れてはいけないことです。
◇東ティモール平和構築の体験学習に参加する学生グループ
東ティモールでは20年前まで、独立を推進する人たちとインドネシアの統治を維持しようとする人たちとの対立があって、独立した後もどのように対立していた勢力と和解し、国を共に作っていくかが課題になっています。2017年に4校の先生方と東ティモールを訪問した時には、その平和構築のプロセスを学ぶために東ティモールに来ている日本の学生グループと出会いました。その中には上智大学・早稲田大学・法政大学の混成チームがあって、そのグループのネットワークの中には71期と73期の六甲卒業生もいました。一人は六甲在学中インド訪問の経験者で、アジアの中でより教育環境の整っていない東ティモールを研究対象として選び、卒論のフィールドワークのために、たまたまその時にその場にもいました。その後、上智の大学院修士から東京大学の博士課程に進んで、研究を続けつつユネスコの活動に携わり始めています。もう一人は2014年に東ティモール大使館から招待されてイエズス会姉妹校のチームとして東ティモール訪問を経験した卒業生でした。彼はその後、ニューヨークでの模擬国連の高校生リーダーとしても活躍し、阪大の医学部に進学しました。71期の卒業生は教育の分野で、73期の卒業生は医療の分野で、世界に貢献する道を歩み始めています。
ロシアとウクライナもまだまだ先の見えない状況で、国同士はますます関係が悪くなる過程が予想されますが、民衆のレベルで両国の平和に向けて協力してゆくプロセスは、今後可能だと思いますし必要なのではないでしょうか。
世界の様々な戦争や紛争後の平和構築、和解のプロセスを進めてゆく人は、これからの『新しい人』として目指すべき姿の一つになるでしょう。皆の中からも、そうした道を目指す人たちが生まれてくるのを期待しています。
《2022年4月7日 中学校入学式 校長式辞》
◇コロナ禍での六甲学院中学ご入学にあたって
六甲学院中学校へのご入学、おめでとうございます。
保護者の皆様、ご子息の六甲学院への入学、おめでとうございます。桜の花の最も美しいこの日に、六甲学院85期生の入学式が迎えられたことを嬉しく思います。
2年間のコロナ感染拡大の中での小学校生活は、様々な面で思いの通りにはいかなかったことと思います。普通の生活とは違う環境を過ごしながらの受験勉強にも、困難を感じることがあったことでしょう。これからの六甲学院の生活の中で、そうした大変な経験を含めて、成長のための糧となればと願っています。
◇ミッションスクールとしての世界観と基本的使命
六甲学院はキリスト教のミッションスクールです。その基本的な世界観の中心は、「神はこの世界を善いものとして造られた。私たちも含めてすべてのものが、神から愛されて、大切なかけがえのない存在としてこの世界にある」ということです。そして、もう一つそれに加えるならば、「私たち一人ひとりには、この世界を本来の善いものとして、すべての命が生き生きと生きるために、何かするべき使命、ミッションが与えられている」ということです。六甲学院の土台にはこうした世界観があります。そしてこの世界観を学校生活での様々な経験を通して伝えることが、キリスト教の学校としての基本的な使命です。
皆さんは85期生で、この学校が造られて85年目を迎えるのですが、ミッションスクールという呼び方の通り、学校にもミッション=使命が与えられています。講堂の舞台正面の壁上部に刻まれた文字は、六甲学院の設立母体である修道会イエズス会の創立期からのモットー『Ad Majorem Dei Gloriam(アド マイヨーレム デイ グローリアム)』というラテン語です。創立者イグナチオの座右の銘で「神のより大いなる栄光のために」という意味です。日常的に神を意識することのない大多数の日本人にとって、「神の栄光」という言葉を聞いてもあまりピンとこないと思うのですが、すべての被造物、生きとし生けるものが、本来の命の輝きを放って生き生きと生きていることが、この世界を創造された神の栄光です。みんなが学校に来て、友だちと楽しそうに遊んでいたり、授業を目を輝かせて聞いたり発表していたり、クラブ活動で一生懸命練習に励んでいたりすれば、それもまた皆を造った神の栄光でもあるということです。神がこの世界を見るまなざしは、両親が、幼い我が子が元気に楽しそうにしている姿を見て喜んでいるまなざしと、似ていると思います。この「神の栄光」のため、生徒が本来の命の輝きを放って生きられるように尽くすことが、私たちの学校の使命と言えるでしょう。
◇「和解」の使命―イエズス会学校として
先に述べたように、キリスト教の世界観では、この世界はすべてよしとされた存在であることを信じています。基本的には楽観的な宗教といえるのではないかと思います。しかし、同時にその世界は必ずしも善いものとして存在していないことも分かっています。人間も本来の善さを見失って悪い方向へ向かう傾きがあることも分かっています。人間は、神がこの世界を造られた意図に反して、互いに自分や自国の富や支配への欲望のために争って戦争を起こしますし、自分たちの都合のいいように自然を利用して環境破壊をしています。今の世界を見ても、大国ロシアのウクライナへの侵攻によって、子どもを含めて罪のない多くの市民の尊い命が失われている現実がありますし、世界各地で豪雨や洪水を引き起こす気候変動にしても、プラスティック廃棄物による海洋汚染にしても、人間によって植物も動物も命あるものの生命が脅かされて、地球から悲鳴が聞こえてくるような状況になってしまっています。
人間は、この世界を創造され、生きとし生けるものが豊かに生き生きとその生命を十全に生きるようにと願われたその神の思いに反し、人間同士は争いあう中でかけがえのない命を落とし、地球の自然環境への配慮も足りずに環境破壊をしてきました。六甲学院の設立母体イエズス会は現在、神の思いに反してきたことに対して「神との和解」、人間が対立し争い続けていることに対して「人間同士の和解」、自然環境を顧みずに破壊し続けてきたことに対して「自然との和解」という3つの和解を進めなければならないというメッセージを発しています。この世界の創造物、生きとし生けるものが神の思いの通りに豊かにその命を生きられるように、人間同士が争って意味なく命が失われることがないように、地球全体が環境破壊によって傷つき滅びることなく後世もすべての生き物がその命を謳歌できるように、人間が力を合わせてこの世界をより善い方向に変えていかなければならないのだと思います。
◇創立者イグナチオの3つの共通メッセージ
六甲学院は、先ほどから述べている通り、キリスト教・カトリックの中でイエズス会という名の修道会によって設立された学校です。創立者はイグナチオ・デ・ロヨラという人です。彼は、神が何のためにこの世界を作られたか、そしてなぜ私たち一人ひとりを作られたか、を問い続けた人です。同時に、一人ひとりがこの世界にいる意味や目的を実感を持って見出せるように、そのための祈りの方法(「霊操」)に気づいて、多くの人たちに広めた人でもあります。昨年5月から今年の7月までを、イグナチオの回心から500年を記念して、全世界の900校近いイエズス会学校では「イグナチオ年」として、さまざまな企画をしています。
なぜ個人的な心の中で起こった「回心」という出来事を記念しているかというと、イグナチオはその「回心」の祈り中で人間すべてに共通する三つの大切なことに気づいたからです。そのうちの二つはキリスト教の世界観として紹介したことでもあるのですが、一つ目は「私たち一人ひとりが、神から大切に愛されて命を与えられていること」、二つ目は、「その与えられた命は、この世界の中で何かすべき使命が一人ひとりに託されていること」、です。そして三つ目は、「その使命を果たすために一人ずつ異なる才能・恵み(賜物)が与えられていて、その才能を磨いて他者のため、世界のために生かすことのうちに、生きる意味や喜びや充実感が得られること」、です。単に自己目的の自己実現でなく、他者やこの世界のために自分の善さや才能を生かして生きる時に、生きる意味や喜びが実感できるように人間は造られていると、イグナチオの精神を受け継ぐイエズス会学校は考えています。
◇3つのメッセージを6年間の学校生活の中で経験すること
新入生には、このイグナチオの三つの気づきを日常の中で味わう経験を、これからの6年間の中でしてほしいと願っています。まず、学校の中で大切にされる体験をしてくれたらと思います。先生方や中一指導員を始めとした先輩たちとの関わりや、自分の善さを引き出してくれるようなよい友人との関係を大事にして下さい。そのためのプログラムは、すでに中1オリエンテーションの友だちづくりから始まっています。
また、授業での学習や社会奉仕活動などの経験を通して、この世界で起こっている様々な出来事や、そうしたことを引き起こすこの世界の仕組みや、人間の尊厳や弱い側面を含めたその性質について深く理解をしてほしいと思います。多様な課題のあるこの世界のため、苦しむ人々のために、自分に何ができるかを問い続け考え続けて下さい。
そして、授業や部活動や委員会活動、日常の友人とのつきあいやクラスメイトや先輩たちと行事をしてゆくなかで、自分の善さや才能を見つけ出してくれたらと願っています。その自分の善さや才能を、授業の発表活動や行事や人との付き合いの中で生かす喜びを、在校中に味わってくれたらよいと思います。
まずは、オリエンテーションの2日目に訓育の中村先生が話されていたように、学校生活の中で、やりがいの持てる場を見つけてください。学校生活の中で、自分が生き生きとできる場が見つけられて、それが、将来したいことや、何か人の役に立つこと、社会をより善く変えられることへと、つながってゆけば、自分が生きている意味や使命に気づくことにもなるでしょう。
先ほど「世界のイエズス会学校では『イグナチオ年』としてさまざまな企画をしている」と述べましたが、六甲学院ではオリジナルの手帳を作成しました。自分の学校生活が充実し、自分の善さや才能を見つけ出して、よりよい人間として成長してゆくために、手帳もぜひ十分に活用してくれれば、と思います。
◇まとめとして…「宝は人に分かち与えるほどに輝きが増す」
話のまとめになりますが、六甲学院への入学にあたって、出会い始めた友人、先輩、先生とのかかわり、自分を大切に思ってくれる人たちとのつながりを大事にしてください。また、様々な学びの中でこの世界や人々のために自分に何ができるか、自分にどういう使命が与えられているかをこれからの6年をかけて探してくれたらと思います。そして、自分に与えられている才能や善さに気づいて、それを人々を幸せにするために生かせるよう、磨いてくれたらと願っています。
昨日のNHK朝の連続テレビ小説「カムカム エブリ バディ」で、侍(さむらい)役俳優の登場人物虚無蔵が主人公ひなたに次のような話をしていました。「そなたが鍛錬し培い身につけたものは、そなたの一生の宝となるだろう。されど、その宝は人に分かち与えるほどに輝きが増すものと心得よ。」 自分に与えられ努力して磨きをかけた才能や技能は、人と分かち合うほどに輝きが増す、というのは宗教を超えた真理なのだと思います。私が今日新入生に伝えたかったメッセージと、そのまま繋がる言葉だと思います。
それでは、一日一日、一つひとつのことを、大切に取り組んでください。
皆にとって六甲生活の良いスタートが切れますようにと、祈ります。
《2022年3月19日 3学期終業式 校長講話》
1 ロシアのウクライナ侵攻と難民への校内募金活動
21世紀になってから、それもヨーロッパで、このような侵略戦争が起こるとは思いませんでした。独立した主権国家であり、日常を平和に送っていたウクライナに、大国ロシアの戦車が国境を超えて攻撃したりミサイルで攻撃したり、3週間たった今は軍事施設だけでなく劇場に避難したり列車で移動したりしている普通の民間人に向けて攻撃が行われています。隣国へ避難している人々が300万人を超えていると言われています。
何かをしなければと思っている最中に、社会奉仕委員が主体的に動き出して募金活動をしてくれました。考査返却期間の3日間、登校時の限られた時間に東西両広場への階段前で呼びかけて、78,107円の募金が集まりました。ウクライナからの難民のための活動に生かしたいと思います。
昨年4月に大洪水の災害のあった東ティモールへの募金の時にも感じたことですが、世界の動きに応じてこうした活動がすぐに始まるのは、イエズス会教育を基本にしている六甲学院の生徒たちの特徴であり良さだと思っています。
イエズス会教育の特徴は、こうした募金活動にも表れているのですが、グローバルな視点と未来志向であることです。どんな厳しい状況になっても、自分のこと、自分の国のことだけを考えず、世界のことを考え、希望を失わずにより良い未来にするためにはどうしたらいいかを思案し行動する精神が、基本にあります。
2 地球儀を見るように世界を見渡す「グローバルな視点」
初期の創立者の一人にヨーロッパから日本にまで来たザビエルがいたように、イエズス会はその初めから「グローバルな視点」を持っていました。必要であればどんな場所でも行く心の自由さがあるだけではなく、地球儀を見るように世界全体を見渡して、特に痛んだところ、傷ついたところに目を向ける視点を持っています。イエズス会学校が大抵、坂の上にあるのはこの全体を見渡す―「眺望する視点」を持つ―ためだと言われることもあります。イエズス会教育の基礎にある創立者イグナチオの精神を体得する祈り方<霊操>の中には、世界を見渡してそこに暮らす人たちをできるだけ具体的に思い浮かべる訓練があります。
イエズス会学校が実際にグローバルな広がりを持っていること、全世界にあることを、ぜひ在校中に様々な機会を捉えて実感してほしいとも願っています。この春休みはチリとグァテマラの姉妹校の生徒たちと六甲の14名の中2・高1の生徒が交流することになっているのですが、そうしたことができるのも全世界に姉妹校があるからです。こうしたプログラムにはぜひ積極的に参加してください。実際にグローバルな視点を持つための助けになると思います。
3 振り返りから社会の変革をめざす「未来志向」
もう一つの特徴である未来志向についてなのですが、イエズス会教育はその初期から「若者の教育は、世界の変革である」という言葉がモットーの一つになっています。イエズス会学校創成期の16世紀後半に活躍した司祭ボニファシオ(Juan de Bonifacio1538-1606)の言葉です。将来の世界をより良いものに変えてゆくために教育に取り組んでいるという意識が、イエズス会教育の初めからありました。
実際に社会を変革するためには、根拠のない夢や妄想を抱くのではなく、しっかりと現実を踏まえたうえで、常により良い未来を考える必要があります。そのために、他者のために何をしてきたか、過去を振り返り、今何をしているか、現在を確かめ、これからこの社会をよりよくしてゆくために何をしてゆくか、自分に何ができるか、将来を考えます。これもイグナチオの精神を体得する祈り<霊操>に、日々の生活の中で過去、現在、未来を、つねに振り返りつつ次の行動を選択する習慣を染み込ませるための訓練があります。「瞑目」の原点にある祈りです。
今回のロシアのウクライナ侵攻にあたって、社会奉仕委員が自主的に募金活動をする動きも、グローバルな視点で世界の特に傷んでいる地域を見て、今の私たちに何ができるかを問う中で、現実的にできることを考えて選択し実現した行動です。
4 教皇フランシスコ来校記念表彰と教皇のメッセージ
今年度、六甲学院のインド募金・インド訪問を始めとした社会奉仕活動が、上智学院の教皇フランシスコ来校記念表彰に選ばれました。教皇とは、世界のカトリック教会のリーダーです。この受賞の意味については、今日配布する学院通信に書きましたので読んでもらえればよいと思います。現在の教皇フランシスコは、貧しく社会から排除されている人々や環境破壊に傷ついている地球を救うことを、メッセージの中心に据えています。教皇はイエズス会出身ですので、彼自身が常にグローバルな視点に立って未来志向の行動をしていることも特徴的です。
賞状には「貴殿は教皇フランシスコが2019年11月26日来日時にくださったメッセージに呼応する活動に、多大なる熱意をもって取り組んでこられました」とあります。教皇フランシスコが上智大学で、その来日時に話した講演メッセージの一部を紹介します。
教皇は講話の中で「貧しい人たちを忘れてはいけません」(ガラテア2・10)という聖書の言葉を引きながら、私たちが「現代社会において貧しい人や隅に追いやられた人とともに歩む」ようにと呼びかけています。そして学校が「単に知的教育の場であるだけでなく、よりよい社会と希望にあふれた未来を形成していくための場となるべきです」と話されます。ただ知識を身につけるだけでなく真の叡智(ソフィア=上智)を身につけ、「己の行動において、何が正義であり、人間性にかない、まっとうであり、責任あるものかに関心を持つ者」「決然と弱者を擁護する者」となるようにと励まされています。教皇はイエズス会の司祭出身ですので、こうした言葉の中にもグローバルな視点と未来志向がみられます。
この「何が正義であり人間性にかない弱者を擁護する行動になるのか」を見極めることを、「識別」といいます。そして教皇は「教員と学生が等しく思索と識別の力を深めていく環境を作り出すよう、推進していかなければなりません」とも述べています。どういう方向へと世界を変革してゆくかを識別する力を、生徒も教師も身につけ深めてゆくことが求められています。
今回の受賞は、こうした方向性をさらに今後も推し進めるようにと、励ますために与えられた賞であるということができます。
5 未来に向けての行動として-平和に導く政治家を選ぶための見識を持つ
もう一つ、皆の将来に向けて大切な願いを伝えたいと思います。私たち国民を戦争に巻き込むような考え方を持っている政治家を、選挙で選ばないということです。今回のことで一人の、あるいは少数の政治家の決断がどれだけの自国と他国の人々の生活を変え、不幸にしてゆくかはわかると思います。日本は選挙で政治家を選ぶことができる国です。選挙というとみんなには縁遠いように思われるかもしれませんが、昨年10月の総選挙の日までに誕生日を迎えた高校3年生は、すでに選挙に行っています。皆も高校3年生になり誕生日を迎えれば選挙で一票を投じる権利を持ちます。中学高校時代は、大人として社会に参加することにそのままつながる準備の期間です。今から卒業までの間で、学校の授業や新聞・テレビなどのメディアや読書やインターネットなどを通して、しっかりとした見識と価値基準とを身につける必要があります。この人が政治家となれば日本や世界は平和の方向に向かうのか、それとも平和を脅かす危険な方向に向かうのか、見分ける力をつけてほしいと思います。それも識別であり未来に向けての行動の一つです。
《2022年3月19日 中学校卒業式 校長式辞》
82 期生の六甲中学ご卒業おめでとうございます。
コロナ感染パンデミックとロシアのウクライナ侵攻が続くこの時代に、皆が中学を卒業するにあたって、どのような人々と出会い、どういう人たちの生き方や心の在り方をめざしてほしいか、について話したいと思います。
1 ロシアの国営放送で「戦争反対」を訴えた勇気ある女性スタッフ
ロシアのウクライナ侵攻から3週間が過ぎ、ロシア軍の攻撃が劇場や列車など子どもを含む民間人にも向けられる中、この戦争を止めるためのメッセージを込めた行動がロシア国内でもあることを示す象徴的な出来事がありました。ロシアで多くの市民が視聴する9時の国営テレビの生放送中に、テレビ局女性スタッフの一人が「戦争反対、プロパガンダを信じないで。ここではあなたにウソをついている」という手書きポスターを掲げた行為が、映像とともに報道されました。「砲撃はウクライナのしわざだ」「ロシア軍はウクライナ政府に苦しめられている市民を解放するために戦っている」といったロシア政府から国営放送を通じてロシア市民に流されるプロパガンダを信じずに、ロシア軍が他国に軍隊を送って攻撃している今の戦争を一刻も早く止めるように、ロシア国民も目覚めて、協力してほしいという訴えです。ロシア内の厳しい言論統制の中、また戦争に反対する市民への弾圧も続く中で、こうした行動を取ることは大変勇気のいることです。本人も「これから自分がどういう処罰を受けるかは、こわい」という心情を話していました。命の危険まで覚悟したうえでの行動だったのだろうと思います。
2 遠藤周作「ヴェロニカ」の物語
カトリックの小説家である遠藤周作の短編に「ヴェロニカ」という小説があります。
教会の暦の上ではこの3月から4月中旬にかけて、イエスの受難と復活を記念する聖週間に向けての40日間の心の準備の期間です。「四旬節」と呼んでいて、世界の苦しむ人々とも心を合わせる時期でもあるのですが、小説「ヴェロニカ」は、この四旬節の時期に私が毎年読むことにしている文章の一つです。国語の教科書にも載ったことのある文章です。その小説の中では、第二次世界大戦中の南フランスでの話が紹介されています。フランスのある山村に住む内儀(かみ)さんが自分の家の納屋で、占領軍として来た敵国ドイツ兵の若者が、怪我をして血を流しながら隠れているのを発見しました。このドイツ人の若い兵士を助けたらドイツ兵に協力した者として処罰されるかもしれない。しかし、どうしても怪我に苦しむ若者を見捨てることができなくて、この女性は敵国の兵士を介抱します。ドイツ兵の苦しみに同情し共感する思いを、作者は「激しい憐憫の情」と表現しています。この傷ついた敵兵は結局見つかって村の青年たちに殺され、それだけでなく青年たちはこの女性もフランスを裏切った者として、ののしりながら殺し古井戸の中に投げ込んでしまいます。のちに村の人々は自分たちの過ちに気づいて悔い、この女性の行為を称え、「あなたはわれわれよりほんとうのフランス人だった。人間だった……。」と文字を刻んだ像を、村の入り口に立てているということです。
3 小説「ヴェロニカ」のメッセージ
小説の中では、人間が集団になると残酷で凶暴な行動に向かってしまう群集心理のこわさと人間の弱さを描きながら、そうした中でも人間としての良心と憐憫の情を失わない人がいることを語ります。同時に小説では、この話と関連させて、凶暴な興奮に駆り立てられた群集が、残酷なむち打ちに傷つき十字架を肩に背負って歩くイエスに罵声を浴びせる中で、あえぎ倒れるイエスに駆け寄って汗と血にまみれた彼の顔を布でぬぐった女性がいたことを、伝承として語っています。その女性の名前が小説の題名である「ヴェロニカ」です。作者は次のように述べます。
「ヴェロニカの小さな存在は、社会や群集がどんなに堕落しても、人間の中にはなお信頼できる優しい人のいることを僕たちに教えてくれるようです。」
4 希望をもたらす人―「憐憫の情」を抱き良心の声に従う生き方
偽りであることを承知で自国の侵略行為を正当化する内容を報道するロシア国営放送の最中に、命をかけて反戦を訴える勇気や、何よりも戦争で苦しむ人たちのことを思いやり自分の良心の声に従おうとする女性の思いは、ドイツ兵を同じ人間として助けたフランスの内儀さんやイエスを助けたヴェロニカとつながるものではないかと思います。国家や民族を超えて傷つき苦しむ人々に憐憫の情を抱き、人間の尊厳や命の尊さを何よりも大切にする人間への愛がその根底にはあるのでしょう。
3月5日の高校3年生の卒業式では、卒業した79期生は『カラマーゾフの兄弟』という小説を読んでいましたので、どんな状況になっても人間としての良心と善良さを失わない「アリョーシャ」という登場人物を例に挙げたのですが、こういう人がいるからまだ人間には望みをかけられると思える人物は、小説の中だけでなく私たちが見聞きし出会う人たちの中にもいるはずです。ロシアの国営放送のスタッフもその一人です。コロナウイルスパンデミックが収まりきらない中でヨーロッパに戦争が起きて、先の見通せない暗い思いが世界を覆いそうなこの時代だからこそ、希望を見出す目を持ってほしいと思います。できれば身近なつながりの中でも、希望となる人たちと出会う機会をもってほしいですし、自分たち自身がそういう人になることをめざしてくれたらよいと思います。
《2022年3月5日 高校卒業式 校長式辞》
1 コロナ禍・ウクライナ戦禍と生き方の軸の模索
79期生のご卒業、おめでとうございます。2年前の政府からの突然の一斉休校要請に始まり、今回のオミクロン株の感染流行に至るまで、皆の高校生活のうちの2年間はコロナウィルスに翻弄され続けました。そのコロナのパンデミックに加えて、10日前のロシアのウクライナへの侵攻によって、世界はますます混迷の度合いを深め、不確実で不透明な時代を今後も生きざるをえない状況になっています。そうした時代でも懸命に重篤なコロナ感染者を救おうとする医療関係者や、戦争に反対し平和の回復を願う世界の人々の連帯の動きなど、人間の尊い行動に目を向けることも忘れてはならないと思います。社会も個人も危機的状況の中で、何を生き方の軸とし、一旦へこんだ心をどう回復させて、経験を次の糧にしていくか、おそらくこの2年間の中で皆が問われたことでもあり、まだ模索中の人もいれば日々の生活や行事の中で何らかの手立てを見つけ出した人もいるのではないかと思います。
79期生が担った2大行事のうち文化祭は映像の配信が中心になり、体育祭は午前中の実施という形にはなりましたが、それぞれを制限された範囲でアイディアを出し合い創意工夫しながら実行していました。特に体育祭は、その一年前に実施できなかった78期の卒業生たちの思いを受け継ぎつつ、まずは練習ができることに感謝しようと全校生徒に呼びかけながら、精一杯取り組んでいた姿が印象的でした。実は、この「感謝する」気持ちは最もポジティブな感情で、逆境や危機に直面していたとしても「感謝」の感情を持つことができたときには、すでに危機的な状況からは一歩抜け出し立ち直っていると言われています。体育祭委員長は、逆境から抜け出す手立てを全校生にメッセージとして伝えてくれていたとも言えるでしょう。
2 79期生の『カラマーゾフの兄弟』の授業
私は授業を担当したことのない学年ではありましたが、印象に残る授業はあります。高2の2学期後半から3学期にかけて、継続的に参観した現代国語の青柳先生の『カラマーゾフの兄弟』の授業です。今日の卒業式の生徒参加者は(コロナ感染対策のため他学年が参加できず)、この小説を読んだ経験のある79期生ですので、この小説を題材にして、話をしたいと思います。
一般的に言えば、高校でドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』のそれも「大審問官」の場面を、授業で扱うのは無謀です。しかし、内容的にも難解な箇所を丁寧に熟読しつつ、解釈の根拠を探し比喩を的確に言い換えながら、筆者の“イイタイコト”を掴み、正当な解釈を導き出す現国の授業として、しっかりと成り立っていました。おそらくグループ発表に当たって、テキストの記述に即してお互いの解釈を出し合い、グループとしての解釈を作り上げてゆく知的な面白さを感じた生徒は多かったのではないかと思います。青柳先生がご家族の事情で東京の学校に転任されることは知っていましたので、私からは、「正確に文章を読み解く授業としてならば、東京に行っても、『カラマーゾフ』を使って同じような授業は可能なのではないでしょうか?」と先生には申し上げたのですが「いや、カラマーゾフの授業は六甲の生徒でないとできないんです」という答えが返ってきました。
授業が進むにつれて、その意味が私なりに少しずつ解ってきました。あくまでも授業は国語としての解釈の授業であり、書かれている文章を根拠に正解を探っていくのですが、時に文字面(づら)だけ、表面的な言葉の意味を理解するだけでは、作者ドストエフスキーが本当に表現しようとした内容までは届きません。特に青柳先生が選んだ「大審問官」とその前の章は、キリスト教の思想というよりは人間としてのイエスがどういう人か、その心もわからないと解釈が根本からズレて、見当違いの表層的な理解になってしまう可能性がある箇所です。六甲の生徒たちは、たとえイエスについての知識は多いとは言えなくても、六甲の生活で、例えば弱い立場の人たちへの共感や、だからこそ生まれて来るこの世界への疑問や、権威を持った人の横暴さへの怒りや、対立の中で和解を望む心や人をゆるすことの大切さと難しさなどを体験しています。学校生活の中でのその共通体験が、こうした深い内容の小説の解釈にも生きてくるように思います。
例えば「人間に『自由』が与えられても、地球上に皆のためにあるはずの食べ物をうまく配分できない」という大審問官の指摘は21世紀にいたるまで本当です。「パン」-つまり生活の糧-を有り余るほど与えられている一部の富裕層が、自分の自由を行使してますます富み、貧しく飢えた人たちに生活の糧が配分されないために格差がますます広まってゆくという現代的な問題を、すでにイワンが描く大審問官は鋭く指摘しています。そうした世界の課題や疑問が、授業や社会奉仕の諸活動の中で生徒の間に共有されているからこそ、また、社会の矛盾や人間の弱さへの洞察を、授業や活動を通して経験しているからこそ、書かれている内容や登場人物への共感も生まれますし、共に解釈を真剣に考え合う場も生まれるのではないかと思います。
3 世界の理不尽さに苦しむ人々への共感からのキリスト教教育
そうした共通体験は79期生だけではなく、在校生も同様にしています。学年末考査一週間前でも、ロシアのウクライナ侵攻について、いくつかの学年では新聞などを用いながら考える授業をしていました。そうした授業を通して権力の横暴さやこの世界の理不尽さを知ることになります。
例えば、キエフの街で10日前までは普通に日常を平和に暮らしていた小学生の女の子が、その2日後には地下壕の中で、「爆弾のドーンという音で目が覚めた。今戦争が起こっていることはわかっている。死にたくない。」と涙を流しながら訴えています。その姿は、カラマーゾフの兄弟の中で「どうして罪のない子どもまで苦しまなくてはいけないんだ」というこの世界の理不尽さに対してのイワンの疑問とつながります。そして、彼の創作する大審問官の物語の中でイエスは終始無言ではあっても、大審問官への態度からは、無垢な人々が苦しむこの世界に根本的な疑問を持つ人間に、苦しみに無関心な人々よりも、共感し受け入れようとしているように読み取れます。それは、イエス自身も強大な権力による横暴さのために死に直面し、その理不尽さを丸ごと経験したうちの一人だからです。
六甲学院は、一般に言う「ミッションスクール」のイメージとは違って、一緒に声を合わせて祈りを唱えたり聖歌を歌ったり、校舎の中に十字架や聖像などを置いたりしない学校です。教えとして系統立てて、キリスト教について学ぶ機会もほとんどないかもしれません。しかし、知識としてそれほどイエスことは知らなくても、気づかぬうちにイエスの生き方や思いと通じる種が心の中に蒔かれて、いつの間にか育っているように思います。その共通の土壌が、「カラマーゾフの兄弟」の授業であれば、作者ドストエフスキーの伝えたかったメッセージをある程度の深みをもってつかむことにもつながり、解釈の表現の中にも自然に表れて来るのではないでしょうか。青柳先生のおっしゃる「六甲でなければ成り立たない授業」というのは、一つには、そういうことなのではないかと思います。
4 危機の中で心の支え・生き方の軸を見出すために(3つのヒント)
コロナ禍の中で、世界的な危機でもあり、時には個人にとっても精神的な危機でもあったこの2年間は、初めに話したように、何を支えにしてどう乗り切るかを問われていた時期であったと思います。危機を乗り切る手立てを探るヒントとして、「カラマーゾフの兄弟」と関連させながら最後に3点話したいと思います。
一つ目は、イワンにとって心の支えになるアリョーシャのような存在に出会ってほしい、または誰かにとってのアリョーシャのような人物になることをめざしてほしいと思います。
イワンは弟のアリョーシャに「大審問官」の物語を話した後に次のように言います。「もしほんとうにぼくに若葉を愛するだけの力があるとしても、おまえを思い出すことによってだけ、ぼくはその愛を持ちつづけていけるんだ。おまえがこの世界のどこかにいると思うだけで、ぼくは生きて行く気力をまだなくさずにすむんだ。」(江川卓訳)
どんなに理不尽な状況下にあっても人間らしさや善良さを失わない人物、人間関係がどれだけ険悪な最中でもより良い方向へむかうよう努力する人物、こういう人がいるから人間に対して失望しきらずに生きてみようと思える人物、そういう人物に出会ってほしいと思いますし、できれば、六甲を卒業する一人一人が、他者に生きる希望や気力や元気さをもたらす人になってくれることを願っています。
二つ目は『カラマーゾフの兄弟』の最終章に、アリョーシャが中学生たちにひとまとまりの話をする場面があります。アリョーシャが、暮らしてきた街を出て行くにあたって子どもたちとの別れのあいさつをする場面です。もしも、『カラマーゾフの兄弟』を最後まで読んでいないのであれば、大学に合格したらぜひ読んでみてください。アリョーシャは物語の終わりに次のように話します。
「子どもの頃から持ち続けられている、何かすばらしく美しい、神聖な思い出、それこそが、おそらく、何よりもすばらしい教育なのです。もしそのような思い出をたくさん身につけて人生に踏み出せるなら、その人は一生を通じて救われるでしょう。そして、そういう美しい思い出がぼくたちの心にはたった一つしか残らなくなるとしても、それでもいつかはそれがぼくたちの救いに役立つのです。」
よい思い出を共有できる仲間がいることは大切です。仲間とのつながりも、その仲間との思い出も、支えになりますし、アリョーシャが言うように、そういう大切な思い出が一つでもあれば危機的な場面でも自分の「救い」になりうると思います。卒業式予行の日に配られた卒業アルバムは、そのための役にも立つでしょう。
6年間をともに過ごした仲間とのつながりと思い出を、大切にしてもらえたらよいと思います。
与えられた命を人のために活かす‐「使命」に気づくこと
三つ目に紹介したいのは、高名な医師であり105歳まで生きて2017年に亡くなられた日野原重明(ひのはらしげあき)さんの話です。1970年、58歳の時によど号ハイジャック事件に巻き込まれて、命の危機を体験されています。犯人たちは乗客を人質にとって、北朝鮮の平壌(ピョンヤン)へ向かうように要求します。朝鮮海峡上を飛んでいるときに「平壌(ピョンヤン)までは時間があるから読み物を貸す」と犯人の一人が言ったその読み物リストの中に『カラマーゾフの兄弟』があったそうです。飛行機は平壌(ピョンヤン)まで直には行かず韓国の金浦空港に着陸して日本の政府とハイジャック犯たちとの折衝が始まり、日野原さんは4日間飛行機の中に拘束されます。もしも韓国軍の部隊が操縦室に突入して犯人たちを撃破しようとすれば、犯人たちはダイナマイトで自爆して、乗客たちは巻き添えになる危険性がある。そういう命の危機の中で日野原さんは犯人から『カラマーゾフの兄弟』を借りて、特に危険度の高まる夜間に、心の平静を保つためにこの小説を読んでいたといいます。
日野原さんは『カラマーゾフの兄弟』の扉ページ冒頭に引用されていた聖書のことば 「一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる」(ヨハネによる福音書12章24節)という一節を読んで「今ここで僕のいのちが失われたとしたら、自分の死は、果たしてその麦のように多くの実りをもたらすごとができるのだろうか。僕はそのことを自分自身が問われているように受け止めた」といいます。そして、当時の政府高官の一人が乗客の身代わりになるという折衝の結果、拘束から4日目に乗客全員が解放されました。日野原さんは金浦空港の地面に足をつけた瞬間、無事生還した感激とともに、「僕は再びいのちを与えられた」という「感謝」の思いが強く沸き起こったそうです。そして「これからの僕は、与えられたいのちを生きる僕なのだから、誰かのためにこのいのちを捧げよう、そういう気持ちが自然にわいてきた」といいます。「一時は失われることも覚悟したいのちが再び与えられ、こうして地球の地面を踏むことができた。僕はその恵みに対して、自分の名誉などのためではなくて、人のために何かをすることこそが使命だ、と素直に思いました」とも述べています。日野原さんはその後の人生を「第二の人生」というほど、この出来事が大きな転機になりました。
今回のコロナウイルスパンデミックのように、危機に直面することは辛いことではありますが、次を生きるための新しい人生観に気づく契機にもなりうるのではないかと思います。
自分の命は与えられたものであり、その生命を終えるときには豊かな実をむすぶような、人のために何かをする使命が与えられている、そうした気づきが得られたとき、また自分の使命が何かを自覚できたとき、それはこれからの危機を乗り切るための力にもなるだとうと思います。キエフの地下壕で「死にたくない」と訴えている女の子のために何ができるか、それは小説の中の問題ではなく現実の問題です。最初に述べましたように、ますます混迷の度を深めてゆく世界の中で、だからこそこの世界のため、人のために自分にできる何か、自分にとって生きる意味であり使命と言える何かを、79期生一人一人が見つけ出してくれれば、と願っています。
コロナ禍に「心の免疫」となる「元気の素」を見出す ~阪神淡路大震災の体験からメッセージを読み取る
1 心に危機的状況への免疫を持つこと
3学期が始まります。中学入試AB日程があるため、生徒たちにとっては、始まって一週間すると、5日ほど家庭学習の日が続きます。その期間もぜひ有意義に過ごして欲しいと思います。高校3年生にとっては、一週間後に大事な大学入学共通テストがあります。模試成績などを見ると全体として上向きに推移していますので、この一週間健康には留意して、前向きに頑張ってくれれば…と思います。また、阪神間で生活してきた人たちにとっては、忘れられない阪神淡路大震災の起こった1月17日が、5日間ある家庭学習日の真ん中にあります。震災のあった1995年当時、六甲学院に通っていた1,200人近い生徒の中には、幸い犠牲者はいませんでしたが、一緒に暮らしていた家族や近隣に住んでいた祖父母を失った生徒が数人いました。長い休校期間があり日常を取り戻すのに様々な困難があって時間もかかった点では、コロナ感染による緊急事態とも共通しており、六甲学院に限らず阪神間の学校は似たような体験をしてきています。
今回の新型コロナ感染によるパンデミックのように、社会にとっても個人にとっても生活面でも精神面でも危機を伴う出来事は、人生の中で何回かは起こりうるものだと思います。皆の世代でも、ワクチン接種をして体に免疫を持つことで、罹ったとしても深刻化するリスクが和らいだ人は多いと思いますが、精神的にもこの危機を乗り越える手立てを試行錯誤の中で自分なりに身に付けること、つまり心に危機的な出来事に対する免疫を持つことは、大切なことです。
2 行事・芸術・スポーツから心の免疫力を高める「元気の素」を見出すこと
心に免疫を持つこと、と言いましたが、コロナ禍の様々な制約の中で長期間学校に通い、実施条件が流動的に変化してゆく中で、体育祭や文化祭の準備をしたり、キャンプや研修旅行に行ったりした経験を通して、すでに自分自身を支えたり慰めたり元気づけたりする手立てを身に付けている生徒はいるのかもしれません。また、芸術やスポーツもそうした手立てになりうるのではないかと思います。
例えば、昨年実施された学校行事のひとつに秋の芸術鑑賞会がありましたが、角野隼人(すみのはやと)さんの講話とピアノ演奏に元気を与えられたり心を癒されたりした生徒は多いでしょう。私はお話の中で、学問にも芸術にも才能に恵まれた角野さんのような人でも、自分の将来の道について深く悩んでおられた時期がおありだったことや、「自分の可能性を広げられるのは自分だけれども、自分の可能性を信じてくれる人がいることが大切で、そういう人がいてこそ今の自分がある」と、自分のことを知り信じて音楽の道へ進むきっかけを与えてくれた他者の存在に謙虚に感謝しておられたことに感銘を受けました。演奏については、音にはなじみのあるはずのピアノという楽器が、このような美しく不思議な音色を奏でるものなのか、という新鮮な驚きと共に、楽しみながら聞くことができました。後から思い出しても、角野さんの演奏を聴いていた時間が特別な体験のように思えて、音楽には確かに人を癒し元気づける力があることを実感しました。
また、昨年の夏の東京オリンピックやパラリンピック、この正月の箱根駅伝など、スポーツを通して励まされた経験も、あるのではないかと思います。今年の箱根駅伝では、青山学院大学が優勝したのですが、昨年、直前にエースが怪我で走れなくなり、実力は十分あるメンバー達が動揺してレースがガタガタになってしまったため、この一年間は「(自分を律するという意味での)自律」をテーマに「させられる練習」でなく「自分でする練習」に変えたことで、今年は圧倒的な強さを見せたことが、レース後に紹介されていました。精神面がどれだけ実力発揮に影響するものか、「させられる」のでなく「自らする」集団になることが、その集団としての危機を乗り越えるのにいかに大切かを示す例として、興味深く聞きました。
行事に真剣に取り組むことや、芸術鑑賞、スポーツ観戦等、様々な経験の中で、元気を与えられたり、これからはこうしてゆこうという指針を与えられたりすることが、おそらく心の免疫力を高めることにつながるのだろうと思います。生徒にとっては、体育祭や文化祭などの行事への前向きな取り組みや、さまざまな行事から受け取るメッセージの中に、自分にとっての「元気の素」があったのではないかと思います。年末や正月に自分なりに1年の振り返りや目標設定をした人はいるかもしれませんが、自分にとって「元気の素」は何だったろうかと振り返ることが、これからの(こうしたらよいという)指針を見つけ出すことにも繋がってくるのではないでしょうか。
3 阪神淡路大震災時の日番日誌より(1)(危機を乗り越える指針を探すために)
-出来事の中で見えてきた”よい面”にも目を向けること
話の後半として、3学期が始まるこの機会に紹介したいのは、27年前の阪神淡路大震災の時につづられた生徒の日番日誌と感想記事(「阪神淡路大震災体験記(六甲学院)」)です。皆にとっては大先輩であり父親世代にもなる50期台の先輩達が、当時の危機をどう過ごし乗り越えたかの記録を通して、六甲学院にとってコロナ禍の今にも繋がる指針を、メッセージとして読むことができるかもしれません。
最初は学校が始まって3日目の日番日誌からです。
「2月8日 高1 月曜日の化学の授業の時、先生は『今回の地震があってからいろんなものが見えてきた』という話をされたが、僕もそういう経験がいくつかありました。僕の祖母の家は全壊し、その後全焼しました。僕の家はたいしたことがなかったので、それほどの被害があるとは思っていませんでした。とにかく父は、祖母の所へ行ったのですが、父はそこに近づくにしたがって”もうだめかもしれない”と思ったそうです。父は3時間掛かって祖母を救出したのですが、夜、家に帰って来た時は泥んこになっていました。
その後も避難所に何度も差し入れやお手伝いに行きました。父はもともとボランティアとかには興味を示さない人で、昔から僕は、お父さんがボランティアをすれば完璧な人なのに……と思っていただけに嬉しかったし、改めて父を見直しました。当たり前と言えばそれまでかもしれないけど、今回の出来事があってから、みんな人のあたたかさを知り、人を助けることを知ったと思います。これから大変な日が続くと思うけど、助け合って生活していかなくてはならないと思います。」
地震後の出来事を通して父親を見直し人のあたたかさを知ったという日番日誌の記事なのですが、皆はコロナ禍の出来事を通して見えてきたもの、新たに気づいたことがあったでしょうか?この出来事があったからこそ新たに気づくことのできた”よい面”にも目を向けることができれば、それも危機を乗り越える「元気の素」になるのではないかと思います。
4 阪神淡路大震災時の日番日誌より(2)
-これから入学する後輩への思いと勉強かできることへの感謝
2番目は延期した中学入試の前日の日番日誌からです。
「2月28日 高1 地震のために延びていた中学の入試が明日行われる。実に一ヶ月近く延期されたので、勉強道具が無くなった人、調子をくずした人もいるだろうし、より深く勉強ができた人もいるだろう。どちらにしろ、地震によって何らかの影響を受けた人々が六甲中学に入ってくる。これらの人々がこれまでと違った
六甲生になっていくかもしれない。少なくとも地震と受験が重なったことによって、新一年生は、この入試を忘れられないだろう。そんな新一年生がどう成長していくか、楽しみである。
最近、ようやく勉強が軌道に乗りだし、だいぶ日常生活に戻ってきたと思う。しかし、避難所で暮らしている人達のことを考えると、あまり進展がないようにも思える。3月6日から『45分、5時間授業』になるが、こういう状況で自分が勉強できることを感謝し、身を引き締めてやっていきたいと思う。」
後輩思いの校風は昔からなのですが、こうして震災を経てこれから入ってくる後輩を思いやる気持ちは六甲ならではのことなのではないかと思います。当時、街中の多くの公立の学校は教室が避難所として使われていて、数カ月間ほとんど授業ができない状況でした。授業があって勉強ができるということが有り難いことだと感じていた生徒達も多くいました。
5 阪神淡路大震災時の日番日誌より(3)
-ボランティア活動の体験と勉学との両立
3番目は地震から2ヶ月が経った3月16日の日番日誌です。家が住めない状態になって家族で一時神戸を離れていた高校1年生の記事です。
「2月5日、神戸に帰ってきて一番気になったのは友達のことと信愛学園のことだった。(信愛学園とは、当時社会奉仕活動として定期的に関わっていた御影の児童養護施設です。)2月6日から再開した学校の放課後に信愛学園に行って手伝いをさせてもらえることに決まった。その数日後、友達が西宮のボランティアを紹介してくれた。そこには京都から来た人、東京、九州からとあらゆる人がいた。仕事は炊き出しで、本部で材料を整えて現地の小学校で作るものだった。この活動で友達がたくさん出来たし、色々な経験もした。おばあさんが『ありがとう』と言ってくれた時の気持ちは言い表せないくらいだし、逆に配膳の時、少ないと言われておたまを取られ、勝手に入れられた時には多少腹が立った。
しばらくこの活動をしていて、つい最近気付いたことは、自分を見失っていたことだった。本来やらねばならない勉強をおざなりにしてきていたのだ。神戸に帰ったらボランティアをするぞ!! と思っていたから仕方がなかったが、最近は何とか両立させてやっている。これは長期戦だ。いつかは独立して六甲の生徒を集めて灘区での炊き出しをしたいと思っている。
1月17日の地震以来、2ヶ月がたとうとしている。それなのに街の風景、壊れた世の中は2ヶ月前とそう変わっていない。しかし、1月18日の夜の真っ暗な中の人々の心の中と、今の心の中とでは全く違うと思う。僕は2月18日からボランティアで元気村に行っていた。学校が終わってからだったので、3時頃から炊き出しを手伝った。6時半から晩ご飯ということになっていたので20分位前から行列が出来ていた。隣の御影公会堂の人達も来ていたのだが、日がたつにつれて食べにくる人が少なくなっていった。多分、何時までも沈んだままでいても、どうしようもない。さあ、やるか……と立ち上がっていったのだと思う。早く、活気に満ちた神戸をもう一度見たいし、神戸で思いっきり遊びたい。」
生徒が自主的にボランティア場所を探して活動している様子や、勉学もおろそかにしないように兼ね合いも考えつつボランティアをしている様子が伺えます。また、苦境に陥った分、郷土の神戸への愛情も強まっているように思われます。
6「阪神淡路大震災体験記(六甲学院)」より
-自転車で中1生の家庭を回る指導員
六甲の場合、地震があってから3週間ほどは休校になり、2月6日から始業時間を大幅に遅らせて短縮授業で学校が始まったのですが、生徒たちは、学校に来られるようになってからは学校の帰り道に、石屋川の公園に立てられていた炊き出しなどのボランティア基地「元気村」に寄ってボランティアをしたり、社会奉仕委員会が主催する長田区や須磨区の炊き出しボランティアに参加したりしていました。家が倒壊したため近くの学校で避難生活をしながら、その学校の救援活動を手伝う生徒もいました。当時中1だった57期生の記録の中には、次のようなものがあります。学校が再開する前の休校期間中のことです。
「指導員のA先輩が自転車で学校に関することを伝えに来てくれた。自転車で組の人を回っているのだという。とても感謝した。六甲の指導員はこのようなものだと感激した。」
震災直後は電話などの通信手段も通じにくく交通機関がマヒしてしまっていたため、自転車で1学期に世話をした中学1年生の家庭を、連絡伝達を兼ねて自主的に自転車で回る指導員がいました。道路自体も大きな地震の揺れで激しく傷んでいる場所が多い中で、通学校区の広い生徒の家を一軒一軒回るのは、大変だったはずですが、この指導員はよほど自分が指導した中1生のことが心配で、いてもたってもいられなかったのでしょう。
7 “Man for Others, with Others”
-他者と自分が共に危機を乗り越える生き方として
これらの六甲生が震災時に書いた記事に共通することは、日常を取り戻すために今生徒としてすべき事を大切にしつつ、自分が関わってきた後輩や友達や知り合いや家族のことを思いやり、直接には知らない後輩や市民の人たちのことも気遣い、自分の恵まれた環境に感謝しつつ、他者や社会のためにできることはしようとする姿勢です。六甲生として他者のために何かできることを探して行うことが、危機にある自分自身の心の支えともなり、心の免疫力を高め、元気の素ともなっていたようにも思います。それはコロナ禍にある今も同じなのではないかと思います。
他者との関わりの中で生きている私たちにとって、危機の中にあっても、あるいは危機の中にあるからこそ、他者のことを思いやり、他者のために他者と共に生きることのうちに、自分自身を支える何かや元気の源になる何かに出会えるのかも知れません。六甲学院に集い学ぶ私たちにとってだけでなく、おそらく人間にとって、“Man for Others, with Others”は、他者と自分が共に危機を乗り越えるために、めざす生き方の方向性を示しているように思います。
暗闇の中に輝く光-クリスマスとCompassion(共感する心)
◎ 登下校中の生徒の行動と善きサマリア人
12月に入って、学校の近くにお住まいの方から生徒の行いについての感謝やお褒めのお言葉を頂く機会があり、嬉しく思いました。一つは、小学一年生が水筒を落としてしまって、それが学校の横を流れる大月川まで落ちて、さらに下流に転がってゆこうとするところを、川底まで降りて拾い、小学生に渡したという中学生の行動です。もう一つは六甲川に架かる勝岡橋前の横断歩道のところで、雨に濡れた路面で滑って転び、うずくまって苦しそうにしている男性に生徒2~3人で近寄って助け起こし、その男性を支えて横断歩道を渡るまで付き添ったという高校生の行動です。人が困っていたり苦しんでいたりするのを見て助けようとする行動は、ただ放っておけないと思って自然に体が動くこともあれば、ためらってしまって勇気が必要だったりすることもあると思います。この話を聴いて私が思い出したのは、新約聖書のルカ福音書の「善きサマリア人」と呼ばれる有名な個所です。
善きサマリア人(ルカによる福音書10.29-37)
◎ Man for OthersとCompassion
◎ 「おとぎ話」ではないイエス・キリストの誕生の物語
◎ 2011年に被災地石巻で聞いた話
◎ 暗闇の中の光-”Man for Others”となるために
新型コロナによる感染拡大をきっかけに生活面でも精神面でも苦しむ人々が多いこの世界の中で、神が人の行いを通して困難の中にある人々を助け支え導かれますように、私たちが、その働きを暗闇の中に輝く光のように見いだすことのできる心の眼が育ちますように、また私たち自身が苦難の中にあっても世の光となる行動が取れる人間―Man for Others―へと成長しますようにと、クリスマスを迎えるにあたって祈り求めたいと思います。
以下は文化祭後の2021年9月27日の朝礼にて生徒に向けて話した内容です。
今日の朝礼では文化祭展示の感想を、「知的な感動」をテーマとして、話したいと思います。今年の文化祭展示は、文化部も同好会的な集まりも面白いものがありました。授業での取り組みや自分で課題を決めて探究した発表にも、見ごたえのあるものが多くありました。
◎ 高校3年生数学「エレガントな解法」展示について
高3の数学科の青木先生が企画した「エレガントな解法」は、特に興味深いものでした。生徒の切れ味の良い解答を並べて掲示していました。青木先生は「中学・高校の数学は、感動するものであり、少なくとも苦痛を与えるために発明されたものではない」「数学は無味乾燥な学問でなく汗と涙と感動の結晶である」と語ります。その先生が、「切れ味の良い解答を見つけた時の、感動する瞬間をとらえてほしい、その感動を分かち合ってほしい」と願って企画した展示です。“見事な、美しい解答に出会って、このアイディアがすごいと思ったり、この別解があるぞ! と思ったその時の知的感動の瞬間を味わって、人にシェアしてほしい、そういう学びの歓びが、大学での学問・研究活動の原点にもなる”というメッセージが込められた企画でした。
六甲生の数学に関しては、私は尊敬に近い思いで感心した出来事がありました。夏の奉仕活動の引率で阪急夙川駅から施設の最寄りのバス停「甲山」までのバス乗車20分ほどの間、2人の生徒が教科書もノートも筆記用具もなしで、数学の問題について数式を使って論じ合っていました。夏休みの朝に、奉仕作業に行くバスの中で、頭の中に同じ数式や図形を置きながら、世間話をするように数学の問題について楽しげに論じ合えるのが、日ごろ自分が教えている六甲生なのだと思って、驚いた体験でした。もしかすると皆にはそれほど不思議ではないことなのかもしれませんが、私にはそれなりの知的能力を備えた者同士でしか成り立たない光景のように思えました。別解の切れ味の良さをすぐに見抜いて感動できるというのも、ある程度理系的な知的レベルを共有していることが前提であるように思いますし、それができる恵まれた才能を持った生徒たちが、六甲には集まっていることも確かなのだと思います。
◎ 高校2年生の詩作展示と英作文展示について
高2の企画展示については、詩を創作したうえで「詩とは何か」についての自分の考えを加えて展示しているものが印象に残りました。見学時間が限られていてすべての作品を読み通せたわけではないのですが、詩そのものに作品としてよいものが多かっただけでなく、その後の「詩とは何か」のエッセイがよかったと思います。初めて詩を創作してみての感想や、本格的な詩論や、自作の解説になっているものや、時にはエッセイそのものが詩と対になった散文詩のように読めるものもあって、生徒たちの文学的な面での素養の高さが感じられました。
同じ高2の展示物の中では、英語でおもに人権に関わる社会の課題について、自分の意見を論じている企画の内容もよかったと思います。生徒たちの英語展示については、中1では「私のヒーロー」と題して尊敬する人について表現することから始まって、中2では「夏休みの思い出」を表現する課題に取り組み、さらに高2になると抽象的な社会問題についても論じることができるようになってゆく、その中学の初期段階からの英語の表現力にも感心しましたし、その表現力と共に社会的な意識が広がってゆく成長の過程も、英作文展示から見ることが出来たように思いました。
◎ 中学1年生の地学展示と前島キャンプ体験発表について
中学1年生の授業展示企画も充実したものでした。地学をテーマとした展示では、身近な出来事や授業で見聞きしたことから疑問に思ったことや関心を持ったことの中で、研究したいものを選んで探究していました。100万年前には無かった六甲山がどうして出来たのか、有馬温泉の近くには活火山がないのになぜ温泉が湧き出るのか、そこで鉄分を含む赤い温泉と透明な塩水の炭酸温泉が出るのはなぜか、東北地方の三陸沖で大型地震が多く起きるのはなぜか、30年以内に高い確率で起こると言われている南海トラフ巨大地震はどのような仕組みで発生するのか、南アメリカ大陸の東側とアフリカ大陸の西側とがなぜパズルのようにはまるのか、その二大陸はなぜもともと一つの大陸だったといえるのか、そうした純粋に知りたいと思って始めた探究活動は、やはり見るものを感動させる何かを持っているようにも思いました。
中学1年生の前島キャンプでの体験発表も心に残ったものの一つでした。展示の中では経験した出来事だけでなく、その時に感じた思いまでよく表現されていました。キャンプファイヤーでさまざまなゲームやスタンツをして盛り上がった後に、その残り火で小グループに分かれて先輩たちと静かに語り合ったミニファイヤーの時間がよかったという発表もありました。「ミニファイヤーについては、それほど期待していなかったのだが、先輩を交えて色々なことを言い合ううちに心を許せて、その場にいた友達・先輩と一つにまとまった気がした。」「残り火の周りに集まって神秘的ともいえるような、それまで感じたことのない感覚を味わった」、という感想もありました。友人や先輩とそうした時間を持つことが出来ることも、六甲の行事の良さの一つだと思います。
◎ 知的な探究の場・知的感動を分かち合う場として-学習センターの活用
六甲は、中一指導員と中一生徒とのつながりから始まって、クラブや委員会や行事などで先輩・後輩との人間的なつながりを深める機会があることが特徴なのですが、今回の文化祭展示を見て、生徒同士が知的な面でも、お互いにもっと刺激し合える環境があるとよいと思いました。
高3の数学の授業企画の意図ともつながることなのですが、知的感動を分かち合う習慣がもっと日常的に六甲にあればよいと思います。その機会は学校の教室内でも登校時・下校時でも可能なのですが、本格的にグループで探究し生徒同士が知的な刺激を与えあう場所として、六甲には学習センターがあります。例えば、学習センターには4名から8名ほどが利用できる2室のグループ学習室があるのですが、なぜそういうスペースを作ったのかというと、隣のレファレンスコーナーで調べた内容をもとに、生徒たちが資料を持ち寄りながら図書館内で討議する場所が必要だと思ったからです。また、グループでの発表準備のための話し合いやプレゼンのリハーサルをしたり、グループで学び合いたいという生徒が、白板も使いながら討議し合ったりする場を想定していたからです。生徒の自主的・主体的な学習活動をするための貴重な場所、どの生徒も希望すれば使える場所として創られたスペースです。実際、生徒たちのグループが自主勉強として使い、白板に数式などが並んでいた時期がありました。今は、コロナ禍の感染予防のために使用に制限がかかっているのですが、感染者数も落ち着き生徒のワクチン接種が進めば、もとのような形で使えるようにしてもよいのではないかと思っています。とりあえず、10月に入り緊急事態宣言が解除されたら、グループ学習室のうち一部屋を4人まで、感染対策はした上で貸し出すことを始められれば、と準備しています。
◎ 進路に繋がる日常の授業の中の知的感動について
文化祭は終わって日常に戻ったのですが、日常の授業の中でも、頭と感覚を研ぎ澄ませれば知的な感動につながるものは多くあると思います。人によって何に興味を感じるかは違うと思うのですが、過去の卒業生の中には、大学で何を学ぶかを選ぶ上で、学校での授業内容に影響を受けた人は多くいます。例えば、政治経済の授業を受けて、社会経済のしくみを専門的に知りたいと思ったり、生物で遺伝について学んで医学の観点から遺伝を研究したいと思ったりして、進路を決めた卒業生は、私が担任した生徒の中にもいました。
六甲生の能力は自分たちが思う以上に高いのではないかと私は思っています。知的な感動を分かち合う仲間と出会い、その能力をお互いに磨き伸ばし活かす場に、六甲学院がなってほしいと願っています。
以下は2021年8月30日 2学期始業式にて生徒に向けて話した内容です。
不自由さの体験からネットワーク作りへ ―コロナ禍の中で文化祭を迎えるにあたって
■ 不自由の経験と誰かの役に立つ仕事
2学期が始まりました。皆の夏休みは、どうだったでしょうか? 想像以上にデルタ株の新型コロナウイルス感染が拡大したために、昨年に引き続いて、部活動も家族旅行や友人と遊びに行くことなども、思うようにはできなかった生徒が多かったのではないかと思います。
最近学校に送られてきた就職希望者向けの募集ポスターの中に、「不自由だけは経験した」というキャッチコピーがありました。確かに今の生徒の共通体験は「不自由さ」なのかもしれません。ポスターは次のように文章が続きます。「今、不自由を経験していない人はひとりもいない。でも果たして、考えたかどうか。自分にとって何が自由で、何が不自由か。……そして、他者の不自由も少し想像する。これも立派な経験だ」。文章の後半には、「面接でよくある質問。『これまでどんな経験をしてきましたか』上等だ。自分の不自由を思いっきり語ろう」とあります。そして、この文章は、「不自由の経験は、きっと『誰かの役に立つ仕事』につながる。」という言葉で結ばれます。(兵庫県行政職員募集ポスター)
誰もがこの「不自由」な状態にうんざりして、ここから抜け出したいと願っています。不満や弱音を吐きたくなることもあるでしょう。政治や行政に向けての批判や怒りをもとに、社会の何をどう変えたらいいのかを考えることも大事だと思います。と同時に、この言葉にあるように「自分にとって何が不自由で、この不自由感はどこからくるのだろう?」という問いは、考える価値があるように思いますし、誰もがしているこの不自由の経験が、将来別の誰かの、また何かの役に立つことがあるのかもしれない、とも思います。
パラリンピックの競技を視聴していてよく紹介される言葉に「失われたものを数えるな。残されたものを最大限に生かせ」というものがあります。パラリンピックの父、グットマン博士の言葉です。障害による不自由さだけでなく、私たちの日常的な不自由さに対しても、大切なメッセージが込められているように思います。今与えられている不自由さを、ただ不満に思うのでなく、その限られた条件の中で、残されているものを最大限に活かして、できるだけのことを精一杯する体験は、きっと不透明で不確実なこれからの時代を生きる私たち皆にとって、貴重なものになるはずです。
■ 今年の文化祭の目標と東京オリンピック
文化祭があと3週間に迫っています。今年の文化祭のテーマは「大きな一枚岩」を意味するギリシャ語の「モノリス(Monolithos・英Monolith)」であると文化祭委員長から発表されました。一人ひとりが城の石垣のように組み合わさり団結して、六甲学院が大きな一枚岩の集団であることを皆が実感することが、今年の文化祭の目標なのでしょう。同時に委員長からは、「全力で楽しむ」ことが、もう一つの目標として挙げられていました。委員長は自分が小学校の頃に六甲学院の文化祭を見学しに来て、先輩たちの楽しんでいる姿(例えば仲間と協力して作ったピタゴラスイッチが成功した時の喜ぶ姿)から、自分も喜びを感じて感動したという体験を紹介していました。
「一枚岩」のように結束したチームだと感じたり、人が心から「楽しんでいる」姿が、周りの人々にも感動を与えるということは、身近に見聞きする体験の中でもあると思います。今回の東京オリンピックやパラリンピックを視聴した中にも、そうした場面はあったのではないでしょうか?
例えば、水泳競技はメドレーリレーを除いて個人のタイムを競う競技ですが、私は今年の日本選手には様々な場面で、個人を超えたチームとしての絆を感じました。本多灯(ともる)選手は、競泳男子200メートルバタフライの決勝進出時点で8番目でありながら、決勝では銀メダルを獲得しました。まだ10代の本多選手は、日本代表のチームメイトの先輩たちからアドバイスを受け支えられていた一方で、彼の素直で前向きな性格はチームの雰囲気によい影響を与えていたようです。決勝後のインタビューで、決勝の時に心がけていたことを聞かれて「誰よりも楽しむこと」を挙げていました。
その他の種目でも、互いに切磋琢磨してきたメンバー同士が、競技や演技を競い合いながら、そのスポーツそのものを楽しんでいるような場面がいくつもありました。特に国籍や民族を超えたつながりを感じたのは、スケートボードです。皆と同じ世代の青年たちがスケートボードをする姿には、他の競技と一味違った自由な雰囲気が感じられて新鮮に思えました。国の違いも勝敗も超えて競技を楽しんでいる姿、成功しても失敗しても生き生きとして笑顔を絶やさず、互いを称えたり励ましたり慰めたりする姿など、10代中心の若い世代が国や民族の壁を軽々と超えて、相手を競い合うライバルではなく仲間として大切にしている様子が伝わってきました。「こうした違いを超えたつながりの輪が世界中に広まってゆけば、この世界は大丈夫」という希望も感じることができました。
■ 「違いを超えた一体感」と「楽しむこと」から世界のネットワーク作りへ
文化祭テーマの「モノリス」と「全力で楽しむ」ことともつながることなのですが、一つに結束した前向きな集団(チーム)になることと、一人ひとりがそのチームの支えを感じつつ、今自分のしていることを心から楽しむことが、個々の能力を最大限に引き出す、ということは、スポーツに限らず、文化活動でも研究活動でもありうることだと思います。私たちは―特にこれまでの大人たちは―「楽しむこと」を遊びや娯楽と結びつけがちですが、真剣な努力が必要なスポーツや学問の分野においても個々の能力を引き出す心の状態として「楽しむこと」を見直す必要があるように感じます。これからの文化祭への取り組みだけでなく、日常の部活動や委員会活動やグループで取り組む学習などでも「楽しむ」心を忘れずに生かすことができたらよいと思っています。
さて、今回の東京オリンピックでは、若い人たちが国籍や民族や言語の隔てを軽々と超えて、つながりを持つ姿が印象に残ったのですが、六甲では高校2年生、1年生が海外のイエズス会学校の生徒たちと英語を使ってオンラインで交流する機会がありました。感想を読むとオンラインでもこれだけ印象深い体験になるのか、と思えるような交流経験をしていたことが伝わってきます。1日目にうまくコミュニケーションができずにやや落ち込んでいた生徒たちが、2日目には自分たちが会話のリーダーシップを取るというチャレンジを課すことで、それこそ姉妹校生徒とのやりとりを「楽しんでいる」様子も見られました。
イエズス会教育の目標の一つは、世界に800以上もあるイエズス会系学校のつながりを生かしたグローバルなネットワーク作りです。それは、世界をより良い方向へ変えてゆく”仕えるリーダー”のネットワークです。また、国連が提唱する、持続可能な世界を目指すSDGsの取り組みも、17の課題のうちの17番目は「パートナーシップ」です。先進国側の人々が発展途上国の人々を支援するだけでなく、国や立場を超えてネットワークを作りながら弱い立場の人々をサポートする社会のしくみ作りを目指しています。イエズス会教育も国連も、弱い立場の人々がより人間らしく生きられる世界とするためにネットワークを作ってゆく方向性は共通しています。グループで課題に取り組む文化祭での体験や、姉妹校との交流体験などが、将来の社会をよりよく変えるネットワーク作りへと生かされてゆくことを願っています。
■ コロナ禍の制限の中で創意工夫を―「残されたものを最大限に生かす」精神で
最後に、デルタ株の感染についての一般的な注意をしたいと思います。
デルタ株の感染力の高さ、急激に重篤化する危険性、そしてこれまで感染する割合が少ないと言われていた20歳以下の若い人たちにも感染することなど、これまで以上の感染防止対策が新学期に入ってから必要になります。デルタ株が広まる前には学校での感染ケースはそれほど多くはなかったのですが、今は近畿圏でもクラブ活動の試合などを通じて数校でクラスターが発生し、その影響で大阪方面には最近文化祭を中止にせざるを得ない学校もありました。
8月下旬に兵庫県からは原則的にクラブはしないように通達があり、六甲学院でも、公式戦が迫る時期の練習を除いて部活動を中止にせざるをえません。クラブの原則中止は文化部も同様ではあるのですが、文化祭を文化部の公式戦とみなすことで、準備のための活動を全面的に休止することはしないことにします。ただ、今の感染状況を考えると活動は制限をせざるをえません。文化祭自体を中止にする事態になることを避けるための処置と考えて、今与えられた条件の中で、できる範囲での準備をして文化祭を迎えてほしいと思います。
今年もコロナ禍の中での文化祭になり、特に展示発表の中心になる文化部は昨年度に引き続き、夏期休暇に県外へ泊りがけの合宿(研修旅行)をした上で、その研究成果を発表する形を取ることができませんでした。それでもそれぞれのクラブは日帰りで行ける県内の見学場所を探したりしながら、活動を工夫して充実した発表を試みていると思います。文化部以外の生徒たちもそれぞれに、関心の持てるテーマを選んで、小グループに分かれて取り組みながら、発表をする予定です。
準備過程でも本番でもコロナ禍の制約のある文化祭ではありますが、そうした最中であるからこそ、それぞれのグループが結束し創意工夫をしながら活動することに、やりがいや楽しさを見出してくれたらよいと思います。不自由ではありますが「失われたものを数えるのでなく、残されたものを最大限に生かす」精神で、個々の個性や能力を発見したり生かしたり伸ばしたりする機会に、この文化祭がなってゆくことを願います。